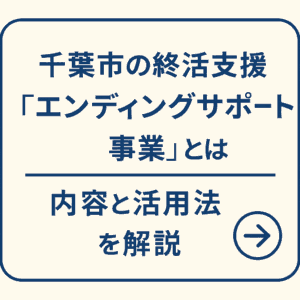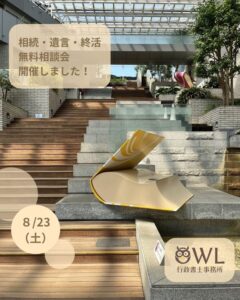1. はじめに
空き家を相続したものの、「誰も住む予定がない」「どう処分すべきか分からない」と悩む方は少なくありません。2023年の空き家法改正により、放置していると固定資産税の優遇が外れ、税負担が一気に増える可能性もあります。
本記事では、相続前に取れる準備と、相続開始後に選べる処分・活用方法を体系的に整理しました。法改正のポイントを踏まえ、専門的な視点から実務上の留意点もあわせて解説します。
2. 2023年の空き家法改正のポイント
従来の制度では、空き家が「特定空家」と判断された場合(著しく倒壊の危険がある、衛生上有害、景観を著しく損なうなど)、住宅用地特例による固定資産税の軽減が外され、税額が最大6倍になることがありました。
改正後は、そこまで深刻でなくても 「管理不全空家」 と認定されれば同様の扱いとなる可能性があります。例えば:
- 草木が繁茂して近隣に迷惑をかけている
- 建物が傷んで外壁が落ちそう
- 適切に換気・清掃されず害虫が発生している
こうした段階で早めに行政からの指導対象となり、固定資産税の軽減が受けられなくなるのです。つまり「使わないから放置しておこう」が、これまで以上にコスト高になるというわけです。
3. 相続前にできる空き家対策
将来、実家や所有不動産が空き家になることを見越して、相続前に準備できる選択肢はいくつかあります。早めに動くことで、相続後のトラブルや余計な税負担を防ぐことにつながります。
- 遺言で方針を明確にする
誰に相続させるかを指定しておけば、共有状態による処分の停滞を防げます。売却指示や換価分割の指定も可能です。 - 家族信託の活用
親が元気なうちに「将来の管理や処分権限」を信頼できる家族に託せます。認知症など判断能力が低下しても、スムーズに売却や活用が進められる点がメリットです。 - 生前贈与や持ち家の整理
早い段階で子世代へ贈与して活用してもらう方法もあります。相続税対策として有効になるケースもあるため、税理士との連携が必要です。 - リフォームや利活用を検討
将来的に賃貸や二地域居住の拠点として使えるよう、リフォームや用途変更を視野に入れることも有効です。空き家バンクや自治体補助金制度の下調べもおすすめです。 - 家族会議を開く
「実家をどうするか」というテーマは、感情面で揉めやすい部分でもあります。元気なうちに家族で意向を確認し、処分・活用の方針を話し合っておくことが、のちの対策として最も現実的で大切です。
このように、相続前にできる対策は「法的な仕組みづくり」だけではなく「資産活用の検討」「家族間の意思確認」など幅広い視点があります。
4. 相続後にできる空き家の処理
実際に相続が発生してから「誰も住まない家が残った」というケースは非常に多いです。特に親が亡くなった後に実家が空き家になるケースでは、相続人が複数いて話し合いが進まず、結局何年も放置されることも珍しくありません。
ここでは、相続後に取り得る選択肢を整理します。
(1)相続放棄を検討する
「遠方で管理できない」「建物が老朽化して資産価値が低い」といった場合、相続放棄も一つの方法です。相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになり、空き家を含めた財産を引き継がずに済みます。
ただし注意点として、
- 相続放棄は原則として「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要がある
- 預貯金などプラスの財産も一緒に放棄することになる
という点があります。
「空き家はいらないが預貯金は欲しい」という調整はできないため、総合的な判断が必要です。
(2)遺産分割協議で所有者を決める
相続人が複数いる場合、空き家の扱いを誰にするかを話し合いで決める必要があります。共有状態のままにすると、売却や解体など重要な処分をする際に全員の同意が必要になり、結局何も進まない事態になりがちです。
- 誰かが住む予定があるなら、その人が単独で相続する
- 誰も住まないなら、売却前提で一人が引き取り、その代わりに金銭で調整する(代償分割)
といった形で、なるべく単独所有にまとめることが望ましいです。
(3)売却する
「住む予定がない」「管理の負担を避けたい」場合、売却は現実的な選択肢です。
特に「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度があり、相続した空き家を一定条件で売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない住宅
- 相続から3年以内の売却
- 相続人が誰もその家に住んでいない
といった条件がありますが、税負担を軽減できる大きなメリットがあります。
(4)賃貸や管理委託をする
売却までは考えていない場合でも、賃貸として活用すれば家賃収入が得られ、劣化を防ぐことにもつながります。
また、自分で管理できない場合には管理会社に委託する方法もあります。月数千円程度の管理委託料で、定期的な見回りや草木の手入れを代行してくれるサービスがあります。
(5)解体・更地化する
老朽化が進んで危険な場合や、売却のために更地にした方が有利な場合は解体も選択肢になります。ただし注意点として、建物を解体すると「住宅用地特例」が外れるため固定資産税が高くなることがあります。
「解体後すぐに売却できる見込みがあるか」を不動産会社に確認してから判断すると安心です。
(6)地域の空き家活用制度を利用する
自治体によっては「空き家バンク」に登録して移住希望者に貸したり売ったりする制度があります。
また、改修費の補助金を出してくれる自治体も増えていますので、「処分に困った空き家」が思わぬ形で利活用できることもあります。
5. まとめ
2023年の法改正によって、空き家を「とりあえず放置しておく」ことのリスクは格段に高まりました。
相続前に遺言や生前対策をしておくことが理想ですが、相続後であっても、売却・賃貸・管理委託・解体といった多様な選択肢があります。
「相続してしまった空き家をどうするか?」という状況は誰にでも起こり得ます。まずは自分の立場でどの選択肢が現実的かを整理し、専門家や自治体の制度も活用しながら、早めに動くことが大切です。