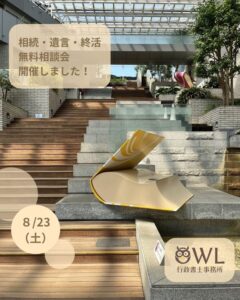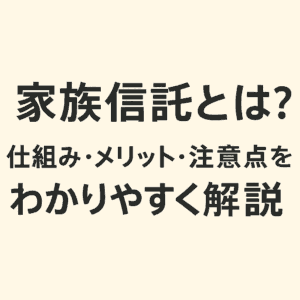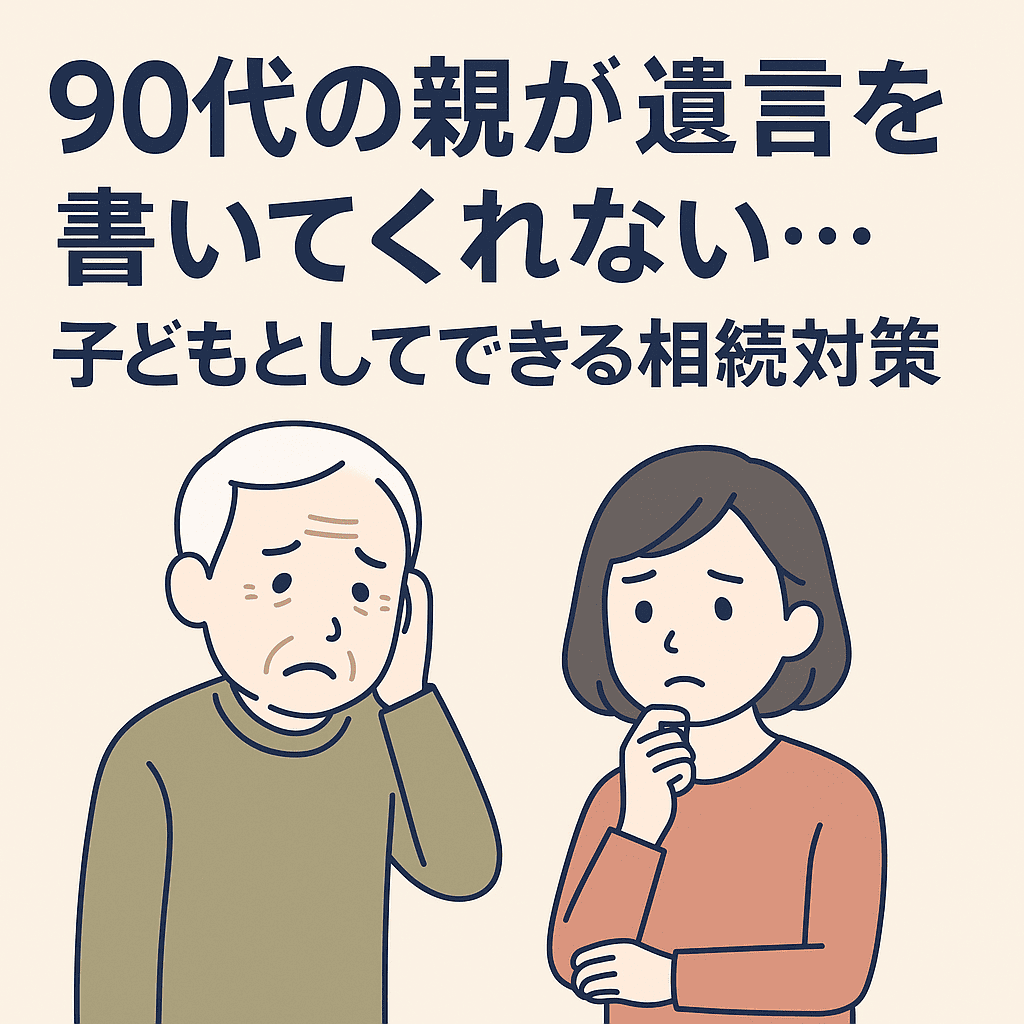
親が90代になっても「遺言はまだ書かない」と言うことは珍しくありません。
しかしそのまま相続が始まると、子ども世代の兄弟姉妹で遺産分割協議をしなければならず、ときに話し合いが紛糾することもあります。さらに、子どもが先に亡くなっていた場合には、その子(孫)が代襲相続人として協議に参加し、思いがけず孫世代まで相続争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。
「親が遺言を書いてくれないから仕方がない」とあきらめるのではなく、子どもとしてできる備えを考えることが大切です。本記事では、90代の親が遺言を残さない場合に想定されるリスクと、子ども世代としてできる現実的な相続対策について解説します。
1. 親が遺言を書かないと何が起きるか
1-1. 相続は兄弟姉妹の“話し合い”に委ねられる
親が遺言を残さずに亡くなった場合、相続人である子どもたち(兄弟姉妹)は、遺産分割協議を行って誰がどの財産を引き継ぐのかを決める必要があります。
現金や預金のように分けやすい財産なら話はまとまりやすいですが、自宅や土地、賃貸用の不動産など「分けにくい財産」が多いと、意見が対立して協議が長引くことは珍しくありません。
1-2. 不動産は“共有”になりやすく、管理が難しい
協議がうまくまとまらず、とりあえず法定相続分に応じて共有名義にすることもあります。しかし、共有不動産は修繕・売却・賃貸などの管理にあたって相続人全員の合意が必要になり、将来のトラブルの種になりやすいのです。
特に親の自宅やアパートが残されるケースでは、「誰が住むのか」「誰が管理するのか」で感情的な対立が起きやすく、兄弟姉妹の関係が悪化する例も少なくありません。
1-3. 子どもが先に亡くなれば“孫”が相続に参加する
さらに長寿社会の今、子ども世代が親より先に亡くなるケースも決して珍しくありません。その場合には、亡くなった子の子ども(孫)が代襲相続人となり、遺産分割協議に参加することになります。
つまり、遺言がないと「子ども世代の話し合い」で済むはずだった相続が、「孫世代を巻き込んだ話し合い」へと広がってしまうのです。若い世代にとっては、突然、祖父母の相続問題に関わらされるのは大きな負担であり、思わぬ争いの火種にもなりかねません。
2. 孫世代を巻き込むリスク
2-1. 想定外のメンバーが協議に加わる
代襲相続によって孫が相続人となると、遺産分割協議のメンバーが一気に増えます。祖父母の相続は「親(子ども世代)だけで話し合えば済む」と思っていたのに、孫までテーブルに着くことになれば、それだけ合意形成は難しくなります。
特に、孫が複数人いる場合は利害がさらに複雑になり、協議の調整に時間も労力もかかるようになります。
2-2. 孫世代にとっての精神的な負担
孫からすると、「祖父母の遺産分割に自分が関わるなんて思ってもみなかった」というのが正直なところでしょう。
自分が幼い頃に世話になった祖父母や、仲の良かった叔父・叔母と対立する立場に立たされることは、大きなストレスになります。また、相続財産が不動産の場合は、修繕や管理など現実的な責任を負わされることもあり、孫世代にとっては心理的・実務的に重い負担となります。
2-3. 世代をまたぐ“争族”に発展する可能性
孫世代が相続に巻き込まれると、争いは二世代にまたがることになります。「親の代で片づけてほしかった」という不満が孫の心に残り、親族関係が長期的に悪化することもあります。
結果として、「相続争いを次世代にまで引き継いでしまう」という、まさに避けたい事態になりかねません。
3. 子ども世代(自分)にできる対策
3-1. 一次相続でできること
親が遺言を書いてくれない以上、相続人同士で話し合うしかありません。
兄弟姉妹の間で早めに意見をすり合わせ、できるだけ共有名義を避けるように工夫することが重要です。共有にすると、将来の売却や管理で全員の同意が必要となり、手続きが複雑になるからです。
また、不動産や預貯金の評価額を事前に把握しておくことで、感情的な対立ではなく、数字に基づいた冷静な協議を進めやすくなります。必要であれば、専門家(行政書士・司法書士・税理士など)に同席してもらうのも効果的です。
3-2. 二次相続を見据える
「孫を相続に巻き込みたくない」という気持ちは、自分の相続に備えることで対応できます。
たとえば、自分が一次相続で取得した財産については、自分の遺言であらかじめ承継先を指定しておくことができます。これによって、自分の死後に子ども(孫)が祖父母世代の揉め事を引き継がされないようにすることが可能です。
つまり、「親の遺言がないから仕方がない」とあきらめるのではなく、自分の遺言で“二次相続の混乱”を防ぐことが、現実的な解決策となります。
3-3. 親と子、両世代で準備を進める
理想をいえば、親が遺言を残してくれるのが一番シンプルです。ですが、それが難しい場合には、自分自身が「次の世代を巻き込まない工夫」をしておくことが大切です。
一次相続を円滑に進める努力と、二次相続への備え。この両方を意識することで、「相続争いを次の世代に持ち越さない」という目的を果たすことができます。
4. まとめ|巻き込まない相続のために
親が90代になっても遺言を書かないままというケースは決して珍しくありません。
しかし、その場合には子ども世代の兄弟姉妹での遺産分割協議が避けられず、さらに子どもが先に亡くなれば孫世代まで巻き込む事態になりかねません。相続分の割合よりも、「誰が話し合いに参加するか」という点が実務上の大きな負担となります。
だからこそ、子ども世代にできる現実的な対策は次の3つです。
- 兄弟姉妹で早めに話し合い、共有を避ける工夫をする
- 自分が相続した財産については、自分の遺言を残して二次相続に備える
- 必要に応じて専門家を交えて冷静に調整する
理想はもちろん、親が遺言を残してくれることです。しかし、それが難しい場合でも、自分の行動次第で「孫世代を巻き込まない相続」に近づけることは可能です。
“争いを次世代に持ち越さない”という視点を持ち、今から準備を進めてみてはいかがでしょうか。
おすすめの関連記事
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
「うちも同じ状況かもしれない…」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
親世代が遺言を書かないとき、子どもとしてどんな備えができるのか、一緒に整理してみませんか?
初回60分は相談無料です。ご来所のほか、オンライン(Zoom)にも対応していますので、安心してお話しいただけます。」