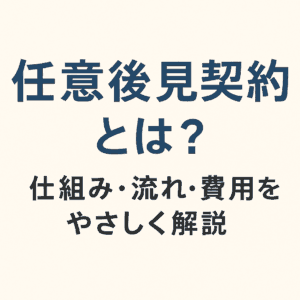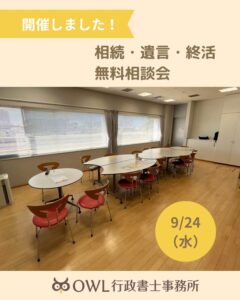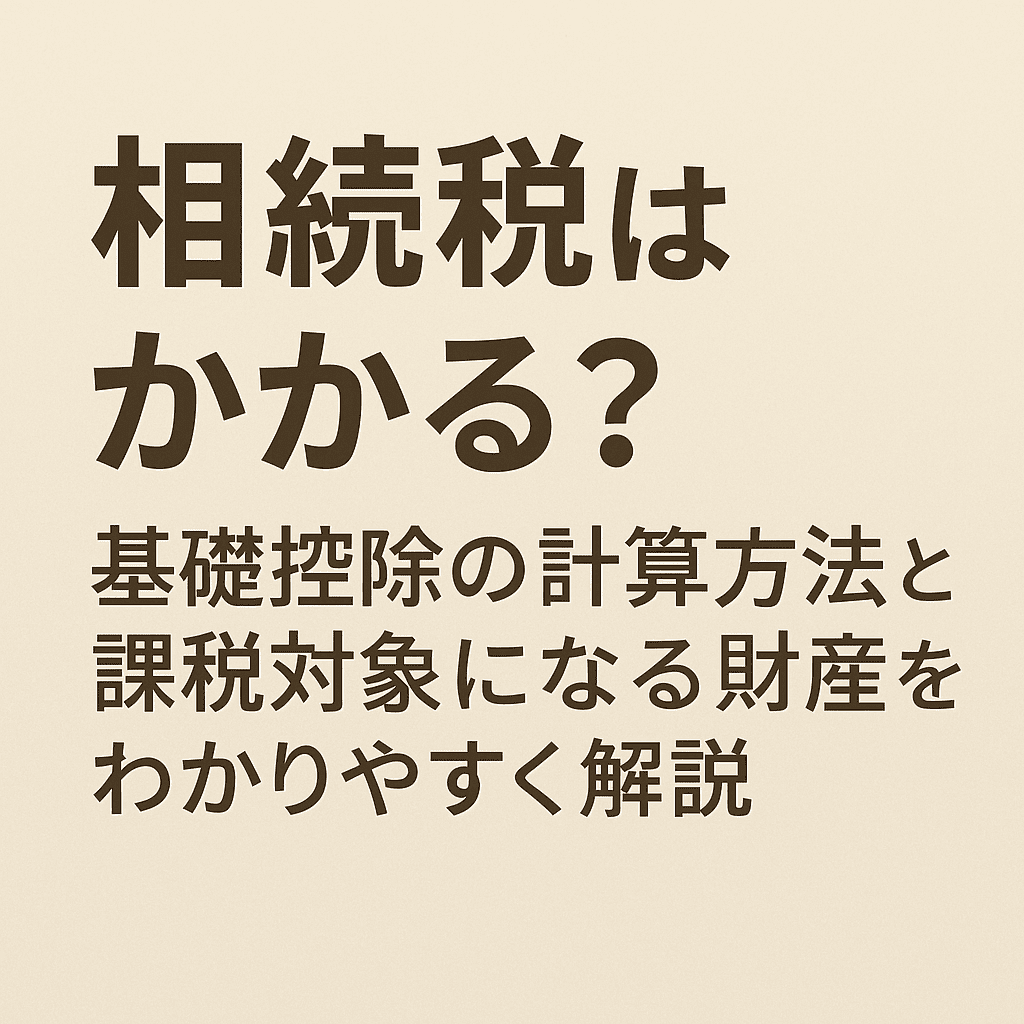
はじめに|「相続税がかかるかどうか」を知りたい人へ
相続税は「相続が起きたら必ずかかる税金」と思われがちですが、実際にはかからない方が多いのが現状です。国税庁の統計によると、相続税を納めているのは全体の1割に満たない程度。つまり、9割近くの人には相続税がかかっていません。
それでも「うちの場合はどうなんだろう?」と不安になるのは当然です。相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額と「基礎控除」と呼ばれる仕組みによって決まります。この記事では、基礎控除の計算方法や、相続財産に含まれるもの、生前贈与の扱いなどの重要ポイントをやさしく解説します。
相続税の仕組み
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産に対してかかる税金です。ただし、すべての人が対象になるわけではありません。
相続税がかかるかどうかは、次のように判断します。
- 相続財産の総額を把握する
- 基礎控除額を計算する
- 「相続財産の総額 - 基礎控除額」がプラスなら相続税の申告が必要
つまり、財産が基礎控除の範囲内に収まっていれば、相続税はかかりません。
基礎控除とは?計算方法と具体例
相続税がかかるかどうかを判断するときに、最初の目安となるのが「基礎控除」です。基礎控除とは、一定の金額までは相続税がかからないという仕組みのこと。
計算式は次のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
ここで注意したいのが、「法定相続人の数」をどう数えるかという点です。
たとえば、遺言書に「すべての財産を妻に相続させる」と書いてあったとしても、基礎控除の計算上は「法定相続人の人数」でカウントします。子どもが2人いれば、実際に相続するのが妻1人だけでも「妻+子2人=3人」として数えることになります。
具体例
- 相続人が「妻+子ども2人」の場合
基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
→ 相続財産が4,800万円以下なら相続税はかからない。 - 相続人が「妻のみ」の場合(子どもがいないケース)
基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
→ 相続財産が3,600万円以下なら相続税はかからない。
このように、同じ財産額でも相続人の人数によって基礎控除額は大きく変わります。
相続財産に含まれるもの
相続税を計算するうえで重要なのが、「どんな財産が相続財産に含まれるのか」という点です。現金や不動産だけではなく、思った以上に幅広い財産が対象となります。
不動産(土地・建物)
自宅や別荘、貸しているアパートなど、すべての不動産が対象になります。土地については路線価や固定資産税評価額をもとに評価されますが、専門的な計算が必要になることも多いです。
預貯金・株式などの金融資産
銀行預金や郵便貯金、株式や投資信託なども相続財産に含まれます。現金のほか、証券口座にある金融商品も忘れずにカウントしましょう。
生命保険金・死亡退職金
被相続人が契約していた生命保険の死亡保険金や、勤務先から支給される死亡退職金も相続財産に含まれます。
ただし、生命保険金や死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があるため、実際には全額が課税対象になるわけではありません。
借金や葬式費用はマイナスできる
マイホームの住宅ローンや、その他の借金も相続財産から差し引くことができます。また、葬儀にかかった費用(火葬やお通夜・告別式にかかった費用など)も控除の対象です。
「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も考慮して計算するのがポイントです。
生前贈与はどう扱われる?(持ち戻しの考え方)
「相続が始まる前に贈与しておけば、相続税の対象から外れるのでは?」と思う方も多いでしょう。ところが、相続税の計算では「持ち戻し」といって、生前贈与した財産を相続財産に戻して考えるルールがあります。
原則は「3年以内の贈与は戻す」
現行の制度では、相続開始前 3年以内 に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に含めて相続税を計算します。
たとえば、亡くなる2年前に子どもへ現金を贈与していた場合、その金額は相続財産に足し戻されます。
法改正で「7年以内」に延長
2023年の税制改正により、この持ち戻し期間が 3年から7年に延長 されました。
ただし、すぐにすべての生前贈与に適用されるわけではありません。
- 2024年1月1日以降の贈与が対象
- 続開始前の4年~7年以内の4年間の贈与については、総額100万円まで相続財産から控除できる
つまり、実際に影響が出るのは 2027年1月1日以降の相続からとなります。
贈与=安心ではない
「贈与したから相続税対策は大丈夫」と思っていても、一定期間内の贈与は再び相続財産に含められることがあります。将来の相続税を見据えて贈与を活用する場合は、このルールを知っておくことが欠かせません。
非課税や特例のある財産
相続財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。税法上、一定の非課税枠や特例が設けられており、これを知っているかどうかで大きな差が出ます。
生命保険金の非課税枠
生命保険金は相続財産に含まれますが、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。
たとえば、相続人が妻と子2人の合計3人なら、500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税。
残りの部分だけが相続財産としてカウントされます。
死亡退職金の非課税枠
勤務先から支給される死亡退職金も生命保険金と同じ扱いで、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の土地については、一定の条件を満たすと評価額を大幅に減額できる特例があります。代表的なのが「小規模宅地等の特例」で、居住用宅地なら最大で 80%減額。
この特例を使えるかどうかは相続税額に直結するため、実際の申告では非常に重要です。
相続税の申告期限は10か月以内
相続税がかかる場合には、相続の開始(通常は被相続人が亡くなった日)を知った日の翌日から 10か月以内 に申告・納税をする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが課されることもあるため注意が必要です。
財産の評価や特例の適用には時間がかかるケースも多いので、基礎控除を超える可能性がある場合は早めに準備を始めることが大切です。
まとめ|基礎控除を超えるかどうかは専門家に早めの相談を
この記事では、相続税がかかるかどうかを判断するための基礎控除や相続財産の範囲、生前贈与の扱いといった重要ポイントをシンプルに解説しました。
ただし、ここで紹介したのはあくまで基本的な仕組みです。実際の相続税の計算では、土地の評価や非課税枠・特例の適用などが絡み、非常に複雑になる場合があります。
特に、相続財産が基礎控除額を超えるかどうか微妙なケースでは、自分で判断してしまうと申告漏れや余計な税負担につながりかねません。
「うちの場合はどうだろう?」と少しでも不安を感じたら、早めに税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、安心して相続に備えることができます。