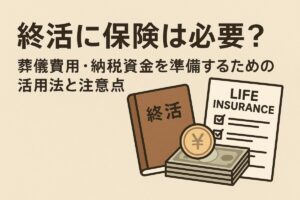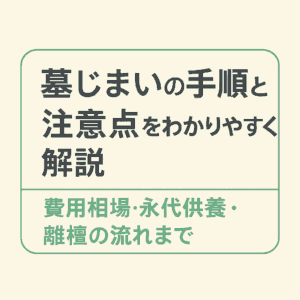はじめに|婿養子の相続をめぐる「よくある誤解」
婿養子という言葉には、昔ながらの「家を継ぐ」という響きがあります。
しかし現代の法律における婿養子は、単に“家名を守る”ための制度ではなく、
ひとつの独立した親子関係を生む法的手続きです。
この記事では、
- 婿養子とはそもそもどういう制度なのか
- 養子縁組によって相続権はどう変わるのか
- 実子との相続関係・遺留分の扱い
- 「家を継がせたい」想いを実現するための現実的な方法
を、法律のしくみと実例を交えながらわかりやすく解説します。
第1章|まず整理したい「養子縁組」の基本構造
1.養子縁組とは?
養子縁組とは、血のつながりのない人どうしが法律上の親子関係を結ぶ制度です。
民法上は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、
日常で「婿養子」と呼ばれるのは、一般的に「普通養子縁組」にあたります。
普通養子縁組を行うと、
養親と養子の間に「実の親子」と同じ法的効果(相続・扶養など)が発生します。
つまり、養子は養親の実子とまったく同じ立場で相続に関わることになります。
2.「婿養子」とは結婚+養子縁組の組み合わせ
「婿養子」とは、結婚した男性(婿)が妻の実家の養子になることをいいます。
具体的には次のような二重構造になります。
| 関係 | 手続き | 法的効果 |
|---|---|---|
| 婚姻 | 婚姻届の提出 | 配偶者となり、法律上の夫婦関係が成立 |
| 養子縁組 | 養子縁組届の提出 | 妻の親(=妻の実家)の養子となり、法律上の親子関係が成立 |
婚姻と養子縁組は別の手続きです。
「長女と結婚したから自動的に婿養子になる」という誤解がよくありますが、
実際には別途、養子縁組届を提出しなければ婿養子にはなりません。
3.婿養子になると姓はどうなる?
一般に「婿養子=妻側の姓になる」と思われがちですが、
正確には次のように整理されます。
| パターン | 氏(姓)の変化 | 備考 |
|---|---|---|
| 婚姻のみ | 夫婦どちらかの姓を選択(夫の姓 or 妻の姓) | 婿入りでも妻が夫の姓を選べば姓は変わらない |
| 婚姻+養子縁組 | 養親(妻の親)の姓を名乗る | 戸籍上、養親と同じ姓になる |
つまり、婿養子=妻の親の戸籍に入り、その家の姓を名乗るということになります。
かつて「家を継ぐ」ことを重視した時代には、この「姓」が極めて重要な意味を持ちました。
4.養子縁組によって生じる法的効果
婿養子(=養子)になると、次のような法律上の関係が発生します。
- 養親との間に親子関係が生じる
- 養親に対して扶養義務を負う
- 養親の相続人となる(相続権が発生)
- 実親との関係も存続し、実親の相続権も残る(=二重の親子関係)
このように、婿養子は養親側と実親側の両方で相続権を持つため、
場合によっては「相続が二重に発生する」立場になります。
【補足:特別養子縁組との違い】
参考までに、家庭裁判所の許可を必要とする「特別養子縁組」は、児童福祉目的で設けられた制度であり、実親との親子関係が完全に切れるのが特徴です。
成人の婿養子がこれに該当することはありません。したがって、相続をめぐる議論の対象になるのは、通常はすべて「普通養子縁組(=婿養子)」です。
第2章|婿養子に相続権はある?その範囲と順位
1.婿養子は「養親の子」として相続人になる
婿養子(=妻の親の養子)になると、法律上、養親の「実子」と同じ立場の相続人になります。
民法上の相続順位は次のように定められています。
| 順位 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(実子・養子を含む) | 子が死亡していれば孫などが代襲相続 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 子がいない場合のみ発生 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合 |
つまり、婿養子は養親の「子」として第1順位の相続人になります。
この点は実子と完全に同格で、相続分にも一切の差はありません。
2.事例:長女の夫を養子にした場合
たとえば、次のような家族構成を考えます。
母(養親)
├─ 長女(実子)
│ └─ 夫(婿養子)
├─ 次女(実子)
└─ 三女(実子)
父はすでに亡くなっており、母が一人で家や土地を所有しています。
この母が婿養子(長女の夫)を正式に養子として迎え入れた場合、
母と婿養子の間には法律上の「親子関係」が成立します。
そして、母が亡くなったときの法定相続人は次の4人です。
- 長女(実子)
- 婿養子(養子)
- 次女(実子)
- 三女(実子)
それぞれの法定相続分は1/4ずつとなります。
つまり、婿養子は実子と「同じ相続分」を持つのです。
3.婿養子が“特別に多くもらえる”わけではない
このように、養子縁組をしても相続上の地位は「他の子どもと同等」です。
「家を継いだ人が全部もらえる」というわけではなく、
法定相続ではあくまで平等に扱われます。
たとえ長女の夫として家を守っていても、
遺言書がなければ他のきょうだいと同じ1/4ずつの分配になるのです。
このため、家や土地を確実に継がせたい場合は、
遺言で明確に指定することが欠かせません。
第3章|遺留分はどうなる?兄弟姉妹との関係にも注意
1.養子にも「遺留分」がある
「婿養子にすべての財産を残したい」と考える方は少なくありません。
しかし、遺言で「全財産を婿養子に相続させる」と書いたとしても、
それで完全に他の子どもの権利を排除できるわけではありません。
民法では、一定の相続人に「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分を保障しています。
これは「親の意思だけで全財産を特定の人に集中させることはできない」というバランスの仕組みです。
そして――重要なのは、養子にも遺留分が認められるということです。
婿養子は、養親の「子」として法定相続人になりますから、
他の実子とまったく同じ遺留分を持ちます。
2.遺留分の基本構造
遺留分は、法定相続分の一定割合で定められています。
| 相続人の構成 | 遺留分の全体割合 | 個々の相続人の遺留分 |
|---|---|---|
| 子どものみ(配偶者なし) | 法定相続分の1/2 | 各子が法定相続分×1/2 |
| 配偶者と子ども | 法定相続分の1/2 | 同上 |
したがって、たとえば養親に「子が4人(長女・婿養子・次女・三女)」いる場合、
各人の法定相続分は1/4ずつ、
その遺留分はさらに半分の1/8ずつになります。
つまり、
遺言で「全財産を婿養子に与える」としても、
他の3人(次女・三女・長女)がそれぞれ1/8ずつの遺留分請求権を持つことになります。
3.「遺留分侵害額請求」で争いになるケース
遺留分を侵害された相続人は、
相続開始後に「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この請求が行われると、
婿養子は他の相続人に対して金銭で補償する義務を負います。
(2020年の民法改正で、物の返還ではなく金銭支払いが原則になりました)
たとえば、遺言で「財産のすべてを婿養子に相続させる」とした場合、
他の相続人が請求すれば、遺留分侵害額を金銭で支払う必要が出てきます。
不動産しかないケースでは、
その支払い原資を確保できずにトラブルになることが多いのです。
4.「家を継がせたい」気持ちと「公平」のバランス
家や土地を守りたいという想いは非常に尊いものです。
しかし法律上は、相続は「家督」ではなく個人の財産承継という考え方が基本です。
そのため、
「家を継ぐ」=「すべての財産を承継できる」
とは限りません。
他のきょうだいからすれば、「なぜ婿養子が実の子と同じ、あるいはそれ以上の取り分をもらうのか」
という心理的な抵抗感も生まれやすく、たとえ法的に正しくても感情的に受け入れがたいケースもあります。
こうした不公平感を最小限に抑えるためには、
遺留分を侵害しない範囲での遺言設計や資金準備が重要になります。
第4章|「家を継がせたい」想いを実現するための手段
1.遺言書で意思を明確に残すことが第一歩
「誰に何を残すか」を確実に実現するには、遺言書の作成が不可欠です。
特に、婿養子や孫など、家を継がせたい特定の人物がいる場合には、
遺言書がなければその意思は反映されません。
民法では、遺言書がない場合、法定相続分どおりに財産が分けられます。
したがって、婿養子を含む相続人が複数いると、
家や土地が分割の対象となり、「家を守る」どころか処分の方向に向かうことも珍しくありません。
公正証書遺言にしておけば、形式の不備や紛失の心配もなく、
家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
2.付言事項で「想い」を残す
遺言書の法的効力があるのは「遺言事項(分配内容)」のみですが、
「なぜそのように分けたのか」「どんな気持ちで託したのか」を記す付言事項が、
争いを防ぐうえで非常に大きな意味を持ちます。
たとえば次のように書き添えることで、
他の相続人の理解や納得を得やすくなります。
「長年、家を支えてきた〇〇に家と土地を託します。
これは、家を守るために考えた私の希望です。皆が円満に助け合っていけるよう願っています。」
このような言葉は、法的効力はありませんが、心理的には大きな効力があります。
この付言事項があるだけで、遺留分請求の火種が鎮まるケースは少なくありません。
3.生前贈与で段階的に承継を進める
不動産を複数所有している場合であれば、
「相続開始時に一度にすべてを移す」よりも、
生前のうちに一部を贈与して承継を進める方法も有効な選択肢の一つです。
たとえば、
- 使用していない土地や古い建物を、早めに名義変更しておく
- 贈与税の非課税枠(毎年110万円)を活用して少しずつ移す
- 家を継ぐ人に住宅取得資金を援助する
といった工夫を重ねることで、税負担を分散しつつ、
相続人間の不公平感も緩和できます。
ただし、贈与の累計額や名義移転時期によっては
相続税の「生前贈与加算」の対象となるため、
税理士と相談しながら進めることが前提となるでしょう。
4.不動産の整理・売却による現実的対策
たとえば、不動産を複数所有しているにもかかわらず現金・預金が少額な場合には、
その不動産のすべてを一人に相続させることは税金・維持管理の両面で難しくなります。
そのような場合は、「家や土地を守りたい」という想いがあっても、
使われていない土地や建物を一部売却して、遺留分調整資金や納税資金に充てるのが現実的です。
不動産を現金化しておくと:
- 他の相続人への支払いがしやすくなる
- 納税資金を確保できる
- 管理負担が減る
というメリットがあります。
「守るべき家」と「手放してもよい資産」を切り分けることが、
結果的に家を守る最短ルートになることもあります。
5.家族への説明と共有を怠らない
どんなに法的に完璧な遺言や贈与設計をしても、
家族がその背景を理解していなければ、相続の場面で不信感が生まれます。
特に婿養子が関わるケースでは、
「外から来た人が家を乗っ取った」と受け取られるリスクが常にあります。
そのため、養親が元気なうちに、
- 家族全員が集まる場で大まかな方向性を共有する
- 遺言書の存在を公言する(内容までは話さなくても可)
- 専門家など第三者を交えて説明する
といった「話し合いの場づくり」が大切です。
これは法的な問題ではなく、家族関係のケアの領域です。
おわりに|「家を守る」とは、家族を守ること
「家を継がせたい」「土地を守りたい」という想いは、
単なる財産の話ではなく、家族の歴史や絆の継承に関わるものです。
しかし、その想いを現実に形にするには、
法と税と感情の三つの要素を丁寧に整理する必要があります。
養子縁組や婿養子という制度は、
単なる形式ではなく、想いを法的に裏づけるための手段です。
祖母のように意思が明確なうちに、
- 専門家と連携して遺言書を作る
- 不動産の整理を進める
- 家族の理解を得る
この3つを実践することが、
「争いのない家族の未来」への最も確かな一歩になります。