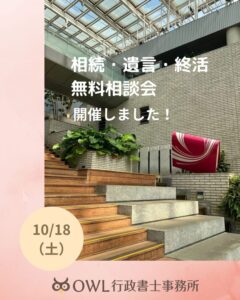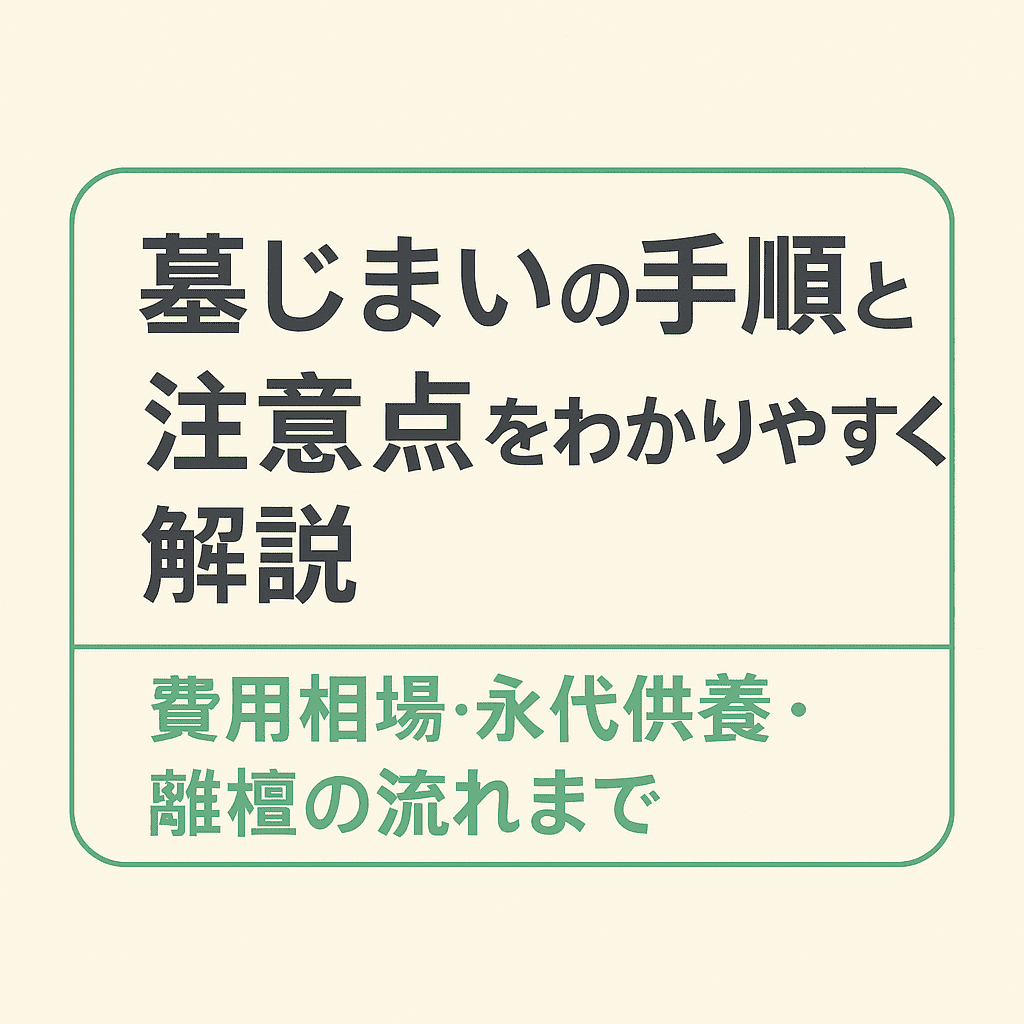
第1章|なぜ今「墓じまい」が増えているのか
「墓じまい」とは、現在あるお墓を撤去し、墓地を更地に戻して管理者へ返還することです。この際、お墓に納められた遺骨を別の場所へ移す「改葬」も行われるのが一般的です。改葬には市区町村での許可申請が必要で、遺骨を無断で移動したり廃棄したりすることは法律で禁じられています。
近年、墓じまいを選ぶ人が増えているのは、次のような理由によります。
- 跡継ぎがいない、または遠方に住んでいて管理が難しい
- 子ども世代に負担をかけたくない
- 都市部に住み替えたため、地元の墓に通えない
- 永代供養墓や納骨堂など、手間のかからない選択肢が増えてきた
かつては「先祖代々のお墓を守るのが当たり前」とされていましたが、現代は価値観も生活環境も多様化しています。墓じまいは、そうした変化の中で「供養をやめる」ではなく「供養のかたちを変える」という前向きな選択として行われるようになっています。
この記事では墓じまいの流れや費用、注意点についてポイントを解説します。
第2章|墓じまいの全体の流れ
墓じまいは、おおまかに次の三段階で進みます。
- 家族・親族との話し合い
- 管理者や寺院への相談
- 行政手続き・撤去・改葬の実施
それぞれの流れを順に見ていきましょう。
■ ① 家族・親族との話し合い
まずは、家族や親族としっかり話し合うことが何より大切です。
お墓は「誰のものか」が明確ではないことも多く、一人の判断で進めると後でトラブルに発展するケースも少なくありません。
- 誰が管理名義人になっているか
- どのような理由で墓じまいを考えているか
- 遺骨をどこに移すか(永代供養・納骨堂・樹木葬など)
こうした点を共有し、できれば文書やメモに残しておくと安心です。
■ ② 寺院・霊園の管理者への相談
次に行うのが、お墓を管理している寺院や霊園への相談です。
特に寺院墓地の場合、いきなり撤去や離檀を切り出すのではなく、まずは住職に事情を伝えることが大切です。
寺院によっては、同じ境内に永代供養墓を設けており、そこに遺骨を移して供養を継続できる場合もあります。そうした場合、改葬の手続きは不要で、寺院との調整だけで完結することもあります。
霊園や自治体墓地の場合は、管理事務所に連絡し、撤去や返還の方法を確認しましょう。墓石の撤去をどの石材店に依頼できるか、指定業者があるかなど、施設によって取り扱いが異なります。
■ ③ 改葬許可の取得(行政手続き)
遺骨を別の場所に移す場合は、市区町村役場で「改葬許可申請」を行う必要があります。
手続きの流れは次のとおりです。
- 現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらう
- 移転先(受け入れ先)から「受入証明書」をもらう
- この2つの書類をそろえて、市区町村役場で「改葬許可申請書」を提出
- 役所から「改葬許可証」が交付される
この改葬許可証がないと、遺骨を運搬・納骨できません。
手続きには時間がかかることもあるため、早めの準備が安心です。
■ ④ 閉眼供養と墓石撤去
改葬許可が下りたら、まず「閉眼供養(魂抜き)」を行います。
これは僧侶に読経してもらい、墓石に宿っている“魂”を抜く儀式です。
法要後に、石材店へ墓石撤去を依頼します。費用の目安は1区画あたり15〜30万円前後。撤去後は区画を整地(更地)に戻し、管理者に返還します。
寺院墓地の場合は、撤去前に「離檀」についての合意を住職と取り交わしておくことが重要です。この点については、第4章で詳しく解説します。
■ ⑤ 新しい納骨先での開眼供養
遺骨を新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)に移したら、「開眼供養(魂入れ)」を行います。これで改葬が正式に完了です。
手続きそのものは数か月で終えられますが、気持ちの整理にはもう少し時間がかかることも多いものです。焦らず、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。
第3章|墓じまいにかかる費用の目安
墓じまいには、いくつかの費用が関係します。
ひと口に「墓を片づける」と言っても、行政手続き・供養・撤去・新しい納骨先の準備など、複数の工程が含まれているためです。ここでは、一般的な費用の構成と目安を整理しておきましょう。
■ 主な費用項目と相場
| 費用の種類 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 墓石撤去・整地費 | 墓石を解体し、更地に戻す費用(石材店へ支払い) | 約15〜30万円 |
| 僧侶へのお布施 | 閉眼供養・開眼供養などの法要にかかる謝礼 | 3〜10万円程度 |
| 永代供養料 | 改葬先で今後の供養をお願いする費用(寺院や霊園へ) | 10〜50万円前後 |
| 改葬許可手数料 | 行政手続きでかかる費用(自治体によって異なる) | 数百円〜数千円 |
| その他 | 骨壺の購入、運搬費、法要時の会食など | 数千〜数万円 |
全体としては30万〜80万円前後が目安です。
ただし、墓地の区画の広さや地域、寺院の宗派・格式によって幅があります。
見積もりは、寺院・石材店・改葬先の三者からそれぞれ取り、内訳を確認しておくと安心です。
第4章|寺院墓地にお墓がある場合の手続き
寺院墓地での墓じまいは、宗教的なつながりや住職とのご縁もあるため、慎重な対応が求められます。
■ まずは住職への相談から
寺院墓地の場合、最初の一歩は住職への相談です。
いきなり「お墓を撤去したい」と切り出すのではなく、たとえば
「子どもが遠方に住んでおり、今後お墓の管理が難しくなってきました」
「永代供養という形に変えることも考えています」
と率直に話してみましょう。
寺院によっては、境内に永代供養墓(合同墓)や納骨堂を設けており、遺骨をそこに移すことで、管理の負担を軽くしながら供養を続けられます。
■ 永代供養をお願いする場合の流れ
寺院で永代供養を依頼する場合、多くは檀家関係を終了(離檀)する形で進みます。
墓地の区画を返還し、以後の供養を寺院に委ねることになるためです。
離檀とは、これまでの檀家関係を終了し、お墓の管理関係を一区切りつけることを意味します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 現在のお墓の撤去と区画の返還を住職と相談
- 遺骨を永代供養墓や納骨堂へ移す
- 永代供養料を納め、閉眼供養と納骨法要を行う
この際、同じ寺院の境内であっても、遺骨を別の場所へ移す場合は改葬許可が必要とされることがあります。
扱いは自治体によって異なるため、事前にお寺と市区町村役場の両方に確認しておくと安心です。
また、費用面では永代供養料と墓石撤去費が別になるのが一般的です。
永代供養料は供養をお願いするためのお布施(10〜50万円前後)、墓石撤去・整地費は石材店への実費(15〜30万円前後)が目安です。
「一式料金」と提示される場合でも、内訳を確認しておくとトラブルを防げます。
なお、寺院によっては、檀家のまま永代供養を申し込めるケースもあります。
今後も葬儀や法要を同じ寺にお願いしたい場合などは、関係をどうするかも含めて事前に住職へ相談しておくとよいでしょう。
■ 他寺院や霊園へ改葬する場合
同じ寺院で永代供養を行わず、他の寺院や霊園へ遺骨を移す場合も、離檀の手続きを経て改葬を行います。
離檀から改葬までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 改葬の意向を住職に伝え、了承を得る
- 離檀届を提出し、閉眼供養を行う
- 墓石を撤去し、寺院から「埋葬証明書」を受け取る
- 改葬先の「受入証明書」を準備
- 市区町村役場で「改葬許可申請」を行い、改葬許可証を受け取る
- 新しい納骨先で開眼供養を行う
離檀の際には、これまでの供養への感謝を込めて「御布施」「御礼」として3〜10万円前後を包むのが一般的です。
金額に決まりはなく、気持ちを込めてお渡しすれば十分です。
■ 円満に進めるための心得
寺院との関係は、形式よりも心遣いが大切です。
離檀を申し出る際は、書面だけで済ませず、まずは対面または電話で説明し、日程や進め方も寺側の都合に配慮しましょう。
改葬先の契約を先に進めてしまうと誤解を招くことがあるため、必ず先に寺院へ相談しておくことをおすすめします。
感謝の気持ちを伝えながら丁寧に進めることで、最後まで穏やかに関係を結ぶことができます。
第5章|改葬先(新しい供養先)の選び方
お墓を閉じることはゴールではありません。
むしろその後、どこに遺骨を安置し、どのように供養を続けていくかを決めることこそが、墓じまいの本質です。
近年は多様な供養のスタイルが広がっており、それぞれに特徴と注意点があります。
■ 永代供養墓:管理不要で安心
もっとも一般的な選択肢が、寺院や霊園が管理する「永代供養墓」です。
納骨後は寺院や施設が責任をもって供養を続けてくれるため、跡継ぎがいなくても安心です。
費用の目安は10〜50万円前後。
最初は個別のスペースに納骨され、一定期間(たとえば13年や33年)を過ぎると合同納骨される「期限付き個別安置型」が主流です。
一方、初めから合同で納骨する「合祀型」は費用が比較的安く、管理も簡素ですが、後で遺骨を取り出すことはできません。
■ 納骨堂:アクセス重視の都市型スタイル
近年増えているのが、屋内施設にロッカー型・仏壇型で遺骨を安置する「納骨堂」です。
屋内なので天候に左右されず、都市部から通いやすいのが魅力。
電子カードで参拝できるタイプや、モニターに遺影を映す自動搬送型など、形式も多様化しています。
管理料は年間1万円前後〜、契約期間は33年や50年など施設によって異なります。
契約更新をしないと合祀される場合が多いため、契約内容をよく確認しておきましょう。
■ 樹木葬・散骨:自然志向の新しい供養
「自然に還りたい」という思いから人気が高まっているのが、樹木葬や散骨です。
樹木葬は墓石の代わりに樹木や花をシンボルとして遺骨を埋葬する方法で、管理も比較的容易です。
一方で、散骨は粉骨した遺骨を海や山に撒く供養法で、法的には「節度をもって行えば問題ない」とされています。
ただし、散骨は一度行うと遺骨を取り戻せないため、家族の同意が不可欠です。
また、海洋散骨は専門業者に依頼するのが一般的で、費用は5〜20万円程度が目安です。
■ 手元供養・自宅供養という選択
近年は、自宅に遺骨や遺灰の一部を保管し、小さな仏壇やオブジェに納める「手元供養」も広がっています。
ガラスや木製のデザイン性の高い容器に納めるタイプも多く、宗派を問わず選びやすい方法です。
ただし、相続や売却の際に「遺骨があると手放せない」という実務上の問題もあるため、長期的な視点で考える必要があります。
■ 選び方のポイント
改葬先を選ぶ際は、次の三点を意識すると後悔が少なくなります。
- 供養の継続性:誰が、どのように供養を続けてくれるか
- 立地とアクセス:通いやすさ・交通の便
- 費用と契約内容:管理料や合祀の時期などを明確にしておく
「どこが一番安いか」よりも、「自分たちの暮らしと気持ちに合う形かどうか」を基準に選ぶのが大切です。
第6章|トラブルを防ぐための注意点
墓じまいは、単に手続きをこなすだけではなく、人と人との関係を丁寧に整理していく作業でもあります。
特に家族や寺院との関係には感情が入りやすく、ちょっとした言葉のすれ違いから大きな摩擦に発展することもあります。
ここでは、よくあるトラブルとその防止策を紹介します。
■ 家族・親族間の合意形成を怠らない
最も多いのが、親族間の意見の食い違いです。
「そんな話は聞いていない」「勝手に決めた」といった不満が出やすいのは、お墓が“家”や“血筋”の象徴でもあるからです。
対策としては、次の二点を意識しましょう。
- まずは、墓じまいを考える理由を正直に話すこと。
(高齢や遠方など、やむを得ない事情を共有する) - 方向性が決まったら、進捗を都度共有しておくこと。
書面で合意を取るまでの必要はありませんが、家族グループLINEやメモ書きなど、記録に残しておくと後々の誤解を防げます。
■ 寺院との関係を礼をもって終える
寺院との関係は、感情的な対立を避けることが第一です。
檀家として長年支えてくれた住職にとっても、墓じまいの申し出は少なからず寂しさを伴います。
したがって、形式的な書類のやり取りだけで済ませず、対面または電話で感謝の気持ちを伝えることが大切です。
また、永代供養や離檀料などの金銭に関しても、「支払う/支払わない」という二元的な考え方ではなく、“これまでのご縁へのお礼”としてどう整理するかを意識すると、自然と穏やかなやり取りになります。
■ 石材店・霊園との契約内容を確認する
墓石の撤去や整地を依頼する際は、契約内容をしっかり確認しましょう。
費用の見積もりを口頭で済ませてしまうと、後から「基礎部分の撤去は別料金」といった追加費用が発生することもあります。
見積書に明記すべき主な項目は次のとおりです。
- 撤去の範囲(墓石・外柵・基礎コンクリート)
- 廃棄物の処理方法
- 更地に戻す範囲と仕上げの状態
- 費用の総額と支払時期
契約前に現地で立ち会い確認を行い、写真を撮っておくとトラブル防止になります。
■ 手続きや法要の経過を記録しておく
墓じまいの過程は、数か月から半年ほどにわたることもあります。
行政書類や領収書、法要の日程などを一つのファイルにまとめておくと、後から内容を説明する際にも役立ちます。
特に、複数の親族が関わる場合や相続に関連する場合は、「いつ」「誰が」「どんな手続きをしたか」を簡単にメモしておくことで、思いがけない誤解を防げます。
第7章|墓じまい後の仏壇・位牌・供養の整理
墓じまいを終えても、家の中には仏壇や位牌が残っていることが多いでしょう。
お墓を閉じることは供養をやめることではなく、むしろここからが新しい形の供養との向き合い方の始まりです。
■ 仏壇・位牌の扱い方
古い仏壇や位牌を整理する場合は、まず「閉眼供養(魂抜き)」を行います。
僧侶に来てもらい、お経を唱えていただいたうえで処分するのが正式な方法です。
その後、寺院や葬儀社で「お焚き上げ」を依頼するか、最近では「仏壇供養専門サービス」に送る方法もあります。
仏壇を小型化したり、モダン仏壇に買い替える家庭も増えています。
仏壇を新しくしても、そこに込められた感謝の気持ちは変わりません。
**“形式よりも心を残す”**という視点で整理するとよいでしょう。
■ 過去帳や法要の続け方
お墓を閉じたあとでも、年忌法要やお盆・お彼岸の供養は自由に続けられます。
永代供養墓に納骨した場合、寺院が合同法要を行ってくれることが多いため、その日程を確認しておくとよいでしょう。
また、過去帳(故人の命日を記した帳面)は、仏壇に保管しておくか、永代供養をお願いした寺院に預けることも可能です。
■ 改葬後の「心の整理」
墓じまいを終えた後、多くの人が感じるのは「安心」と「寂しさ」の入り混じった感情です。
お墓を守り続けることができなくなったことに罪悪感を抱く人もいますが、墓じまいはご先祖を粗末にする行為ではありません。
むしろ、「これからも穏やかに供養を続けられる形を整えた」という前向きな選択です。
たとえば、命日やお盆に花を供える、写真に手を合わせるなど、日常の中で小さな祈りを続けることが、最も自然な供養の形かもしれません。
大切なのは、「どんな形であれ、故人を思う気持ちは変わらない」ということです。
第8章|まとめ|お墓を閉じることは、供養を終えることではない
墓じまいは、手続きや費用の面だけを見れば事務的な作業のように思われがちですが、実際には「これまでの感謝を整理し、これからの供養の形を整える」ための大切な節目です。
お墓を閉じることは、ご先祖とのつながりを断つことではありません。
むしろ、その思いを今の自分たちの暮らしに合った形に受け継ぐことだといえます。
誰かに勧められて行うのではなく、「今後の管理をどうしていくか」「自分たちが安心して供養できる形は何か」を考え、家族で納得できる方法を選ぶことが何より大切です。
そして、どんな形を選んでも、ご先祖を思う気持ちがそこにあれば、それが一番の供養になります。
焦らず、礼を尽くしながら、心の整理を一歩ずつ進めていきましょう。