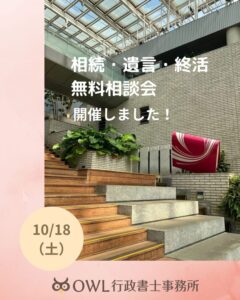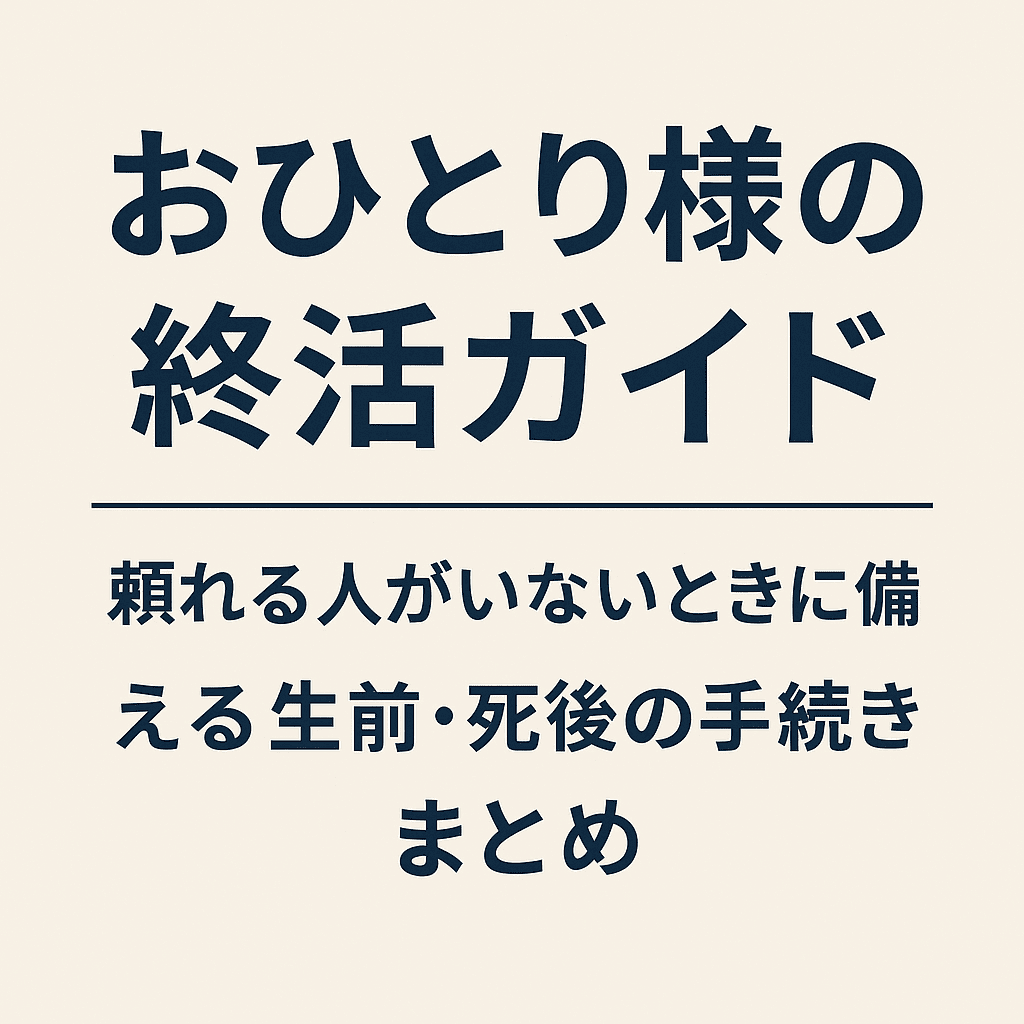
はじめに|“おひとり様”という生き方と終活の必要性
近年、単身で生活する高齢者が年々増加しています。総務省の統計によると、65歳以上の一人暮らし世帯はおよそ800万世帯に達し、今後も増加が見込まれています。
「おひとり様の終活」は、こうした時代背景の中で注目されているテーマです。
一人で暮らしている場合、いざというときに頼れる家族がいない、あるいは遠方に住んでいる──。そんな状況では、病気やケガをしたときの対応から、亡くなった後の手続きまで、さまざまな課題が生じます。
しかし、これらの問題は事前の準備次第で大きく軽減することが可能です。
本記事では、「生前に備えること」と「死後に備えること」を整理しながら、おひとり様が安心して人生の最期を迎えるために考えておきたいポイントを解説します。
1.生前に備えるべき3つの課題
おひとり様の終活は、亡くなった後の手続きだけでなく、ひとりで暮らしていく中で「何かあったときにどう対応するか」ということまで考える必要があります。
ここでは、生前のうちに直面しやすい3つの課題と、その対策について見ていきます。
(1)老後資金の問題
まず最も現実的な課題が、老後の生活資金です。
年金だけでは生活費をまかないきれないというケースも多く、医療費や介護費用が増えると、貯蓄を取り崩す生活に不安を感じる方も少なくありません。
自宅を所有している場合は、次のような資産活用の方法も検討できます。
- リバースモーゲージ
自宅を担保に生活資金を借り入れ、亡くなった後に不動産を処分して返済する仕組み。住み慣れた家に住み続けながら資金を確保できます。 - リースバック
一度自宅を売却し、その後は家賃を支払いながら同じ家に住み続ける方法。まとまった資金を得られる反面、売却額や家賃設定などの条件確認が重要です。 - 売却して施設入居資金に充てる
介護施設やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などへの入居を見据えて、早めに資金計画を立てておくことで安心感が得られます。
いずれの方法を取るにしても、「どのような暮らしを最期まで続けたいか」を基点に考えることが大切です。
(2)病気・ケガのときの対応
判断力が低下したり、突然の入院が必要になった場合、家族がいないおひとり様は特に困ることになります。
入院手続きや手術の同意、身元保証など、誰かの署名や同意を求められる場面は少なくありません。
こうしたリスクを軽減するためには、日頃から地域包括支援センターや社会福祉協議会(社協)とつながりを持っておくことが大切です。
地域の支援体制を把握しておけば、いざというときに迅速な支援を受けられる可能性が高まります。
また、判断力が衰えた際の備えとしては、任意後見契約が有効です。
信頼できる人に自分の生活・医療・財産管理を託す契約で、元気なうちに結んでおくことで、認知症などによるトラブルを防ぐことができます。
(3)孤立死を防ぐための工夫
おひとり様の終活では、「亡くなったことに誰も気づかれない」という孤立死のリスクにも注意が必要です。
特に都市部では、近所づきあいが少なくなるほど発見の遅れにつながります。
対策としては、
- 見守りサービス(自治体・民間)を利用する
- 介護施設や高齢者住宅への入居を検討する
- 地域や友人との関係を絶やさないよう意識する
といった方法が挙げられます。
制度や契約で支えを整えることも重要ですが、最後まで人との関わりを持ち続けることも、おひとり様の終活では欠かせない視点です。
2.亡くなった後に起こる5つの問題
おひとり様が亡くなった場合、葬儀や住まいの片づけ、財産の整理など、多くの手続きが発生します。
家族がいれば自然と誰かが担うこれらの作業も、単身者の場合は代わりに行う人がいません。結果として、葬儀ができない・遺体の引き取り手がいない・遺品が放置されるなどの問題が生じることがあります。
ここでは、主な5つの課題を確認しておきましょう。
(1)葬儀の手配
誰が葬儀を執り行うか、という点はおひとり様にとって大きな課題です。
通常、喪主は家族が務めますが、身寄りがない場合、葬儀自体を依頼できる人がいないケースがあります。
この場合、行政による「直葬(火葬のみ)」という最低限の手続きにとどまることも少なくありません。
葬儀の規模や希望がある場合は、死後事務委任契約を結んで、自分の代わりに葬儀を行ってもらえるよう手配しておくと安心です。
(2)お墓・納骨の行き先
お墓を継ぐ人がいない場合、従来の家墓を維持するのは難しくなります。
近年では、以下のような方法を選ぶ方も増えています。
- 永代供養墓(寺院や霊園が供養と管理を行う)
- 樹木葬・海洋散骨など、自然葬の選択
- 生前に「自分の遺骨をどこに納めたいか」を記録しておく
墓地の契約や費用の支払いも生前に整理しておけば、死後のトラブルを防ぐことができます。
(3)遺品整理と住まいの片づけ
単身で暮らしていた場合、遺品整理を誰が行うのかという問題も生じます。
家財道具や衣類、写真、手紙、パソコンなど、遺品には個人の思い出が詰まっていますが、これらを誰も処理できないまま残してしまうと、賃貸住宅では退去手続きにも支障が出ます。
遺品整理業者に依頼できるよう、死後事務委任契約の中で明確に指示しておくと安心です。
また、普段から身の回りの物を少しずつ減らす「生前整理・断捨離」も効果的です。
(4)財産の処分・相続
相続人がいない場合、遺産は「相続人不存在」として最終的に国庫に帰属します。
ただし、遺言書を作成しておけば、信頼できる友人や支援団体、公益法人などに遺贈として財産を託すことが可能です。
遺言がなければ、預金の引き出しや不動産の処分ができず、長期間放置されるケースもあります。
「自分の財産をどうしたいか」を明確にしておくことが、死後の混乱を防ぐ第一歩です。
(5)保険・死亡退職金などの請求
生命保険金や企業年金、退職金なども、受取人が指定されていない場合は支払いが滞ることがあります。
これらの契約内容を確認し、受取人の指定を見直しておくことが大切です。
また、保険や年金の証書を一か所にまとめて保管し、関係者がわかるようにしておくと安心です。
3.生前にできる具体的な対策
ここまで見てきたように、おひとり様が直面する課題の多くは、生前にしっかりと準備しておくことで解決できます。
主な対策を4つに整理してご紹介します。
(1)遺言書の作成
財産の行き先を明確に定める最も確実な方法です。
相続人がいない場合でも、遺言で信頼できる人や団体に財産を遺すことができます。
また、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。
「遺贈寄付」として社会貢献を選ぶ方も増えており、自分の想いをかたちにする手段としても有効です。
(2)任意後見契約と見守り契約
認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に生活・医療・財産管理を託す契約です。
契約を発動する前から定期的に安否確認や支援を受ける「見守り契約」を併用すると、日常生活の安心感も得られます。
任意後見契約は公証役場で作成でき、あらかじめ支援内容を細かく決めておくことが可能です。
(3)死後事務委任契約
亡くなった後の葬儀、火葬、納骨、住まいの片づけ、行政手続きなどを代わりに行ってもらうための契約です。
身寄りのない人にとっては、まさに「自分の死後を託す」重要な備えとなります。
死後事務委任契約は、遺言や後見契約と併せて整えておくと効果的です。
委任内容を明確にし、信頼できる専門家に依頼することがポイントです。
(4)断捨離とデジタル整理
「自分の死後、人が困らないようにしておく」という考え方が生前整理の基本です。
家財や書類、衣類などを少しずつ整理し、残すもの・処分するものを判断しておきましょう。
また、スマートフォンやパソコンに残るデジタル遺品(写真、メール、SNS、ネットバンクなど)も整理対象です。
パスワードやアカウント情報の一覧を作成しておくと、死後の手続きがスムーズになります。
4.まとめ|“ひとり”でも安心できる終活を
おひとり様の終活では、誰かに頼る前提ではなく、自分の意思と手続きで備えを整えていくことが重要です。
まずは、生前の3つの課題──「老後資金」「医療・介護」「孤立防止」──を意識し、支援機関や地域とのつながりを持っておくこと。
そのうえで、死後に関する5つの問題──「葬儀」「お墓」「遺品」「財産」「保険」──を整理し、誰がどのように対応するかを決めておくことが大切です。
そのための手段としては、
- 遺言書の作成
- 任意後見契約・見守り契約
- 死後事務委任契約
- 生前整理・デジタル整理
といった手続きが基本となります。これらを一度に進める必要はなく、優先順位をつけて少しずつ整えていくようにしましょう。
終活は「亡くなるときのための準備」というよりも、「最後まで自分らしく暮らすための備え」です。
将来に不安を感じたときは、早めに専門家へ相談し、現状に合った方法を確認することをおすすめします。
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
おひとり様の終活では、遺言・後見・死後事務など、誰に何を託すかの整理が大切です。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
現状を伺いながら、必要な備えをわかりやすくご案内いたします。
初回60分は相談無料です。ご来所のほか、オンライン(Zoom)にも対応していますので、安心してお話しいただけます。」