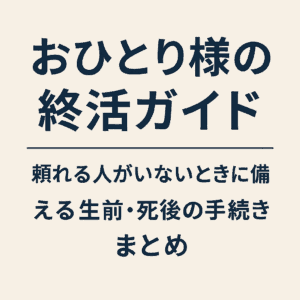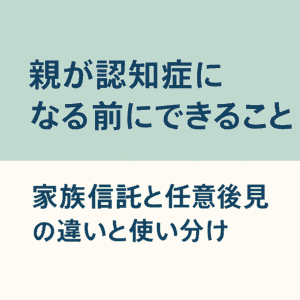1.はじめに|介護が始まると「お金の管理問題」が浮かび上がる
親の介護が始まると、日々の世話や医療対応だけでなく、
医療費や介護費、生活費の支払いといった「お金の管理」が大きな負担になります。
たとえば、入院費の振込、施設利用料の支払い、年金の受け取り、保険金の請求、確定申告の手続き──。
こうした事務をすべて本人が行うことが難しくなると、自然と家族が代わりに動くようになります。
しかし、ここに意外と大きな落とし穴があります。
親の通帳やキャッシュカードを預かって代わりに使うことは、
法律上は本人の代理行為にはならないことが多く、銀行によっては取り扱いを拒まれるケースもあります。
また、「お金の出入りを家族が管理していたら、後から兄弟に疑われた」というトラブルも少なくありません。
「親のためを思ってやっているのに、何か悪いことをしているようで気が引ける」と感じている方も多いでしょう。
介護とお金の管理は、切っても切れない問題です。
そして、法律上の制度をどう活かすかよりも、実際に現場でどう運用できるかが重要です。
本記事では、成年後見制度や家族信託などの制度を含め、実際に介護の現場で“現実的に使える”方法を整理し、
家族としてどのように備えていけばよいかを解説します。
2.よくあるトラブル例|善意のつもりが誤解を招くことも
親の財産を管理しながら介護を行っていると、
「善意でやっているのにトラブルになった」という事例が珍しくありません。
たとえば──
- 銀行での引き出し拒否
→ 委任状を持って行っても、「本人確認ができない」と言われて引き出せなかった。 - 施設や病院での契約手続き
→ 「ご本人の署名が必要です」と対応してもらえず、手続きが進まない。 - 兄弟姉妹間の誤解
→ 支払い記録を見せても「勝手にお金を使ったのでは」と疑われる。
いずれも、介護現場ではよくあることです。
特に、親の判断能力が少しずつ低下してくると、
「本人の意思をどう確認するか」「代理でどこまでできるか」が問題になります。
制度上は、こうした問題を解決するために
「財産管理委任契約」や「任意後見契約」「家族信託」などの手段が用意されています。
しかし、実際にそれらを導入しても、
銀行・施設・役所といった“実務の現場”では思ったように動けないことも多く、
家族としてどう線を引くべきか迷う場面が出てきます。
次章では、それぞれの制度の基本と、現実に使う際の注意点を整理していきます。
3.法的な備え方① 財産管理委任契約とその限界
親がまだ判断能力をしっかり保っているうちは、
「財産管理委任契約」を結ぶことで、家族に財産の管理や手続きを任せることができます。
これは、本人(委任者)が「財産管理をお願いします」と信頼できる家族(受任者)に委任し、
通帳管理や公共料金の支払いなどを代わりに行えるようにする契約です。
公正証書で作成しておけば、法的な裏づけも確保できます。
しかし、実際に使おうとすると次のような壁にぶつかることがあります。
- 銀行では「本人確認」を原則としており、委任契約書があっても対応してもらえないことがある。
- 窓口で「都度、本人の署名か、個別の委任状を持ってきてください」と求められる。
- 施設や病院では「本人の意思確認ができない場合は契約不可」と言われることもある。
つまり、制度上は「委任で代行できる」はずでも、
現場では本人確認を優先され、思うように動けないのが実情です。
とはいえ、日常的な支払い(電気・水道・税金など)や
定期的な生活費の送金など、比較的小口の管理には有効です。
「とりあえず今の段階で、最低限の手続きをスムーズにしたい」という場合には、
財産管理委任契約を結んでおくことは一定の意味があります。
ただし、親の判断能力が低下してくると、
この契約自体が無効と判断されるリスクも出てきます。
その場合に備えて、次に紹介する任意後見契約をあらかじめ組み合わせておくのが現実的です。
4.法的な備え方② 任意後見契約の活用と“発動の壁”
「任意後見契約」は、将来の判断能力低下に備えるための仕組みです。
親が元気なうちに、「いずれ認知症などになったとき、誰に生活や財産の管理を任せるか」を契約で決めておくことができます。
この契約を公正証書で作成しておけば、将来、本人の判断能力が低下した際に
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、その時点で後見契約が正式に効力を持ちます。
法定後見と違い、自分が信頼できる人を事前に選べるのが大きな利点です。
一方で、実際に発動すると動きが制約される面もあります。
- 契約が発効すると、任意後見監督人(多くは司法書士や弁護士)が就き、 財産の管理や支出に対して報告義務・監督が発生する。
- 大きな支出や財産処分をする場合、監督人への相談や承認が必要になることがある。
- 毎月の報告や監督人報酬(一般的に月1〜2万円前後)が負担になる。
このため、「手続きが煩雑になりそう」「費用がかかる」と感じ、
いざ発効させる段階になって申立てをためらう家族が多いのも現実です。
それでも任意後見契約には、
“将来に備えて安心を確保できる”という意味があります。
すぐに発動しなくても、
「判断力があるうちに契約だけしておく」ことで、
いざという時に家庭裁判所への申立てをスムーズに進められます。
つまり、任意後見契約は「今すぐ使う」制度というより、
“将来の選択肢を残す”制度として考えるのが実務的です。
5.法的な備え方③ 家族信託は“万能ではない”
ここ数年、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えました。
信頼できる家族に財産の管理や処分を任せられる制度として注目されていますが、
実際の介護場面では、必ずしも最適解とは限りません。
家族信託は、親(委託者)が子どもなど(受託者)に財産を信託し、
受託者がその財産を親の生活や介護のために管理・運用していく仕組みです。
法律上も安定した制度で、
「親が判断能力を失っても、受託者が柔軟に動ける」というメリットがあります。
ただし、実務の現場で介護資金の管理を目的に利用するには、
次のような課題があります。
- 信託契約書の作成には専門的な知識と一定のコストが必要(公正証書化する場合も多い)
- 銀行によっては信託口座の開設が難しく、取扱金融機関が限られる
- 税務上の処理や収支管理も複雑で、受託者に一定の負担がかかる
- 信託財産の範囲を間違えると、かえって動かしにくくなることもある
つまり、単に「介護費を支払う口座を分けたい」という目的のためだけに家族信託を使うのは、費用や手間が割に合わないことも多いです。
家族信託が真価を発揮するのは、たとえば次のようなケースです。
- 親が所有する不動産を売却し、その資金を介護費に充てたい
- 親が亡くなった後も、一定期間は信託財産を子どもが管理する仕組みにしたい
- 複数の相続人がいて、あらかじめ財産の管理権限を明確にしておきたい
このように、資産全体を中長期で管理・運用する視点がある場合にこそ有効です。
6.現実的な方法:専用口座+代理人カード+記録管理の徹底
ここまで見てきたように、
財産管理委任契約にも、任意後見契約にも、家族信託にもそれぞれ限界があります。
では、実際に介護を担う家族が今すぐできる、現実的な方法は何か。
それは、専用口座を分けてお金の流れを明確にすることです。
親の口座の中から、介護費や生活費用の支払いに使う分だけを
あらかじめ特定の口座に移しておき、その口座でのみ支払いを行うようにします。
入出金を記録(ノートやExcelでも十分)し、
領収書や明細を保管しておくだけでも、透明性は大きく向上します。
このシンプルな方法でも、
「使い込みでは?」という疑念を避け、家族間の信頼を守ることができます。
【補足】本人のカードを預からずに済む「代理人カード」という方法
「親のキャッシュカードを預かって暗証番号を聞くのは気が引ける」
という声は非常に多く聞かれます。
そんなときに検討できるのが、銀行が用意している「代理人カード」制度です。
代理人カードとは、本人の口座名義はそのままに、
家族などを代理人として登録し、別のキャッシュカードを発行してもらう仕組みです。
- 利用範囲は日常の引き出しや振込などに限定される
- 利用限度額を設定できる金融機関もある
- 暗証番号を共有せずに済むため、心理的にも安心
- 取り扱いは銀行ごとに異なり、本人が元気なうちに窓口での手続きが必要
この代理人カードでの管理は、親の口座を安全に管理したい家族にとっては、実用的な選択肢となり得ます。
金融機関によって名称や条件が異なるため、利用を希望する場合は確認してみるとよいでしょう。
記録を残すことの重要性
どの方法を選ぶにしても、もっとも大切なのは「記録を残す」ことです。
支払った金額、日付、目的、領収書。
これらを一定期間ごとにまとめておくだけで、
後から家族間で疑問が生じたときにも説明がつきます。
制度に頼ることも大切ですが、“透明性のある管理”こそが最も強いトラブル予防策になります。
7.将来を見据えた併用プラン|柔軟性と安心を両立する備え方
ここまで見てきたように、
介護とお金の管理をめぐる問題には、「今どう動くか」と「将来どう備えるか」の両面があります。
現時点で親に判断能力があるうちは、
複雑な制度をすぐ導入しなくても、専用口座+記録管理+代理人カードで十分に対応できます。
しかし、判断力がゆるやかに低下していく可能性を考えると、
「将来に備えた法的枠組み」も用意しておくことが大切です。
そのときに現実的なのが、次のような二段構えのプランです。
【第1段階】現役期(親がまだ判断できるうち)
- 専用口座を分け、支出記録を残す
- 代理人カードを利用して安全に引き出す
- 必要に応じて財産管理委任契約を締結しておく
→ この段階では「柔軟に動けること」を重視。
制度よりも実務の運用を整えることがポイントです。
【第2段階】将来期(判断能力が衰え始めたら)
- すでに準備しておいた任意後見契約を発効させる
- 家庭裁判所で監督人を選任してもらい、正式な管理体制へ移行
- 財産が多い場合や不動産処分が必要な場合は家族信託の検討も視野に入れる
→ この段階では「法的安定性」を確保。
本人の意思に基づいて選任された後見人が管理を担うことで、
銀行や施設への対応もスムーズになります。
こうした二段階の構えをしておくと、
“いざというとき”に慌てずに移行でき、家族の心理的負担も軽減されます。
また、任意後見契約は一度結んでもすぐに効力が発生するわけではありません。
契約書を公正証書で作成しておくだけなら、
親子双方にとって「心の保険」のような位置づけとして備えておけます。
8.まとめ
親の介護とお金の管理は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
それだけに、「どの制度が一番よいか」という発想だけで判断してしまうと、
かえって動きにくくなったり、費用倒れになったりすることもあります。
大切なのは、制度を使いこなすことではなく、生活を守ること。
制度にはそれぞれの強みと限界がありますが、
日々の生活の中で「どう記録し、どう共有するか」を意識するだけでも、
家族の信頼関係を保ち、無用なトラブルを防ぐことができます。
そして、親がまだ元気なうちに、
「誰が、どのようにお金を管理していくか」を話し合っておくことが、
最もシンプルで確実な備えになります。
判断能力が低下してからでは、選べる制度も限られてしまいます。早めに方向性を整理しておくことで、
ご家族全員が安心して介護に向き合うことができるでしょう。
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
親世代の介護の場面では、財産管理や後見の問題だけでなく、遺言・死後事務など、考えるべき問題がたくさんあります。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
現状を伺いながら、必要な備えをわかりやすくご案内いたします。
初回60分は相談無料です。ご来所のほか、オンライン(Zoom)にも対応していますので、安心してお話しいただけます。」