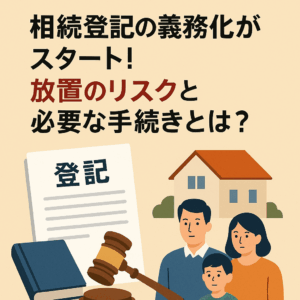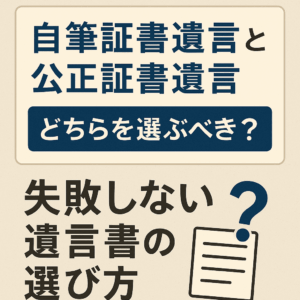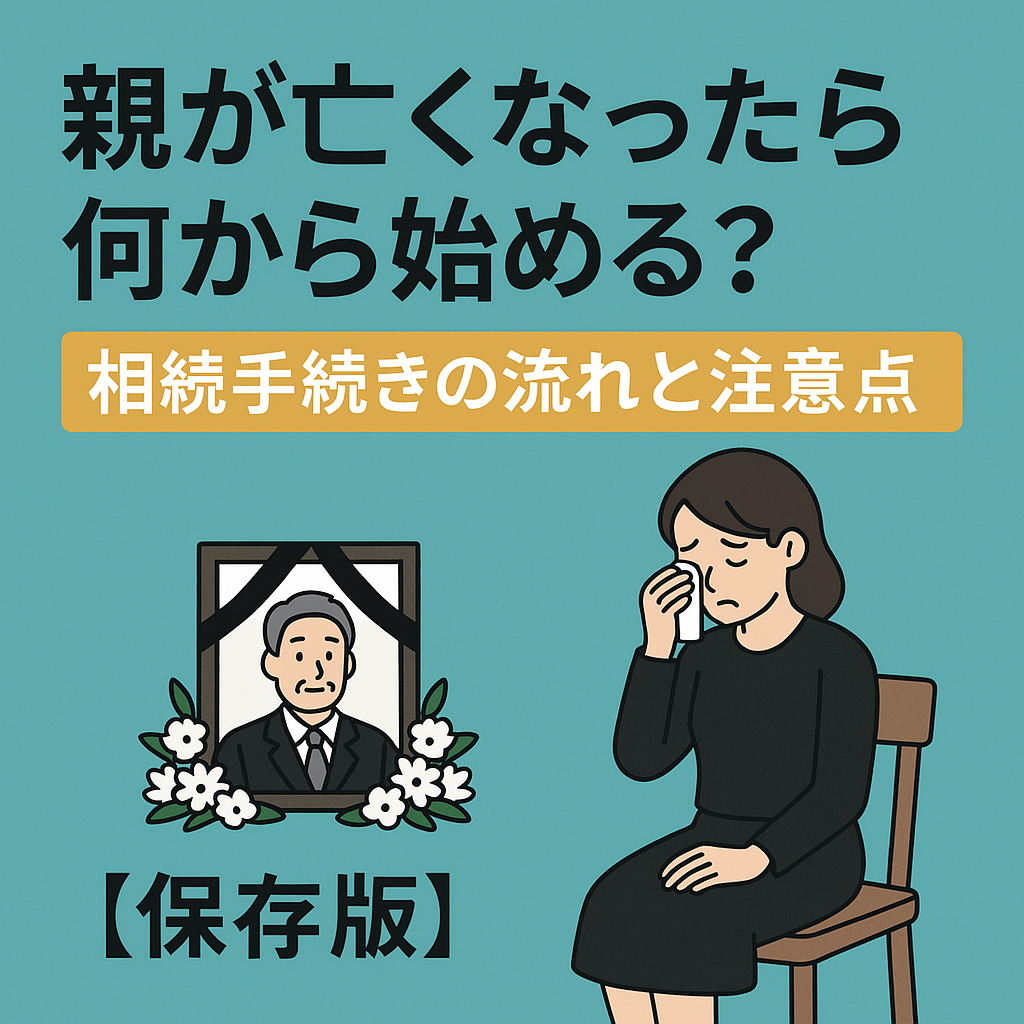
はじめに
親や親族が亡くなった直後は、深い悲しみの中で何をどうすればよいのか分からず、戸惑う方がほとんどです。この記事では、死亡直後から順を追って、相続に関わる主な手続きとその注意点をわかりやすく解説します。今すぐ必要なことと、少し落ち着いてからでも間に合うことを区別しながら解説していきますので、いざという時の備えや確認用としてぜひご活用ください。
死亡届〜葬儀までの初動対応
死亡診断書と死亡届の提出
まず行うべきは、医師から発行される死亡診断書をもとに市区町村役場に「死亡届」を提出することです。死亡届の提出期限は"死亡後7日以内"とされており、これを提出することで火葬許可証が交付されます。
喪主の決定と葬儀社の手配
家族間で喪主を決定し、葬儀社を手配します。葬儀の形式や日程などを打ち合わせします。葬儀費用は法律的には喪主が支払うものと考えられますが、実務上は相続財産から支払うことが多いでしょう。その場合は、必ず領収書を忘れずに保管しておきましょう。
市区町村役場への届け出
火葬許可、埋火葬許可の取得のほか、健康保険や介護保険証の返納なども必要です。多くの手続きが役所で行われるため、複数の届け出をまとめて処理すると効率的です。最近は“おくやみコーナー”などの窓口を設置している市区町村が増えてきていますので、まずは相談されると良いでしょう。
相続の有無と戸籍の集め方
相続の発生を確認
人が亡くなると、法律上は"相続の開始"となります。まず行うべきは、その方にどれだけの財産や債務があるのかを確認することではなく、「誰が相続人になるのか」を明らかにすることです。遺言書が存在するかどうかもここで確認すべき重要なポイントです。遺言書があれば、そこに指定された相続人や分配方法が優先されるため、内容の確認が必要です。
相続人を確定するための戸籍収集
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。これは養子縁組や離婚、再婚、認知など、過去の家族関係をすべて把握するために欠かせない作業です。戸籍は複数の市区町村にまたがっている場合もあり、その都度請求先が異なるため、整理しながら進めることが重要です。
戸籍の請求方法と注意点
戸籍は本籍地の役所でのみ取得でき、現在の住所とは異なるケースがほとんどです。遠方の場合は郵送での取り寄せが可能ですが、申請書や本人確認書類、手数料(定額小為替)などが必要になります。請求する際は「除籍謄本」や「改製原戸籍」も含めて、抜け漏れのないように注意が必要です。また、相続人が複数いる場合は、各相続人の戸籍も必要になる場合があります。役所ごとに処理日数が異なるため、余裕を持ったスケジュールで動くことをおすすめします。
遺産の内容によって変わる対応
財産の種類ごとの違い
相続財産にはさまざまな種類があり、それぞれ手続きが異なるため、内容ごとに確認して対応する必要があります。代表的なものとして、預貯金や不動産、上場・非上場の株式、自動車、生命保険金、貴金属、骨董品、会員権などが挙げられます。たとえば、預貯金は金融機関ごとに手続きが必要で、口座が凍結された後は相続人全員の同意がないと払い戻しができません。不動産については法務局で登記の名義変更(相続登記)が必要となりますし、登記を行わなければ将来的な売却や相続人間のトラブルのもとになることもあります。また、株式や投資信託は証券会社を通じて名義変更の手続きが必要です。財産の種類や金額が多い場合は、「財産目録」の作成をおすすめします。
遺言書の有無を確認
相続において遺言書の有無は手続きの複雑さや進め方を大きく左右します。また、遺言書がある場合は、その形式によって必要な手続きが異なります。自筆証書遺言の場合は、開封する前に家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があります。検認とは遺言書の存在と内容を確認するものであり、これを怠ると手続きに進むことができません。近年は法務局で保管される「自筆証書遺言の保管制度」も始まり、この場合は検認が不要です。一方、公正証書遺言は、公証人の関与によって作成されたものであり、検認は不要ですぐに相続手続きに使えます。ただし、どちらの場合も、遺言の内容に沿って財産を分配することが基本ですが、遺留分など他の相続人の権利に影響する可能性もあるため注意が必要です。
名義変更や解約手続き
相続手続きでは、個々のの財産ごとに名義変更や解約の手続きを行う必要があります。たとえば、預貯金は各金融機関に申請し、相続届の提出とともに必要書類(戸籍・遺産分割協議書など)をそろえる必要があります。不動産は登記変更(相続登記)を行いますが、令和6年4月からは相続登記が義務化され、期限内(3年以内)に行わないと過料が科される場合もあります。
法改正により令和6年4月からは相続登記が義務化され、放置すると過料が科される場合もあります。
▶ 詳しくは「相続登記の義務化がスタート!放置のリスクと必要な手続きとは?」をご覧ください。
また、自動車の場合は運輸支局での名義変更手続きが必要です。さらに、これらの手続きにおいては「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」の作成が求められることが多く、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるケースも多々あります。早めに準備を進めておくことで、手続きを円滑に進めることができます。
手続きの期限に注意(相続放棄など)
相続放棄・限定承認は3ヶ月以内
相続を受けたくない場合や、相続財産よりも借金の方が多いと考えられる場合には、「相続放棄」または「限定承認」という制度を利用できます。これらの申立ては、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。期間を過ぎると、自動的に単純承認(すべてを相続する)とみなされる可能性があるため、注意が必要です。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人に影響が及ぶこともあります。
準確定申告は4ヶ月以内
被相続人が給与所得や年金所得、不動産所得などを得ていた場合には、亡くなった年の所得について「準確定申告」を行う必要があります。これは相続人が共同で行うもので、死亡日から4ヶ月以内に所轄の税務署に申告・納税する必要があります。申告漏れや遅延には加算税や延滞税が課されることもあるため、早めの準備が重要です。
相続税の申告と納税は10ヶ月以内
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。期限は被相続人の死亡から10ヶ月以内で、申告書は被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。延納や物納などの制度もありますが、事前の申請や条件があるため、相続税が発生しそうな場合は早めに税理士などの専門家に相談するのが安心です。
おわりに:不安な方は無料相談をご活用ください
相続は一生に何度も経験することではなく、手続きの複雑さや期限のプレッシャーに不安を感じる方がほとんどです。当事務所では、相続開始直後の対応から遺産分割・名義変更までトータルでサポートしております。
初回相談は無料です。また、毎月開催の「相続無料相談会」もございますので、「何から始めればいいか分からない」「家族で揉めたくない」などのお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。