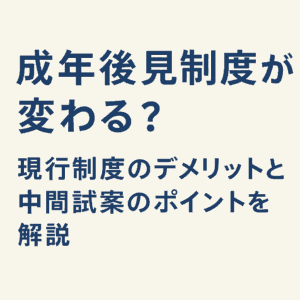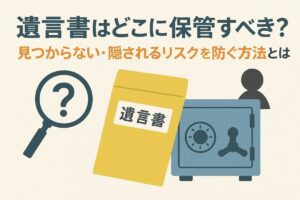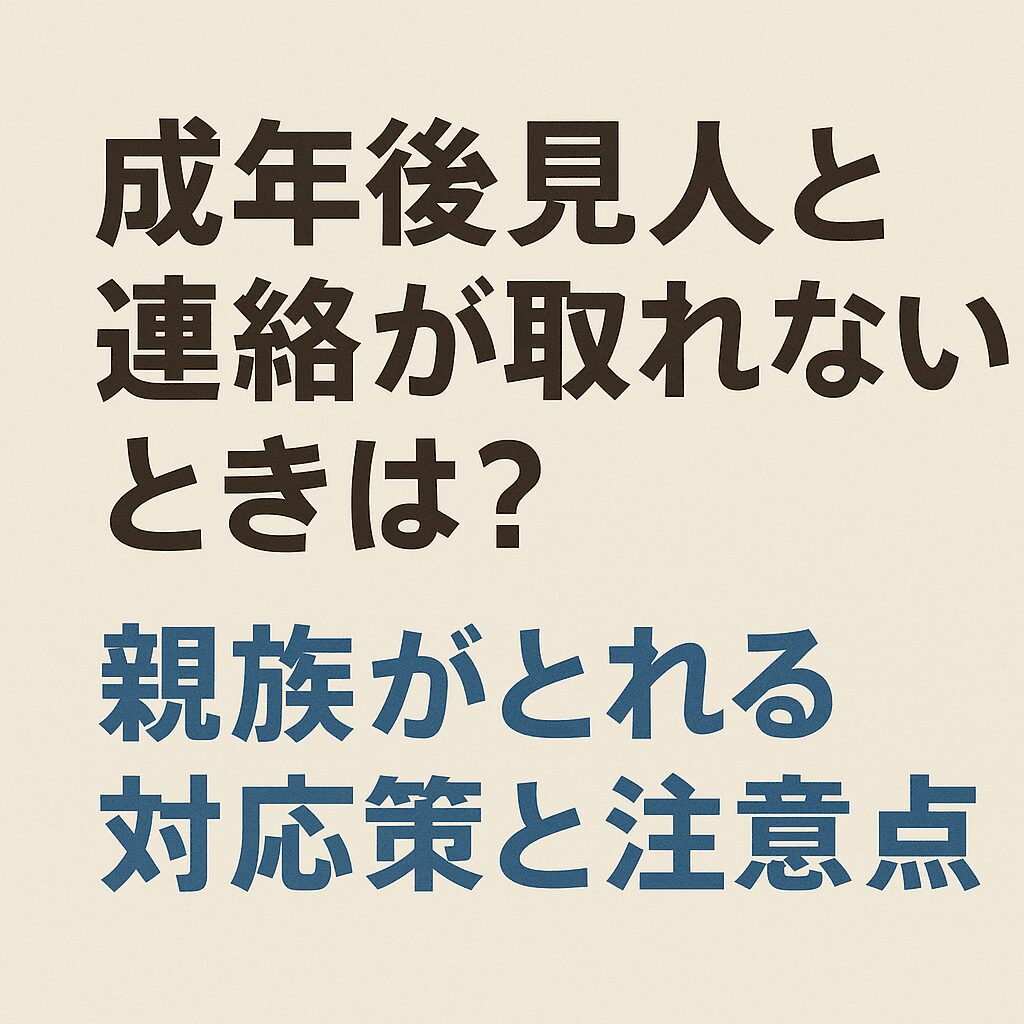
はじめに|成年後見人が「連絡をくれない」…
「成年後見制度を利用すれば安心」と思っていたのに、後見人とまったく連絡が取れない――そんな悩みを抱える親族の方が少なくありません。
たとえば、認知症になった親の成年後見を申し立て、家庭裁判所によって弁護士が後見人に選ばれたものの、その後まったく音沙汰がない。親の財産や施設費用の支払い状況、医療費の管理などについて心配になって問い合わせても、返答はなく、家庭裁判所に聞いても「後見人に任せています」と言われてしまう……。
このような状況は、決して珍しいものではありません。
そしてそこには、現行の制度設計上の「落とし穴」が存在しています。
本記事では、こうした問題の背景にある成年後見制度の仕組みと限界、そして親族の立場からできる具体的な対応策について、やさしく解説していきます。
1. 現行制度の仕組み|後見人は“誰に”報告するのか
成年後見人には、被後見人(本人)の財産を管理し、必要な支援を行う法的な権限と責任があります。
その活動内容については、定期的に「家庭裁判所」に報告する義務があります。
● 家庭裁判所にのみ報告義務がある
成年後見人は、1年に1回、家庭裁判所に対して財産管理や身上監護の状況を報告します。これは制度上の義務です。しかし、親族に対しては法的な報告義務は一切ありません。
つまり、たとえ申立人が家族であっても、「その後の後見人の対応について何も知らされない」という状況が制度上、起こりうるのです。
● 専門職後見人は「必要最小限の対応」にとどまることも
後見人に弁護士や司法書士などの「専門職」が選ばれた場合、職業倫理上の配慮や、家族とのトラブルを避ける目的から、親族とのやり取りをできるだけ控えるということがあります。
「家庭裁判所には報告しているから、それ以上の説明はしない」というスタンスを取られることもあります。
これは制度として“正しい運用”かもしれませんが、親族にとっては非常に不安で、やるせない状況です。
2. なぜ親族に情報が届かないのか?
成年後見制度では「後見人は本人の利益のために活動する」ことが原則とされています。そのため、親族=利害関係人と見なされることも多く、あえて情報を制限する運用が行われるケースもあります。
● 制度設計上の理由:本人保護とプライバシー重視
現行制度では、被後見人(本人)の権利保護とプライバシーを重視する観点から、後見人は家庭裁判所の監督下にあるだけで、親族には報告義務を負いません。
「親族が関与しすぎることで、本人の意思が損なわれる」「親族間でのトラブルがある場合、情報提供はむしろ不適切」とされる場面もあります。
● 専門職後見人の対応姿勢:トラブル回避のための“壁”
弁護士や司法書士などの専門職は、職務上の中立性を重視します。
そのため、親族が財産状況を尋ねても、「家庭裁判所に報告していますので」として個別の対応を控える傾向が強いです。
また、専門職が後見人に選任される背景には、「親族間にトラブルがある」「親族による財産管理に不安がある」などの事情があることも多く、親族との接触自体を避ける方向で動くケースも少なくありません。
● 本人と親族の意思との乖離
さらに、被後見人本人が高齢や認知症により自ら希望を表明できない場合、
「親族として何かしてあげたい」と思っていても、その気持ちは制度の枠組みの中では反映されにくくなります。
3. 親族ができること|“泣き寝入り”しないための3つのアクション
それでは、こういった場合に親族や申立人ができることはないのでしょうか?ここでは以下の3つをご紹介します。
① 家庭裁判所に相談し、必要に応じて定期報告書の閲覧を申し立てる
後見人は、1年に1度、財産の状況や支出内容などを家庭裁判所に「定期報告書」として提出しています。
この報告書は原則として裁判所と後見人の間でやりとりされるものですが、利害関係人(たとえば相続人や申立人)としての立場から、家庭裁判所に相談し、閲覧を申し立てることが可能な場合があります。
「財産状況がまったく分からず心配している」「後見人と連絡が取れない」という事情を丁寧に説明することで、閲覧を認めてもらえるケースもあります。
② 成年後見センターや地域の相談窓口に相談する
各都道府県には、成年後見制度の利用やトラブルに関する相談機関が設置されています。
たとえば、以下のような窓口があります。
- 地方自治体の高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)
- 社会福祉協議会内の成年後見センター
- 弁護士や司法書士会に設置されている成年後見相談窓口
これらの機関では、後見人とのコミュニケーション不全や制度の運用に関する相談を受け付けています。
必要に応じて助言をもらったり、改善のための働きかけが行われるケースもあります。
③ 家庭裁判所へ意見書を提出する
どうしても後見人と連絡がつかず、不信感が拭えない場合は、家庭裁判所に対して意見書を提出するという方法もあります。
たとえば、
- 後見人が親族との連絡を一切断っている
- 施設への支払いなどに不備が見られる
- 本人の生活状況に不安がある
といった懸念点を具体的に記し、後見監督の観点から裁判所に対応を促すことができます。
場合によっては、家庭裁判所が後見人に注意喚起を行ったり、後見監督人の選任を検討することもあります。
4. 制度改正の動き|今後の成年後見制度はどう変わる?
こうした現状を受けて、国の制度見直しも進められています。
2025年以降の制度改正に向けた「中間試案」では、以下のような改善案が示されています。
● 中間試案での主なポイント
- 家族・親族との連携を制度的に位置づける方向
- 定期報告書の内容を、一定の条件下で親族にも共有可能とする案
- 本人の意思・希望の尊重をさらに重視する枠組み
このように、このたびの改正案では、本人の利益保護という観点から家族・親族との連携についても見直しが進められています。
● ただし制度改正には時間がかかる
制度見直しの方向性は明るい材料ですが、実際の法改正・運用の変化には時間がかかります。
すでに制度を利用している人にとっては、「今どうするか」の視点が引き続き重要です。
5. 制度選択の視点|任意後見・家族信託との違いと備え方
成年後見制度の現行ルールでは、後見人に親族が関与しにくいという構造的な課題があります。
しかし、将来に備えておくことで、家族との連携がとりやすい“選べる制度”を利用することも可能です。
ここでは、「法定後見制度」以外の選択肢として注目されている任意後見と家族信託について簡単に紹介します。
● 任意後見|家族との事前契約で信頼関係を反映できる
任意後見制度では、まだ判断能力があるうちに、信頼できる人(多くは家族)と契約を結び、その人が将来の後見人になることを定めておけます。
契約時に「○○については定期的に家族に報告すること」といった条件を明記することもできるため、親族が“知らされない”不安を事前に防ぐことが可能です。
● 家族信託|財産管理の設計を自由に決められる
家族信託は、財産を「託す人(親)」と「管理する人(子など)」の間で信託契約を交わし、家族内で柔軟に財産管理の仕組みを構築できる制度です。
・定期的な報告義務
・管理権限の制限
・複数人での意思決定(信託監督人の設置)
といった内容を自由に設計することができるため、将来の見通しが立てやすくなります。
● ポイントは「判断能力があるうちに動く」こと
どちらの制度も、本人が自分の意思で契約できることが前提です。
つまり、認知症の診断が下りてからでは、選べなくなる可能性が高いのです。
「まだ元気だから」と先送りせず、早めに家族と話し合っておくことが、
制度の“受け身”にならずに済む最大のポイントと言えるでしょう。
6. まとめ
成年後見制度は、高齢者や認知症の方を法的に支える仕組みとして必要不可欠な制度です。
しかしその一方で、「親族がまったく情報を得られない」「何が行われているのか不透明」という問題も、現実には数多く発生しています。
親族としてできることは限られていますが、このような手段を知っておくだけでも、将来の不安を軽減する一歩になります。
👇 お気軽にご相談ください
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を随時受け付けています。
まずは「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。何を相談すればいいかもわからない、という方でも丁寧に現状をヒアリングしてアドバイスいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。