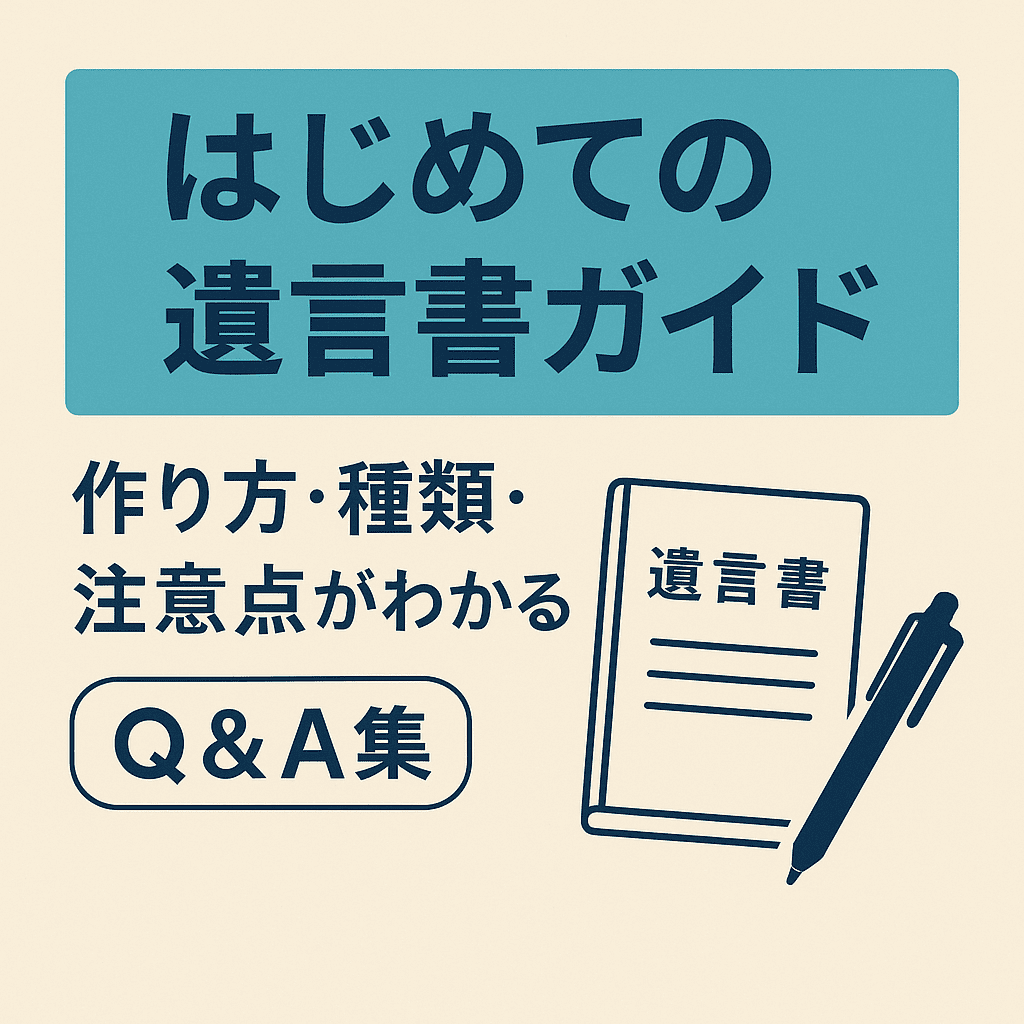
遺言書は、万が一に備えて自分の想いを形にする大切な手段です。
このページでは、はじめて遺言を考える方にもわかりやすいように、Q&A形式で基礎知識をまとめています。
一般の方がつまずきやすい点やよくある質問を網羅していますので、ぜひ参考になさってください。
気になる質問をクリックすると、該当箇所にジャンプします。
1.遺言の基本
Q. 遺言書ってそもそも何?
A. 遺言書は、自分が亡くなったあとに「誰に」「どの財産を」「どう分けるか」などを伝える法的な効力を持つ文書です。自分の意思を残すことで、家族のトラブルを防ぐ役割もあります。
※これに対して、エンディングノートは、備忘録的なメモであり、法的な効力はありませんが、気持ちや希望を伝える手段として併用されることもあります。
Q. 遺言書を書いたほうがいいのはどんな人?
A. 財産の多寡にかかわらず、以下のような人は書いておくと安心です:
- 相続人以外に財産を渡したい人
- 子どもがいない夫婦
- 再婚して家族関係が複雑な人
- 兄弟姉妹が相続人になる人
Q. 遺言がないときは法律上どうなるの?
A. 遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続分に従って分けるのが原則です。
たとえば、配偶者と子どもが相続人なら、財産はそれぞれ2分の1ずつとなります。
ただし、実際は誰がどの財産を受け取るかは法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要で、意見が合わなければ相続トラブルになることもあります。
一方で、遺言書があれば、原則としてその遺言書の内容が優先されます。
Q.「遺留分」ってなに?気にした方がいいの?
A. 遺留分とは、配偶者や子など一部の相続人に法律上保障されている“最低限の取り分”です。遺言でまったく財産を渡さないようにすると、遺留分侵害として争いになることがあります。あまりにも偏った配分にする場合は注意が必要です。
Q.遺言書は何歳から書ける?認知症の場合は?
A. 満15歳以上であれば遺言を書けます。ただし、意思能力が必要なので、認知症と診断された場合は進行度にもよりますが無効になる可能性が大いにあります。判断力に不安がある場合は、公正証書遺言が安心です。
2.遺言でできること・できないこと
Q. 相続人以外(内縁の妻・友人・団体)にも財産を渡せる?
A. 基本的には自由です。法定相続人だけでなく、友人や団体、介護してくれた人など第三者にも遺贈できます。ただし「遺留分」を持つ人の権利は完全には無視できません。
Q. 子どもの認知や後見人の指定も遺言書に書ける?
A. 書けます。たとえば非嫡出子の認知、未成年の子の後見人の指定、遺言執行者の指名なども遺言で可能です。
Q. 遺言ではできないことは?
A. 遺言でできること(遺言事項)は法律で決められているものに限られます。したがって、基本的には、自分の「財産の分配」に関する意思表示が遺言の役割になります。そのため、認知以外の身分に関する行為(離婚、養子縁組)や2代先までの相続方法の指定はできません。
Q. 借金や債務を相続させないようにできる?
A. 例えば、遺言で「借金は長男だけに相続させる」といった書き方をしても、債権者に対しては効力がありません。民法上、借金などの債務は、相続人全員が法定相続分に応じて承継するのが原則です。したがって、相続人が債務を免れたい場合は、相続放棄などで対処する必要があります。
※令和元年改正で新設された民法902条の2で明文化されました。
3.遺言書の種類と選び方
Q. 遺言書にはどのような種類がありますか?
A. 実務上利用されているのは次の2種類です。
・1つは、自筆証書遺言です。自分で全文・日付・氏名を手書きして作成する遺言です。費用がかからず手軽ですが、方式ミスや紛失、発見されないリスクもあります。
・もう一つは、公正証書遺言です。公証役場にて公証人が遺言者の意思を聞き取って作成する遺言です。原本は公証役場に保管され、確実性が高い一方、費用がかかります。
※このほかに秘密証書遺言という種類もありますが、実務上はほとんど利用されていません。
Q. どの遺言書が一番おすすめ?
A. 基本的には「公正証書遺言」がもっとも安全・確実でありおすすめです。ただし、すぐに費用をかけずに始めたい場合は「自筆証書+法務局保管制度」も現実的な選択肢です。
Q. 緊急時に急いで作成したい場合はどうすればいい?
A. 病気や事故などで時間が限られている場合でも、状況に応じて遺言の作成は可能です。
たとえば、意識がはっきりしていれば、自分で書く「自筆証書遺言」を急いで作ることも可能です。この場合、登記事項証明書などが手元になくても「船橋にある私の土地は長男に」など、ある程度の財産の特定ができればいいので、とにかく意思を残すことが大切です。
また、病室に公証人を呼んで「公正証書遺言」を作ることも可能ですが、時間や病院側の協力が必要になります。
さらに、危篤状態などで筆記が難しい場合は、「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」という緊急用の制度もあります。
ただし、証人や家庭裁判所での確認手続きなどが必要なので、いずれにしても、できるだけ早めに専門家へご相談ください。
Q. 生前贈与と遺言、どっちがいい?
A. 目的によります。生前贈与は確実に自分の意志で渡せますが、贈与税がかかる可能性があります。遺言は相続時の分配を指定できますが、遺留分への配慮が必要です。併用も有効です。
4.遺言書の内容・準備・作成方法
Q. どんな内容を書けばいい?
A. 「誰に」「何を」「どれだけ」渡すのかを明確に書きましょう。自筆証書遺言では原則として全文自筆・日付・署名・押印が必須です。形式ミスがあると無効になるので注意が必要です。
Q. パソコンで作ってもいいの?
A. 自筆証書遺言では原則としてNGです。全文を自書(手書き)する必要があります。ワープロやコピーは無効になります。ただし、法改正により財産目録については一定の条件を満たせばワープロやコピーによる作成も一部認められます。なお、公正証書遺言では本文は公証人が作成しますが、下書き原稿を遺言者がパソコンで作成することは可能です。
Q. 日付や署名を忘れたら無効になる?
A. はい、無効になります。とくに日付が曖昧(「○月吉日」など)なものは形式的要件を満たさず無効です。また、署名が不完全だとトラブルの原因になります。必ず年月日とフルネームを手書きしてください。
Q.「付言事項」ってなに?書くべき?
A. 法的な効力はありませんが、家族へのメッセージや気持ちを伝えることができる自由記述欄です。遺言内容への理解や納得感を高め、争いの予防につながることもあります。
Q. 遺言執行者って選んだほうがいいの?
A. はい、選任をおすすめします。遺言の内容を実際に実行する人が「遺言執行者」です。家族の負担を軽くでき、特に相続人以外に遺贈する場合などは指定しておくとスムーズです。
5.遺言書を作成した後のこと
Q. どこに保管すればいい?見つからないとどうなる?
A. 自筆証書遺言は紛失や改ざんのリスクがあるため、信頼できる人に預けるか、法務局の保管制度を利用しましょう。発見されないと「遺言がなかった」ことになってしまいます。
Q. 法務局の保管制度ってなに?
A. 自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらえる制度です。方式チェックもしてくれるので無効になりにくく、紛失や改ざんのリスクも減ります。
Q. 何年ごとに見直せばいい?
A. 財産や家族構成に変化があったとき、5年~10年に一度などの節目ごとに見直すのが理想です。古い遺言が最新の意志と異なると、かえって混乱を招くことがあります。自筆証書遺言の場合は手軽に書き直せるので、1年に1回、誕生日や年末年始に見直すというやり方もあります。
Q. 書き直したい場合はどうすればいい?
A. 遺言書の内容を変更したくなった場合、直接修正するのは無効になるリスクがあるので、全文を改めて書き直すことをお勧めします。その場合「○年○月○日作成の従前の遺言はすべて破棄する」旨の文言を新しい遺言書に入れておくのが安心です。
Q. 家族には内容を事前に伝えるべき?
A. 家族に伝える法的義務はありませんが、家族が遺言の存在や意図を知らないと、実行時に不信感や混乱が生じることもあります。信頼できる家族や遺言執行者には、伝えておくとスムーズです。
6.遺言者の死亡後のこと
Q. 遺言書を発見したらどうする?勝手に開封しちゃったらどうなるの?
A. 自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。封がされている場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。万が一、相続人が無断で開封すると、過料(5万円以下)の制裁対象になることがあります。ただし、開封してしまったとしても、遺言の効力自体は失われません。速やかに家庭裁判所に届け出て、正規の手続きを進めましょう。
これに対して、公正証書遺言の謄本や正本を見つけた場合はすでに公証人が作成・確認済みのため、検認は不要です。封印されていることは通常なく、見つけた時点で開封しても問題ありません。相続人間で遺言の内容を共有し、遺言執行者がいる場合は速やかに連絡をするようにしましょう。
Q. 親が遺言を書いていたかどうかわからない。どうやって探せばいいの?
A. まずは家の中を探してみましょう。自筆証書遺言であれば、金庫や引き出し、仏壇、通帳の近くなどに保管されていることが多いです。
ただし、最近は法務局に預ける「自筆証書遺言の保管制度」を利用している可能性もあります。
この場合、相続人であれば法務局に「遺言書情報証明書の請求」を行うことで、保管の有無を確認できます。
また、公正証書遺言の場合は、公証役場の「遺言検索システム(遺言検索請求)」で調査可能です(死亡届が出された後に利用可能)
7.その他
Q. 行政書士・弁護士・公証人、誰に頼むべき?
A. 一般的には弁護士に依頼すると高額になりやすいでしょう。公証人は遺言書作成の相談には乗ってくれますが、遺言内容が適正かどうかのアドバイスまではしてくれません。どの専門家であっても、その人が本当に相続・遺言に精通しているかどうか、親身になって話を聞いてくれるか、という点がポイントになります。ホームページ等での発信内容や個別相談を通じて判断するしかないでしょう。
Q. 遺言を書いたら争族にならないって本当?
A. 遺言があっても内容次第では争いが起こることがあります。特定の相続人だけに財産を集中させると、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性も。家族間の関係も考慮して内容を検討しましょう。
Q. 遺言書作成はどこまで自分でできる?
A. 自筆証書遺言なら、全て自分で作成可能です。ただし、方式や文言の誤りによる無効リスクがあるため、文案だけでも専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。
Q. 遺言書の作成やチェックを専門家に依頼するメリットは?
A. 法律と実務の両面から、あなたの状況に合った遺言の形を提案してもらえます。作成支援や、公正証書化・証人立会いの手続きサポートまで対応してくれる事務所もあります。
✅ 遺言書の作成に、不安や迷いがある方へ
「この内容で本当に大丈夫?」
「書いた方がいいのはわかっているけれど、何から始めればいいのかわからない…」
そんなときは、専門家に一度ご相談ください。
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を受け付けています。
あなたのご状況を丁寧にお伺いした上で、最適な遺言の形をご提案いたします。
相続関係の整理から文案作成、公正証書遺言の手続きまで、お手伝いします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
