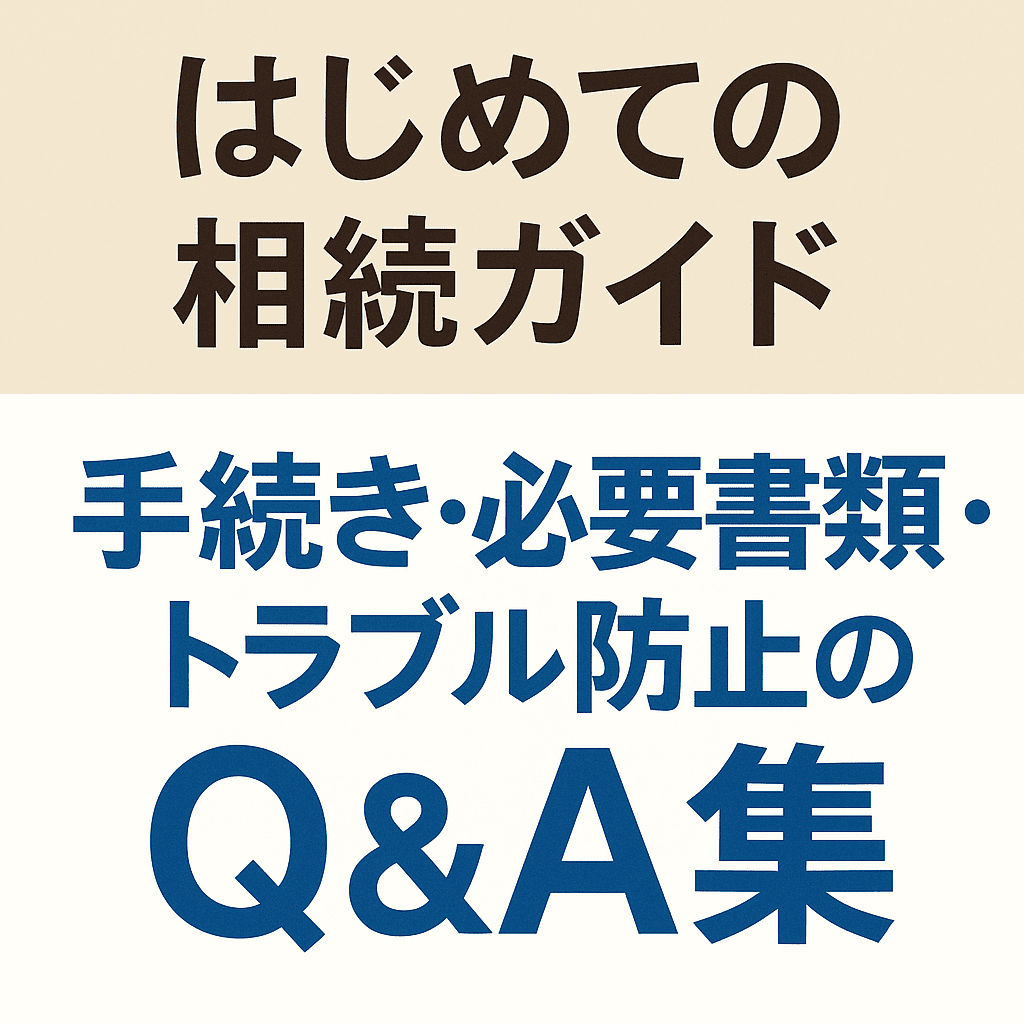
相続は、家族の大切な財産を受け継ぐ一方で、手続きや人間関係に悩みや不安が生じやすい場面でもあります。
このページでは、はじめて相続に直面する方にもわかりやすいように、手続きの流れや必要書類、よくあるトラブルなどを、Q&A形式で相続の基礎知識を整理しました。
疑問を感じたときにいつでも読み返せる、手元のガイドとしてご活用ください。
気になる質問をクリックすると、該当箇所にジャンプできます。
【1】相続人について
Q. 相続人になるのは誰?順位や範囲を教えてください。
A.亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ「法定相続人」には、法律で定められた優先順位があります。基本的には血縁関係にある家族が対象となります。
相続人の順位は次の通りです:
- 第1順位:子(直系卑属) → 亡くなった人の子ども(実子・養子を含む)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属) → 子がいない場合に相続
- 第3順位:兄弟姉妹 → 子も両親もいない場合に相続
配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。他の相続人と「共同相続人」として相続することになります。
Q. 内縁の妻(夫)や事実婚の相手にも相続権はありますか?
A.いいえ、法律上の婚姻届を提出していない「内縁関係」や「事実婚」では、相続権は認められていません。
どれだけ長年連れ添っていても、民法上は「他人」として扱われます。
このような場合は、遺言書で財産を遺贈するか生前贈与するなどの手段をとる必要があります。将来のトラブルを避けるためにも、内縁パートナーがいる場合は遺言の作成が重要です。
Q. 相続人が一人もいない場合はどうなる?
A.相続人がいない場合、すぐに国に財産が帰属するわけではありません。次のような手順が取られます:
- 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任
- 公告を出して相続人を探す(半年間)
- 相続人が見つからない場合でも、遺言や特別縁故者への分与が検討される
- 最終的に、引き取り手がいなければ国庫に帰属
特別縁故者とは、長年介護をしていた人など被相続人と生計を同じくしていた人を指します。該当すれば一部財産をもらえる可能性があります。
Q. 代襲相続とは?
A.代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となるはずだった人が被相続人よりも先に死亡していたり、相続権を失っていたりした場合に、その子ども(孫)が代わりに相続する制度です。
たとえば:
- 父が亡くなり、本来は長男が相続人
- しかし長男がすでに死亡していた
- この場合、長男の子(つまり孫)が「代襲相続人」として相続する
主に子や兄弟姉妹が相続人となる場合に適用されます。
ただし、配偶者には代襲相続の制度はありません。
【2】相続財産について
Q. 相続の対象となる財産には何がありますか?
A.相続の対象となる財産は、被相続人が死亡時に有していたすべての権利義務が含まれます。主なものは次のとおりです:
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式や投資信託などの有価証券
- 自動車や骨董品などの動産
- 借金・ローン(マイナスの財産)
つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続されるのが原則です。
Q. 借金やローンも相続されるのですか?
A.はい、借金・ローン・連帯保証債務なども原則として相続人が承継することになります。
そのため、債務が多い場合には次のような選択肢も考えられます:
- 相続放棄(全ての財産を放棄)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内で弁済)
これらの手続きは家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った日から3か月以内が原則です。
Q. 名義が被相続人のままで他人が管理していた預貯金や不動産も相続財産になりますか?
A.はい、たとえ他の相続人が管理していたとしても、名義が被相続人のままの財産は相続財産として扱われます。
Q. デジタル遺産とは?
A.デジタル遺産とは、被相続人が所有・利用していたインターネット上の資産やデータの総称です。例としては:
- ネットバンクや証券口座の資産
- 仮想通貨(暗号資産)
- 有料会員アカウント(Amazon、楽天、各種サブスク)
- クラウド上の写真・動画・メール
- SNSアカウント(Facebook、Instagram など)
これらも相続の対象になる可能性がありますが、第三者がアクセスするにはログイン情報や手続き方法の明記が必要です。
生前から「デジタル遺産リスト」や「ID・パスワードの管理表」を残しておくと安心です。
Q. 生命保険金は相続財産になる?
A.受取人が指定されている生命保険金は、相続財産には含まれません。
保険契約は「受取人固有の権利」として扱われるため、相続財産とは別枠で受け取ることができます。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 受取人が「相続人全員」など曖昧な場合は相続財産とされる可能性あり
- 相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる
Q. 死亡退職金は相続財産になる?
A.会社から支給される死亡退職金は、退職金規定等の状況によって扱いが異なります。
- 遺族(例:配偶者・子)を受取人と明記している場合は、受取人固有の財産
- 誰宛か特に決まっていない場合は、相続財産として扱われることがある
また、生命保険金と同様に相続税上は「みなし相続財産」とされ、課税対象になります。
Q. 相続財産に含まれないものは?
A.次のようなものは、法律上「相続財産ではない」とされています:
- 生命保険金(受取人固有の権利)
- 死亡退職金(受取人が明記されている場合)
- 遺族年金・未支給年金(原則、請求権者の財産)
- 墓地や仏壇などの祭祀財産(特定の人が承継)
これらは、相続人間で分割協議をする対象とはなりません。
ただし、相続税の計算上は含まれるケースがあるため、注意が必要です。
【3】相続分について
Q. 法定相続分とは何ですか?
A.法定相続分とは、民法で定められた各相続人が相続できる割合のことです。遺言がない場合や、相続人間で合意ができない場合の基準となります。
主な法定相続分は以下のとおりです:
- 配偶者と子が相続人の場合 → 配偶者:1/2、子:1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
- 配偶者と直系尊属(父母など)の場合 → 配偶者:2/3、直系尊属:1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合 → 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
※子が既に亡くなっていて代襲相続がある場合、代襲者がその子の相続分を引き継ぎます。
Q. 遺言がある場合でも法定相続分どおりに分ける必要がありますか?
A.いいえ、遺言がある場合は、原則として遺言で定められた内容が優先されます。
ただし、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保障されています。たとえば全財産を特定の子に相続させるという遺言があっても、他の子や配偶者が遺留分侵害額請求をすれば、一定の金銭を受け取ることができます。
Q. 遺留分って何?
A.遺留分とは、被相続人が遺言などで自由に財産を処分しても、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。
配偶者・子・直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分が侵害された場合は、金銭による「遺留分侵害額請求」が可能です。
請求には期限(原則1年)もあるため、早めの確認が大切です。
※遺言書を作成する際や、生前贈与を行う場合には、この遺留分に注意しないと後から相続トラブルになることがあります。あらかじめ遺留分に配慮した内容にするか、受遺者との間で合意を得ておくのが望ましいでしょう。
Q. 特別受益や寄与分があるときの相続分の計算はどうなるの?
A.相続人の中に以下のような事情がある場合、相続分の計算に調整が加わります:
■ 特別受益(とくべつじゅえき)
→ 被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合、その分を相続分に加算して調整します。
例:長男が生前に住宅資金として1000万円をもらっていた場合、相続財産にその1000万円を加えてから法定相続分を計算します。
■ 寄与分(きよぶん)
→ 被相続人の財産形成や療養看護などに特別な貢献をした相続人がいる場合、他の相続人より多く相続できることがあります。
これらの調整は、基本的に相続人同士の協議や家庭裁判所の判断によって決まります。トラブルの原因にもなりやすいため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
【4】遺産分割協議について
Q. 遺産分割協議とは何ですか?
A.遺産分割協議とは、相続人全員で集まり、被相続人の財産をどのように分けるかを話し合う手続きです。
相続財産は、遺言がない限り原則として相続人全員の共有になります。そのため、分け方を決めて財産の名義を移すためには、遺産分割協議を行う必要があります。
- 協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続登記や預金の解約などに使用します。
- 相続人が一人でも欠けていると無効になるため、必ず全員で行う必要があります。
Q. 協議がまとまらないときはどうなりますか?
A.協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停でも合意に至らないときは、審判手続き(裁判官が判断)に移行します。
Q. 協議書にはどんな内容を書けばいいですか?
A.遺産分割協議書には、次のような内容を記載します:
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 分割対象の財産とその取得者(例:〇〇銀行の預金は長女が取得、不動産は長男が取得 など)
- 協議内容に相違ない旨の文言
- 日付と署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付(登記や預金解約などに必要)
不動産の記載は、登記事項証明書どおりの正確な表記が必要です。
内容に不備があると手続きができない可能性があるため、可能であれば専門家のチェックを受けると安心です。
Q. 相続人が遠方に住む場合に郵送で協議書を作成できるか?
A.はい、郵送でのやり取りによって遺産分割協議書を作成することは可能です。
手順としては:
- 協議内容を文書化し、印刷した協議書を代表者が作成
- 相続人それぞれに順番に郵送し、署名・実印押印
- 印鑑証明書を同封して返送してもらう
全員の署名・実印がそろえば、有効な協議書になります。ただし、郵送途中で内容に変更があると無効になる可能性があるため、内容確定後に署名・押印を行います。
また、相続人の人数が多い場合は各相続人に「遺産分割協証明書」を作成してもらうということも可能です。つまり:
- 協議内容を1枚の文書にまとめたものを、各相続人がそれぞれ別紙として署名・押印する形式
- 各相続人ごとに証明書を作成し、実印+印鑑証明書を添付する
この方法であれば一人一人に郵送するよりも時間の短縮が可能になるため、実務上便利です。
Q. 相続人の中に認知症の人がいる場合はどうすればいいか?
A.相続人の中に判断能力が不十分な人(認知症など)がいる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。このような場合には、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任する必要があります。後見人は本人の代理人として遺産分割協議に参加しますが、他の相続人との利害対立がある場合には、特別代理人の選任が必要になることもあります。後見人や特別代理人は、公平な立場で財産を守る義務があるため、他の相続人の希望どおりに協議できるとは限りません。
相続発生後に慌てないためにも、生前の対策(任意後見や遺言など)が重要です。
【5】相続放棄・限定承認について
Q. 相続放棄はどのように手続きするの?期限は?
A.相続放棄とは、相続人としての権利も義務も一切引き継がないという意思表示です。
借金や保証債務など、マイナスの財産を相続したくない場合に用いられます。
手続きの流れは以下のとおりです:
- 被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述
- 申述書・戸籍謄本などの必要書類を提出
- 裁判所からの照会書に記入し、受理通知をもって手続き完了
一度相続放棄が受理されると撤回できません。
他の財産に手を付けてしまうと、「相続を承認した」とみなされる場合もあるため、注意が必要です。
Q2. 限定承認って何ですか?
A.限定承認とは、被相続人の財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度です。
つまり、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払う」という条件付きで相続する方法です。
ポイント:
- 相続人全員が共同で申述する必要がある(1人では不可)
- 手続きが複雑で、公告・債権者への対応・財産目録の作成などが必要
- 税務申告も複雑になるため、専門家の関与が実質的に必須
相続放棄と違って、プラスの財産も確保しつつ、マイナスも制限できるというメリットがありますが、手続きが煩雑であり公告費用などもかかるため、実務上は利用が難しい制度です。
Q. 亡くなった人の負債の有無はどうやって調べる?
A.負債の有無を正確に把握するのは簡単ではありませんが、実務上は通帳や郵便物を確認したり信用情報機関、金融機関等への照会によって明らかにしていきます。ただし、第三者の保証人になっているなど、完全に債務を把握するのは困難なケースもあります。少しでも不安がある場合は専門家に相談して相続放棄を検討するのがよいでしょう。
【6】相続手続き全般について
Q. 相続が発生したらまず何をすればいいですか?
A.相続が発生した場合、まずは次のような流れで手続きを進めていきます:
- 死亡届の提出と火葬許可の取得
- 遺言書の有無を確認(必要であれば家庭裁判所への検認手続きも)
- 相続人の確定(戸籍の収集)と相続財産の調査
- 相続放棄や限定承認の検討(3か月以内)
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告(10か月以内)
期限がある手続きも多いため、事前に全体像を把握し、優先順位をつけて対応することが大切です。
Q. 相続登記の義務化とは?期限や罰則はある?
A.2024年4月の法改正により、不動産の相続登記が義務化されました。
概要は以下の通りです:
- 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料(罰金)の対象に
登記をせずに放置すると、名義が亡くなった人のままとなり、将来的に相続人が増え続けて手続きが困難になるケースも多く見られます。早めの登記申請をおすすめします。
Q. 相続トラブルを防ぐために生前できる準備は?
A.相続トラブルの多くは、「誰がどれを相続するか」が曖昧なまま残されることにより発生します。以下のような生前対策が有効です:
- 遺言書の作成(特に公正証書遺言が安心)
- 財産目録の作成(デジタル資産も含めて)
- 相続税対策・分割しやすい財産への工夫
- 家族への情報共有・話し合いの機会をもつ
また、認知症などのリスクに備えて、任意後見契約や家族信託を活用する方法もあります。
Q. 配偶者居住権とは?
A.配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が居住していた建物にそのまま無償で住み続けることができる権利です。2020年の民法改正で新設されました。
ポイント:
- 原則として配偶者の終身にわたって居住可能
- 建物や敷地の所有権とは別に「居住権」として登記される
- 相続分を分け合ううえで、住居を取得しつつ金銭的相続分も確保しやすくなる
高齢の配偶者が住む場所を失うリスクを避けるために、有効な制度です。
ただし、遺産分割協議や遺言によって明確に設定されていることが必要です。
✅ 相続のお悩み、ひとりで抱え込まずにご相談ください
相続の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。
だからこそ、専門家のサポートを受けることで、手続きの不安や相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を承っています。
相続人調査や遺産分割協議書の作成など、状況に応じた最適なご提案をいたします。
「何から始めたらいいかわからない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
