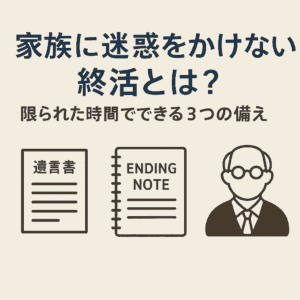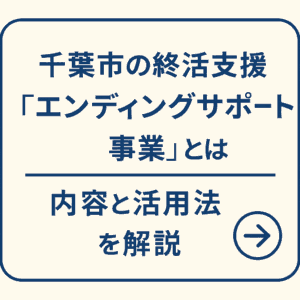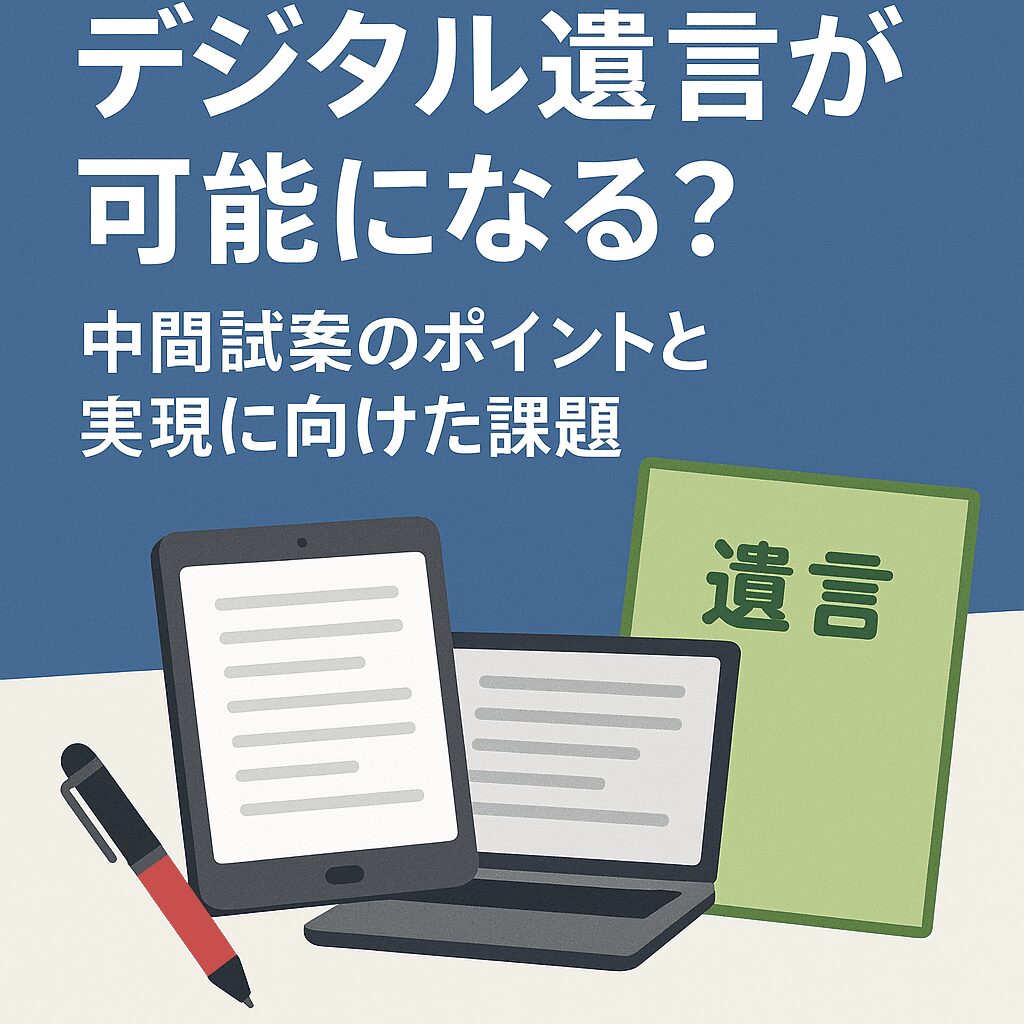
はじめに|デジタル時代に向けた遺言制度の見直し
2024年から、「デジタル遺言」制度化を含む遺言制度の見直しが本格的にスタートし、このたび改正に向けた中間試案が公表されました。
現行の民法では遺言書は紙と自署が基本で、電子的な作成は認められていません。しかし社会のデジタル化が進む中で、パソコンやスマートフォンで遺言を作成・保管できる仕組みを導入すべきだという声が高まっています。
今回の改正検討は単に紙の代わりにパソコンを使うだけではなく、映像や音声による遺言意思の記録といった新しい手法も含め、幅広く議論が行われています。
本記事では、この中間試案の内容をわかりやすく整理し、制度化によって何が変わるのか、そして実現に向けた課題やスケジュールを解説します。
1. 中間試案の概要|「第四の方式」としてのデジタル遺言
「デジタル遺言」とは、遺言者が紙ではなく電磁的記録(電子文書)によって遺言内容を残す新たな方式を指します。中間試案では、デジタル遺言を現行の普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)に加わる「第四の方式」として位置づける方向が示されました。特に、自筆証書遺言のデジタル版に近いイメージです。
特徴は以下の通りです。
- 電磁的記録(電子文書)による作成を認める
- 本人確認や改ざん防止のための技術的要件を設定
- 保管・管理方法に応じて複数の方式を検討(後述)
- 普通方式だけでなく、死亡危急時などの特別方式にも応用可能
特別方式の案としては、遺言者と証人のやり取りを録画し、その映像を遺言データとして保存する仕組みが提案されています。緊急時には、口頭や筆記が難しい場面でも映像・音声で意思を残せるようにする狙いです。
2. デジタル遺言で何が変わるのか|3つの方式案
中間試案では、デジタル遺言の具体的な運用方法として3つの方式案が示されています。
| 方式 | 概要 | メリット | 課題 |
|---|---|---|---|
| 方式A:証人立会い型(自己保管) | 自宅等で遺言を電子作成。証人2名が立会い、やり取りを録画。本人がデータを保管。 | 専門家や証人関与で真正性確保。自宅で完結可能。 | 証人確保の負担。死後に発見されないリスク。検認が必要。 |
| 方式B:公的機関保管型 | 電子作成後、法務局などに提出・保管。 | 公的保管で所在不明や改ざんのリスク低減。検認不要。 | 手数料や窓口手続の負担。高齢者のデジタル対応。 |
| 方式C:プリントアウト型 | 電子作成→紙に印刷し自署→法務局保管。 | 電子で作成しやすく、公的保管のメリットも享受。 | 最終的に紙で署名するため真の電子化ではない。 |
このうち、方式Bは利便性と信頼性のバランスが良く、実務面でも導入しやすいと評価されています。一方、方式Aは自由度が高い反面、死後に発見されないリスクが大きく、方式Cは利便性向上の度合いが限定的です。
3. 実現に向けたハードルと懸念点
制度化にあたっては、利便性だけでなく現行制度と同等の信頼性を確保することが大前提です。実現に向けた主な課題は以下の通りです。
本人確認の方法
まず、本人確認ではマイナンバーカードによる電子署名や顔認証などが検討されていますが、カードを持たない高齢者への配慮として窓口での対面確認を残す案などが検討されています。
改ざん防止策
次に、改ざん防止策としてタイムスタンプや電子証明書、ブロックチェーンの活用が提案され、自己保管型でも真正性を検証しやすくする方法が模索されています。
利用者支援や保管等の問題
さらに、ITに不慣れな人のために、行政書士など専門家のサポートや窓口対応などによって広く利用しやすくする工夫もあわせて検討されているほか、電子データを保管するのに公的機関を新たに設ける場合はその具体的な手続きや保管のあり方などの議論を煮詰める必要があります。
また、方式Aでは検認の要否や、遺言の更新・撤回の方法も論点です。利便性を高めつつ、真意を担保する仕組みをどう設計するかが、制度化のカギとなります。
4. 今後のスケジュールと注目ポイント
デジタル遺言の制度化は、以下の流れで進む見込みです。
- パブリックコメント(意見公募手続き)
市民・専門家からの意見を反映 - 要綱案の作成
中間試案をもとに最終案を作成 - 国会提出・審議・法改正
早くても2026年以降の施行が見込まれる
法務省は諸外国(米・加・韓・中・英・独・仏)の電子遺言制度を調査中で、各国の成功例や課題も踏まえた制度設計が期待されます。
5. まとめ
デジタル遺言は、利便性を大きく高める可能性を持つ一方で、本人確認や改ざん防止、高齢者対応など解決すべき課題も多くあります。制度化されても、すぐに全員がスムーズに利用できるわけではありません。
制度化を待つ間にも、私たちにできる備えはあります。
- 現行制度での自筆証書遺言・公正証書遺言の作成
- エンディングノートで想いを整理
- 専門家に相談し、自分に合った遺言方法を検討
「未来の遺言」の形を考えることは、今の備えを見直すきっかけにもなります。
デジタル遺言の動向を注視しつつ、現行制度を活用して早めの準備を進めることが、安心への第一歩です。