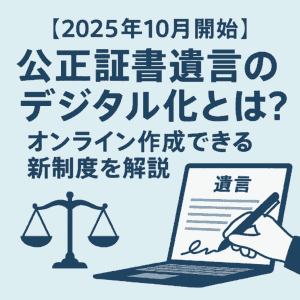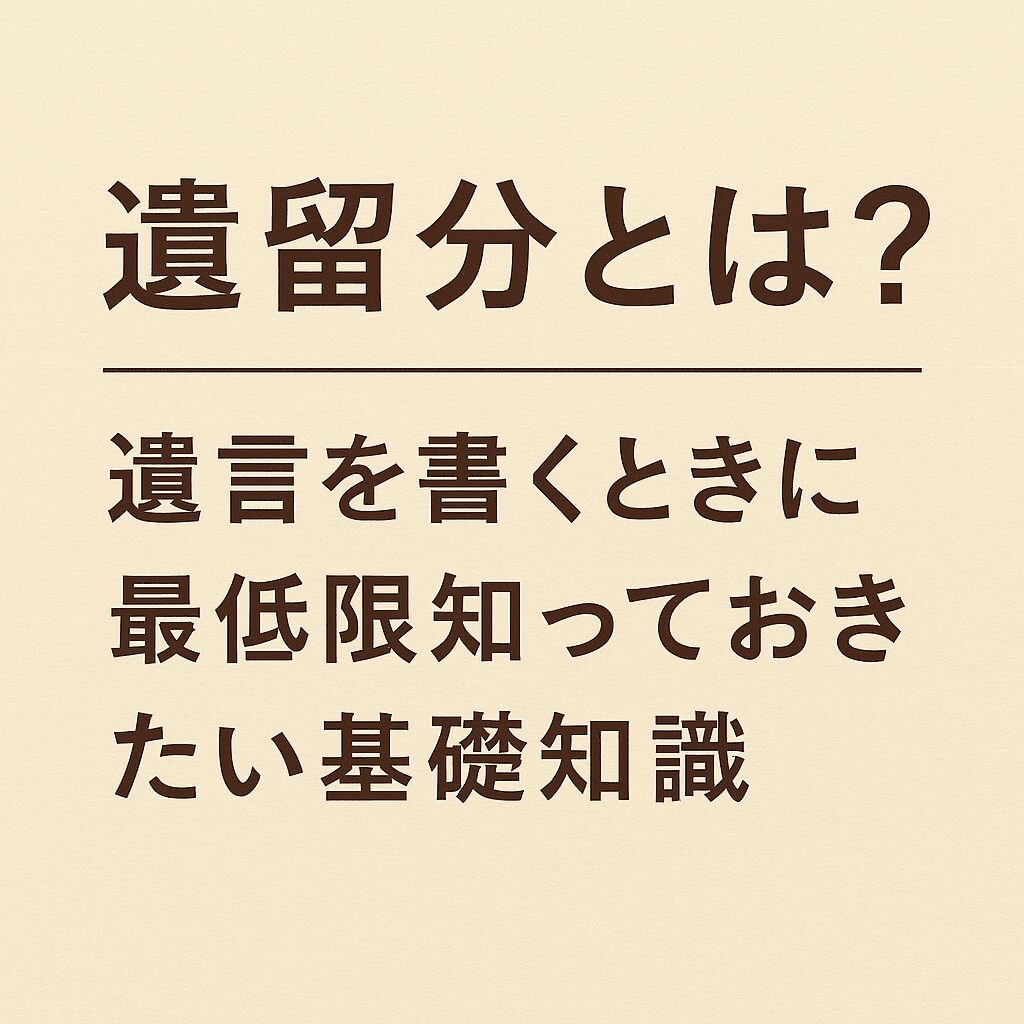
1. はじめに|なぜ遺留分を知っておく必要があるのか
「遺言は自分の好きなように書ける」と思っている方は少なくありません。たしかに、遺言は自分の財産をどう分けるかを自由に決められる強力な手段です。しかし一方で、法律は相続人の権利も守る仕組みを用意しています。その代表的なものが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
もし遺留分を無視した内容の遺言を書いた場合、遺された家族の間で「不公平だ」と感じる人が出て、遺言がきっかけでトラブルになることもあります。せっかくの遺言が争いの火種になってしまうのは避けたいところです。
そこで本記事では、一般の方が遺言を書くときに最低限知っておきたい「遺留分の基礎知識」をわかりやすく解説していきます。
2. 遺留分とは?|遺言でも奪えない最低限の取り分
遺留分とは、法律で定められた「相続人の最低限の取り分」のことを指します。これは遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に必ず認められる権利です。
たとえば「全財産を長男に相続させる」といった遺言を書いた場合でも、他の相続人がまったくのゼロになるとは限りません。法律上の遺留分がある人は、「自分の取り分を返してほしい」と主張できるのです。
誰に遺留分があるのか
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者(夫または妻)
- 子ども(実子・養子を含む)
- 直系尊属(父母など) ※子どもがいない場合
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、「兄弟に一切渡さずに友人や団体に寄付したい」という場合でも、遺留分侵害を心配する必要はありません。
3. 遺留分の割合|具体的にどのくらいの取り分があるのか
遺留分は、法定相続分(法律で決められた取り分)の一部として計算されます。おおまかなイメージをつかむために、代表的なパターンを整理してみましょう。
配偶者と子どもが相続人の場合
相続人が配偶者と子ども(複数)の組み合わせであることが一番多いケースです。
- 法定相続分:配偶者 1/2、子ども全員で 1/2
- 遺留分:その合計の 1/2
つまり、配偶者と子どもにそれぞれ「法定相続分の半分」が最低限の取り分として保障されます。
配偶者のみが相続人の場合
- 法定相続分:配偶者 1/1
- 遺留分:1/2
→ 配偶者に必ず「財産の1/2」の遺留分があることになります。
親(直系尊属)が相続人の場合
子どもがいない場合には、両親など直系尊属が相続人となります。
- 法定相続分:親が1/1
- 遺留分:その 1/3
兄弟姉妹が相続人の場合
繰り返しになりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
このように、遺留分は「常に法定相続分どおり」というわけではなく、相続人の組み合わせによって変わる点に注意が必要です。
4. 遺留分侵害額請求とは?|トラブルになったときの権利行使
もし遺言や生前贈与によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」という手続を使って不足分を取り戻すことができます。
昔の「減殺請求」との違い
以前は「遺留分減殺請求」という制度がありましたが、現在は「金銭請求」が原則です。つまり、「自分の遺留分を返せ」と言ったときに、必ずしも不動産や株式を共有でもらうのではなく、金銭で補填してもらう形になりました。これにより、相続財産の共有状態を避け、紛争を長引かせない狙いがあります。
権利行使の期限
遺留分侵害額請求には時効があります。
- 相続開始と侵害を知ったときから 1年以内
- 相続開始から 10年以内
この期間を過ぎると権利を主張できなくなります。
実際に請求が起こるケース
法律上は請求できても、現実には必ずしも行使されるとは限りません。家族関係が良好であれば「遺言者の意思を尊重して請求しない」というケースも多く見られます。
5. 遺言を書くときの注意点|遺留分を踏まえた工夫
遺言を作成するときには、遺留分を踏まえて内容を検討することが望ましいといえます。ただし、「遺留分を侵害しないようにしなければならない」というわけではありません。ここでは、その考え方のバランスについて解説します。
遺留分を意識して調整する方法
相続人同士の関係が微妙であったり、財産をめぐる不安がある場合には、遺留分を侵害しないように配分する方が無難です。そうすれば、侵害額請求をされるリスクを最小限にできます。特定の相続人に多めに渡したい場合でも、遺留分にあたる金額を代償金として用意しておく、といった工夫が可能です。
「必ず守らなければならない」わけではない
一方で、実務の現場では「遺留分を侵害しないように」と考えすぎる必要もありません。たとえば配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者にすべてを相続させる遺言は珍しくありません。
子どもとしても「いずれ二次相続(配偶者の相続)で財産を受け取れる」と考えることが多く、現実的にトラブルに発展しないケースは少なくないのです。むしろ、遺言者が「配偶者の生活をまず第一に守りたい」と望むなら、その気持ちを尊重することの方が大切でしょう。
リスクも理解しておく
もちろん、家族の仲が悪い、あるいは相続人の一部が金銭にシビアな場合には、遺留分侵害額請求が起こる可能性があります。そのリスクは踏まえておく必要があります。
遺言者の思いをどう表現するかが第一
最も大切なのは、「遺留分をどう計算するか」ではなく「遺言者の意思をどう残すか」です。自分が大切にしたい人にしっかり財産を残したい、家族に感謝の気持ちを伝えたい。そうした思いが明確に表れていれば、相続人も納得しやすく、円満な相続につながります。
6. 遺留分に関する誤解と注意点
遺留分は遺言を考えるうえで重要なルールですが、一般の方の間では誤解されやすいポイントも多くあります。ここでは代表的な注意点を整理してみましょう。
「遺言で自由に全部決められる」という思い込み
「自分の財産だから、遺言で好きなように分ければいい」と考える方は少なくありません。たしかに原則として遺言の自由は広く認められていますが、相続人に遺留分がある場合、それを侵害すると後で請求される可能性があります。結果的に「遺言どおりに相続が進まない」ということも起こり得ます。
遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
相続人が「自分は財産はいらないから、遺留分も放棄する」と考えても、その意思だけでは有効になりません。遺留分の放棄を生前に行う場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。許可を得ずに書面だけで合意しても、後で無効となってしまうので注意が必要です。
トラブルの大半は「知らなかった」が原因
実際の相続争いでは、「遺留分」という制度を知らずに遺言を書いた結果、思わぬ請求を受けてトラブルに発展するケースが少なくありません。逆に、事前に制度を理解していれば、請求リスクを踏まえた上で納得のいく遺言を残すことができます。
7. まとめ|遺言と遺留分を両立させて円満な相続を
遺言は、自分の思いを将来に伝えるための大切な手段です。しかし、法律は相続人の生活を守るために「遺留分」という最低限の権利を定めています。
遺言を書くときに遺留分を理解しておけば、相続人が不公平感を持たず、円満な手続きにつながりやすくなります。ただし、必ずしも「遺留分を侵害しないこと」が唯一の正解ではありません。配偶者に生活の安定を優先してすべてを託す、といった遺言もよく見られるものであり、遺言者の意思を第一に考えることが何よりも大切です。
要するに大切なのは、
- 遺留分というルールを理解したうえで、リスクとメリットを把握すること
- 自分の思いをどう表現するかを軸に、遺言の内容を考えること
この2点です。
そして不安があれば、専門家に相談するのも一つの方法です。法律の仕組みや家族の状況を踏まえたアドバイスを受けることで、より安心して「自分らしい遺言」を残すことができるでしょう。
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
遺留分を意識した遺言は、家族の安心を守るために欠かせません。
「自分の場合はどうなるのか」を知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で承っております。
初回60分は相談無料です。ご来所のほか、オンライン(Zoom)にも対応していますので、安心してお話しいただけます。」