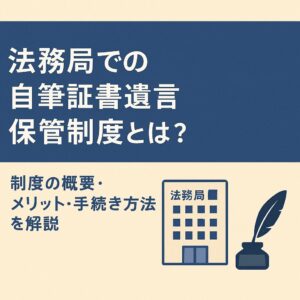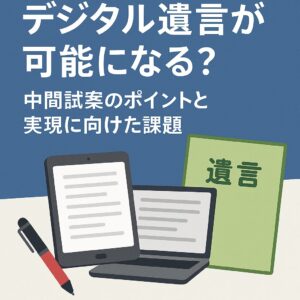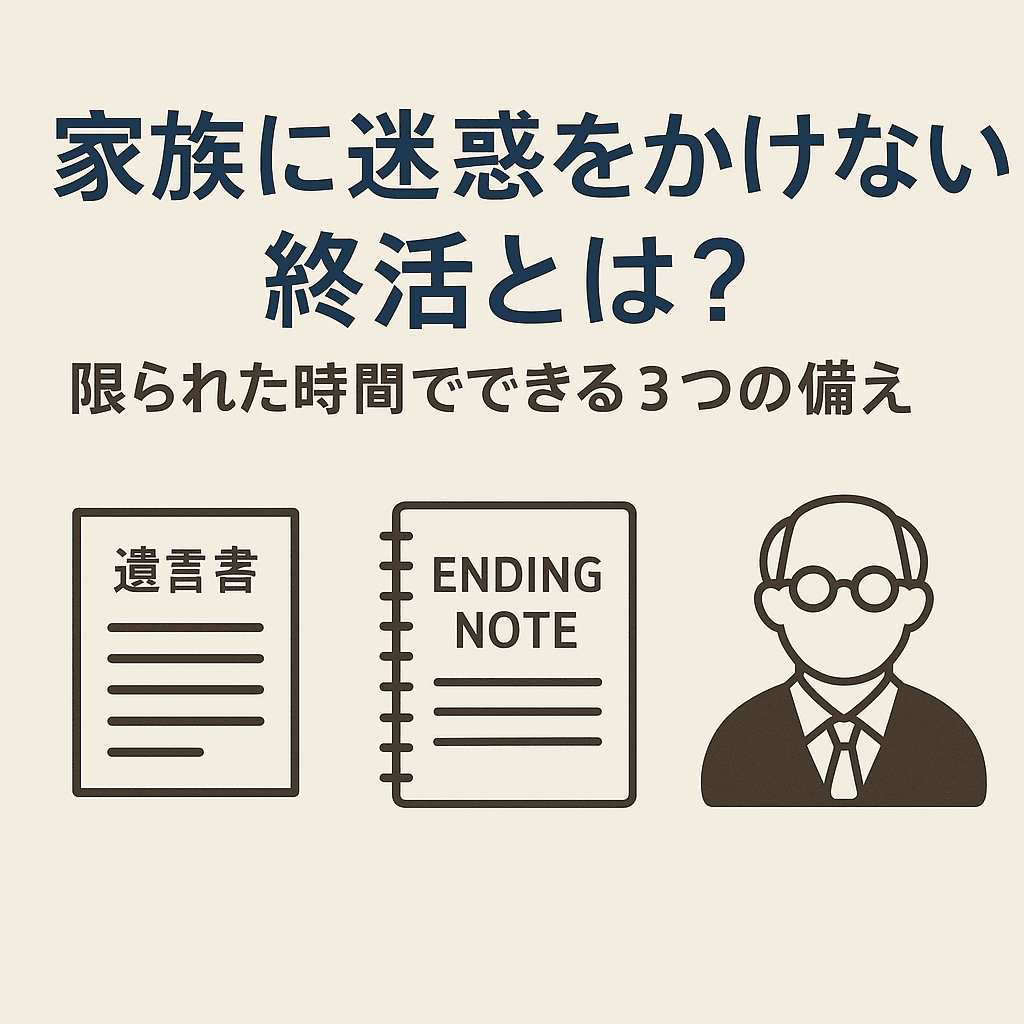
はじめに
「終活はまだ早い」と思っていませんか?
たしかに、終活は高齢者や定年後の人が始めるものというイメージが強いかもしれません。
しかし、病気や体調の不安、あるいは医師から余命の告知を受けることで、「もしもの時」がすぐ近くに迫っているという状況になることもあります。
そんな中でよく聞かれるのが、「家族に迷惑をかけたくない」という切実な思いです。
この記事では、限られた時間でも準備できる「家族に迷惑をかけないための3つの備え」をご紹介します。
第1章:家族に迷惑をかけない終活とは?
終活は、人生の最期を迎えるにあたって、単に「自分のための準備」というだけではなく、「残される人たちのための配慮」という側面が大きいです。
なかでも、「家族に迷惑をかけない終活」とは、次のような考え方に基づいています。
- 自分の死後に、家族が手続きや判断で困らないようにしておく
- 残すもの・残さないものを整理し、感情面でも整理がつくようにする
- 最後まで自分らしい生き方を貫くための意志表示を行っておく
とくに、遺された家族が直面する負担は、次のように大きく3つに分けられます。
- 財産の相続に関する法的・実務的な手続き
- 葬儀や住まいの片づけといった「死後の実務」
- 「本人がどうしたかったのか」が分からないことによる精神的な葛藤
これらの負担を軽減するためには、「何を・どこまで・誰に」託すかを考えることが大切です。
実際、終活のすべてを完璧に整える必要はありません。
押さえるべき3つの備え——「遺言書」「エンディングノート」「死後事務委任契約」——があれば、それだけで家族の負担は大きく減らすことができます。
第2章:3つの備え①|遺言書
「うちは子どももいないし、夫にすべて渡ればいいと思っているから、遺言なんて必要ないと思っていた」
実際に、そうおっしゃる方は少なくありません。ですが、法律における「相続の仕組み」は、私たちがイメージする“家族の常識”とズレている場合があります。
たとえば、配偶者にすべてを遺したいと考えていても、子どもがいない夫婦の場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
また、「仲の良い姉にも一部だけ財産を分けたい」といった希望も、遺言書がなければ実現できません。
自筆でもよいが、専門家の支援を受けて整えるのが安心
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言の方が確実でトラブルも少ないですが、時間や費用、外出の負担などの理由から、「まずは自筆で」と考える方も多くいます。
実際、自筆証書遺言でも法的効力はあり、きちんとした形式で書けば十分に通用します。また、法務局の保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要になるなどのメリットもあります。
ただし、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを明確に書く必要があり、不備があると無効になることもあります。
また、遺言書を作成する際に特におすすめしたいのが、遺言書の中で「遺言執行者」を専門家に指定しておくことです。
これは、遺言に書かれた内容を実際に実行する人のことで、弁護士や行政書士といった第三者をあらかじめ指定しておくことで、家族に負担や手間をかけずに相続を進めることができます。
関連記事
📌コラム:預金口座の相続の流れと遺言の力
人が亡くなると、銀行口座は一時的に凍結されます。
ご家族が「すぐにでも葬儀費用を引き出したい」と思っても、原則として遺産分割協議書や戸籍などの提出がないと払い戻しができないのが現実です。
これに対し、遺言書があれば話は変わります。
遺言書に基づいて特定の人に相続させる旨が明記されていれば、その人がスムーズに金融機関で手続きを進めることが可能になります。
とくに、生活費の引き出しや葬儀の支払いなど、亡くなった直後に必要となるお金の対応をどうするかという点は、遺族にとって大きな問題です。
遺言書があることで、そうした場面でも慌てずに対応することができます。
第3章:3つの備え②|エンディングノート
「エンディングノートって、書いても意味がないんじゃないか?」
そう感じる方もいるかもしれません。たしかに、エンディングノートには法的効力はありません。
けれども、家族にとっては“何よりもありがたい道しるべ”になることが少なくないのです。
遺言書が法的なルールを定める文書だとすれば、エンディングノートは気持ちや暮らしを伝えるための記録帳。
そこに記された「こうしてほしい」「これは伝えたい」といった想いは、手続き以上に家族の支えになることがあります。
書けることはいろいろあります
- 医療や介護に関する希望(延命治療、最期の過ごし方など)
- ペットや植物など、自分の代わりに世話してほしいこと
- 日常生活の中で使っていたサービスやSNSのID・パスワード
- 家族や友人へのメッセージ
- 財産のリスト(預金、不動産、保険、証券など)
財産目録が“探す手間”を減らす
とくにエンディングノートの中でも重要なのが、財産目録(財産一覧)です。
相続の際に時間と手間がかかるのが、何がどこにあるのかを調べる「財産調査」です。
エンディングノートにあらかじめ銀行口座や証券、不動産、加入している保険などを一覧化しておくことで、家族は調査の手間を大きく省くことができます。
「これだけでも書いておいてくれて助かった」
——実際に、そう語るご遺族の声は少なくありません。
📌コラム:葬儀の手配は生前でもできるって知っていますか?
終活を考え始めると、葬儀のことが気になる方も多いのではないでしょうか。
「まだ早い」「縁起でもない」とためらう方もいますが、最近は生前のうちに葬儀社と事前相談や契約を交わす方が増えています。
たとえば、次のようなことを生前に決めておくことができます。
- 希望する葬儀のスタイル(火葬式、家族葬、無宗教式など)
- 葬儀社やプランの選定(費用感の把握も)
- 連絡してほしい人や知らせたくない人のリスト
- 遺影写真や使いたい音楽の指定
葬儀の内容が明確になっていれば、遺されたご家族も迷うことなく、安心して送り出すことができます。
事前に費用を準備しておくこともできるため、経済的な負担の軽減にもつながります。
第4章:3つの備え③|死後事務委任契約
遺言書やエンディングノートで「財産」と「想い」の整理ができたとしても、実はもう一つ、大切なことがあります。
それが、「死後の手続きを誰が行うのか」という問題です。
人が亡くなったあとには、さまざまな実務的な処理が必要になります。
たとえば、
- 賃貸住宅の解約や公共料金の精算
- 病院への未払金の支払い
- クレジットカードや会員サービスの解約
- SNSやメールアカウントの削除
- 火葬や納骨の手続き など
これらの手続きは「相続」とは別の領域であり、法律上、誰かが勝手にやってよいというわけではありません。
家族がやろうとしても、委任状や法的根拠が求められることがあり、意外とハードルが高いのです。
そこで役立つのが、「死後事務委任契約」です。
これは、自分が亡くなったあとの事務手続きをあらかじめ信頼できる人(または専門家)に正式に委ねておく契約です。
行政書士などの専門職と契約を結んでおけば、上記のような煩雑な手続きを代行してもらうことができ、遺された家族の負担は大きく軽減されます。
また、身寄りがない方や、家族にはあえて頼りたくないという方にも有効な手段です。
まとめ:3つの備えで、家族の負担は最小限に
「家族に迷惑をかけたくない」
その思いを形にするために——
以下の3つの備えがあるだけで、終活はじゅうぶん整います。
- 遺言書
…財産の分け方や意思を明確にし、相続トラブルや手続きを簡素化する。
自筆でもOK。執行者に専門家を指定しておくと、家族の負担がさらに減る。 - エンディングノート
…法的効力はないが、暮らしや想いを伝える重要な手段。
財産目録を残すことで、相続人の“財産調査の手間”も軽くなる。 - 死後事務委任契約
…葬儀・解約・住まいの処分など、死後の煩雑な事務手続きをあらかじめ信頼できる人に任せておく。
これらを備えておけば、法律的にも実務的にも、そして気持ちの上でも、家族への配慮が行き届いた終活になります。
「すべて完璧に整えるのは難しそう」と感じるかもしれません。
ですが、一歩踏み出せば、気持ちはぐっと軽くなるものです。
まずはエンディングノートからでも、できることから始めてみませんか?
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
「何から始めればいいか分からない」
「遺言や契約書をどう書けばいいの?」
「自分にとって必要な備えを一緒に考えてほしい」
そんな方のために、初回60分の無料相談を行っています。
事務所での対面相談はもちろん、Zoomによるオンライン相談も可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。