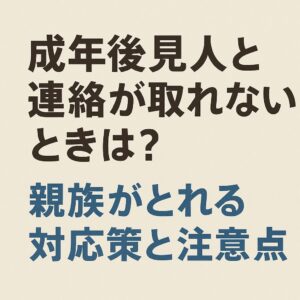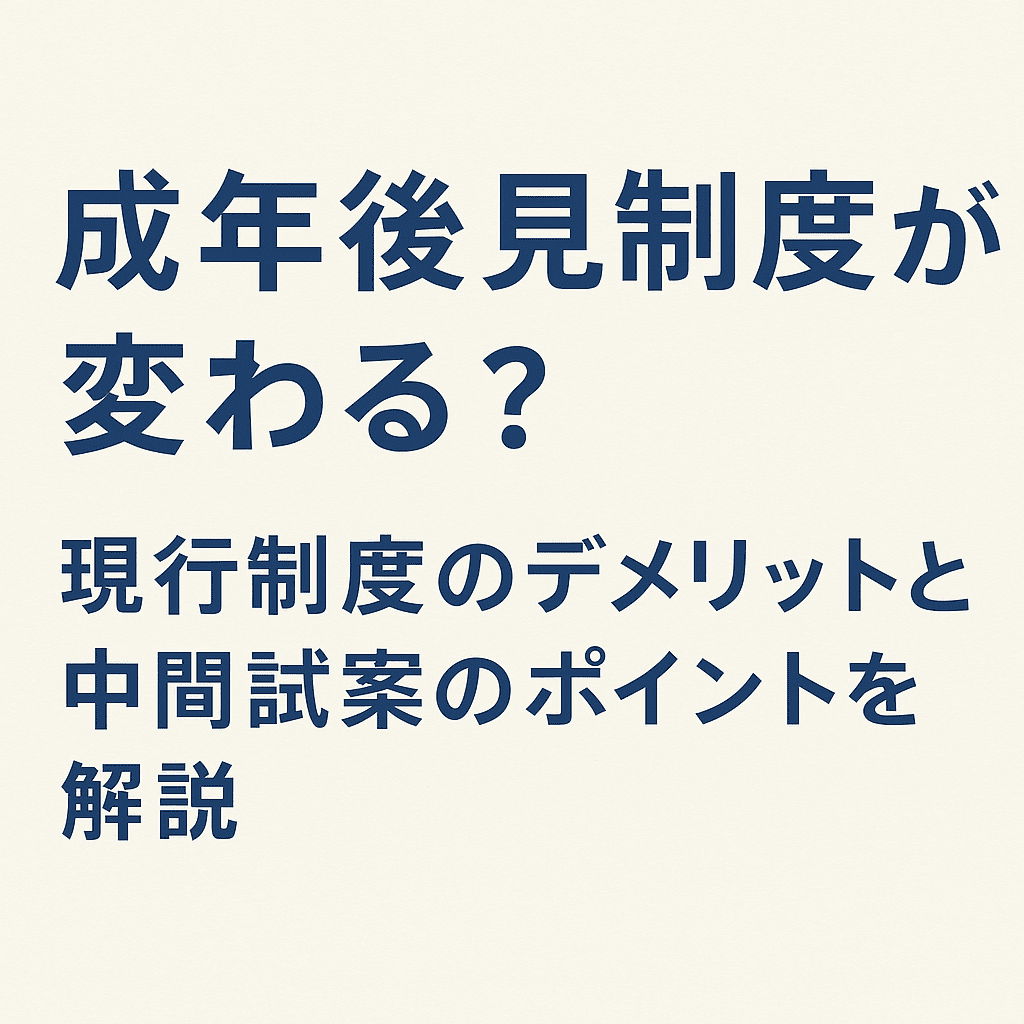
成年後見制度の利用が進まない現状
高齢化が進む中で、認知症などによって判断能力が低下した方を法律的に支援する「成年後見制度」。
財産の管理や契約行為を代わって行うことで、本人の暮らしを守る仕組みとして2000年にスタートしました。
しかし、制度ができて20年以上が経った今も、思ったほど利用が広がっていないのが実情です。
統計によると、認知症の高齢者は全国で400万人以上と言われています。
これに対して、成年後見制度の利用者数は約25万人にとどまります。
そこで、今、制度の大きな見直しが進められており、このたび法制審議会は、中間試案をまとめました。この中間試案は2025年6月下旬にパブリックコメントに付され、さらなる議論を経て、2026年度の法改正の成立を目指すとされています。
この記事では、まず現行制度の「デメリット」を紹介し、そのうえで今後どう変わっていくのかを解説します。
1.現行制度の3つのデメリット
成年後見制度は、本人の権利を守るという点では大切な制度ですが、次のような課題が指摘されてきました。
(1) 一度始めたらやめられない「終身制」
現行制度では、いったん家庭裁判所で後見開始の審判が出されると、基本的には被後見人本人が亡くなるまで後見状態が続くことになります。
たとえ本人の判断能力がある程度回復したり、支援の必要がなくなったとしても、制度的には終了が難しい仕組みです。
このように、長期にわたって拘束される仕組みであることが、制度利用をためらう要因になっていました。
(2) 家庭裁判所の監督が厳しく、使い勝手が悪い
後見人は、本人のお金の使い道や財産管理について、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
また、本人の財産を大きく動かすとき(たとえば不動産を売る、リフォームするなど)は、裁判所の許可が必要になります。
善意の家族が後見人になったとしても、必要なことがスムーズにできず、対応に疲弊してしまうケースも少なくありません。
(3) 本人の意思が十分に尊重されない場合がある
現行制度では、成年後見人に包括的な取消権、代理権があるため、本人保護の名のもとに本人の意思決定が必要以上に制限されるおそれがあるという問題があります。
たとえば、本人が希望する生活スタイルや支出内容があっても、後見人の判断で制限されることがあります。
このような制度設計に対しては、国際的にも批判があり、特に国連の障害者の権利に関する条約の観点から「本人の自己決定権を過剰に制限している」との指摘もあり、見直しが求められてきました。
2. 見直しのポイント
こうした課題を受け、今回の「中間試案」では主に次の3つの論点について改革案をとりまとめました。
(1) 利用期限の見直し|必要がなくなれば「やめられる」制度に
これまでの制度では、一度後見が始まると原則としてやめることができませんでした。
改正案では、この終身制を撤廃し、
- 本人の判断能力が改善した場合
- 家族信託など、他の手段で支援が可能な場合
などにおいて、途中で後見を終了できる案が盛り込まれています。
また、あらかじめ「〇年後に見直す」「〇〇の場面だけに限定して使う」といった期間・用途限定の制度設計も検討されています。
(2) 柔軟な制度設計|“必要な支援だけ”を選べるように
従来は「後見」「保佐」「補助」の3類型から選ぶ仕組みでしたが、
実際には類型ごとの違いがわかりにくく、運用も複雑でした。
そこで今後は、本人の状況に応じて、
- 支援内容をオーダーメイドで設定したり
- 不要になった権限を縮小・解除したり
といった柔軟で本人本位の制度運用が可能になるような仕組みが検討されています。
(3) 家族信託や任意後見との併用が可能に
現行制度では、家族信託や任意後見との併用が制度的に曖昧で、実務上も混乱のもとになっていました。
今回の見直しでは、
- 財産管理は家族信託、
- 身上保護(医療・介護)は成年後見、
- 判断能力があるうちに任意後見を用意しておく、
といった支援の組み合わせを制度的に容認・推進する方向です。
これにより、本人や家族の事情に合わせた「一番ちょうどいい支援」を選びやすくなります。
3. 今後の見通し
成年後見制度の見直しは、2026年度の通常国会にて法改正を目指すとされています。
✅ では、それまで後見申立ては待ったほうがいいの?
これはケースバイケースです。
たとえば…
- すでに判断能力が著しく低下していて、医療契約や施設入所などができない
- 預金が凍結されてしまっている
- 不動産の売却など、法律行為が必要になっている
このような場合は、今の制度で法定後見を申し立てるしかないというのが現実です。
ただし、今後は「終身制が撤廃される可能性」があるため、
現在の申立てでも「将来的に終了できる可能性がある」という前提で進められるようになるかもしれません。
✅ 制度改正を見据えて今できる備えは?
法定後見のほかにも、以下のような準備をしておくことで、柔軟な対応が可能になります。
- ✅ 判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおく
- ✅ 家族信託などを活用して、財産管理を先に仕組み化しておく
- ✅ 見守り契約や財産管理委任契約を通じて、徐々に支援体制を構築
こうした「判断能力がまだある段階での備え」が、今後ますます重視されるようになります。
4. まとめ
成年後見制度は、本人の暮らしを守るための大切な制度です。
しかしこれまでは、
- 一度始めると終わらない
- 裁判所の監督が厳しく使いにくい
- 本人の意思が軽視されがち
という問題から、「制度はあるけど使いづらい」と感じる人が多くいました。
ようやくこの制度が「本人に寄り添ったもの」へと変わろうとしています。
終身制の見直しや、家族信託との併用など、柔軟で現実に即した仕組みに整備されていくのは、とても大きな一歩です。
改正はまだ少し先ですが、今のうちに情報を整理し、状況に応じた備えを考えておくことが、将来の安心につながります。
👇 お気軽にご相談ください
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を随時受け付けています。
まずは「話を聞いてみたい」だけでも大丈夫です。何を相談すればいいかもわからない、という方でも丁寧に現状をヒアリングしてアドバイスいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。