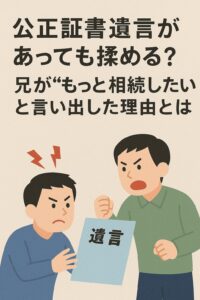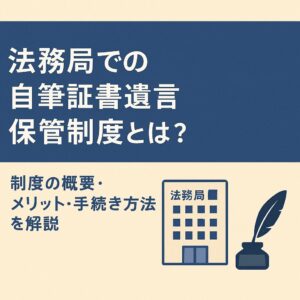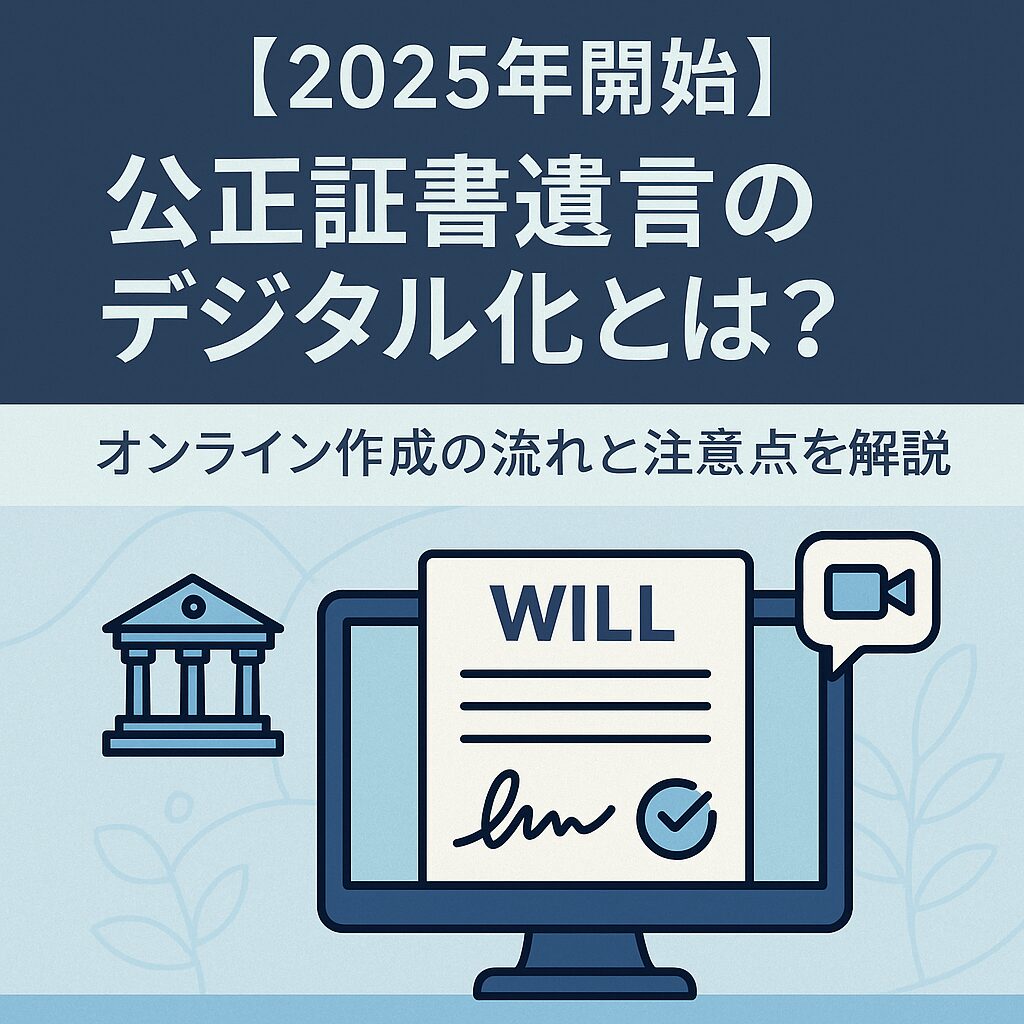
はじめに|「公正証書遺言のデジタル化」が始まります
遺言は、人生の最期に自分の意思を明確に残すための大切な手段です。中でも「公正証書遺言」は、法律的に最も安全性が高く、確実に執行される形式として多くの方に選ばれています。
しかし一方で、「公証役場まで行くのが大変」「証人の手配が面倒」といった理由で、公正証書遺言を敬遠する方が少なからずいらっしゃるのも事実です。
こうした背景を踏まえ、2025年(令和7年)を目処に、公正証書遺言の作成手続きをオンラインで行える制度の導入が予定されています。いわゆる「公正証書遺言のデジタル化」です。
この記事では、この新制度によって何がどう変わるのか、現在の制度と比べながら分かりやすく解説していきます。
1. 現行の公正証書遺言の作成手続き
まずは、公正証書遺言の現在の手続きがどのように行われているのかをおさらいしておきましょう。
● 作成の流れ(現行)
- 事前相談・打ち合わせ
公証役場または専門家(弁護士・行政書士など)に遺言内容の相談をします。正式な作成前に、公証人に原案を提出し、文言や形式について調整します。 - 公証役場での作成当日
遺言者本人が、公証役場に出向いて公証人と面談します。このときに必要なのは以下の通りです:- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(実印が望ましい)
- 証人2名の同席
- 手数料(金額は事前に伝えられます)
- 口述と確認
遺言者が自分の遺言内容を口頭で述べ、公証人がこれを法的に整った文章にまとめます。作成された遺言書の内容は、本人と証人に読み聞かされ、確認が取れれば署名・押印をします。 - 公証人による作成・保管
完成した遺言は公証人が原本を保管し、遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。これにより、家庭裁判所の検認は不要となります。
● 現行制度のポイント
- 原則として対面での手続きが必要
- 証人2名の立ち会いが必須
- 作成後の原本は公証役場で厳重に保管
- 家庭裁判所の検認が不要なため、確実性が高い
このように、現在の公正証書遺言は「手間はかかるが、安全性と信頼性が高い」という制度です。ただし、高齢者や遠方の方にとっては、移動や証人の確保といった面で負担が大きいのも事実です。
その負担を軽減し、より多くの人が遺言を作成しやすくなることを目的として、いよいよデジタル化が導入されようとしています。
2. デジタル化で何が変わる?|制度のポイント
公正証書遺言のデジタル化により、これまで対面を前提としていた遺言作成手続きの一部が、オンラインで行えるようになります。
法務省は2025年中の実施を目指しており、すでにシステム開発と運用に向けた準備が進められています。
では、具体的にどのような点が変わるのでしょうか?
● 遠隔での面前手続きが可能に
これまで遺言者は公証役場に赴いて、公証人と直接面談する必要がありましたが、デジタル化後はオンラインでの面談(ビデオ通話)が認められるようになります。
このときには、顔認証技術などを用いたeKYC(オンライン本人確認)が導入される予定です。
本人確認の厳格性を維持しつつ、高齢者や地方在住の方も負担少なく手続きが可能になります。
● 電子署名による意思表示
公正証書遺言では、本人が署名・押印をする必要がありますが、デジタル化により電子署名での意思表示が可能になります。
電子署名には本人性と非改ざん性を担保する技術的基盤があるため、対面での署名と同等の効力を持たせることが可能です。
この仕組みにより、手続きの全体がペーパーレスで完結するようになります。
● 公証人による作成・保管も電子化へ
これまでは紙で作成された原本が公証役場に保管されていましたが、今後は電子データとしての保管も可能になります。
すでに「電子公証制度」自体は商取引分野で先行導入されており、今回の遺言分野への展開はその応用といえます。
これにより、公証役場側でも業務の効率化が進み、利用者にとっても書類の紛失リスクが軽減されるメリットがあります。
● 証人の扱いについては未確定
現行制度では証人2名の立会いが法律上必須とされています。
ただし、遠隔手続きの導入に際し、証人もオンラインで同席できるようにする方向で検討が進められています。
一方で、法改正が必要となるような変更(例:証人不要にする等)は現時点では予定されておらず、制度の根幹部分には大きな変更はないと見込まれます。
このように、デジタル化は「公正証書遺言の本質を損なわずに、手続きの利便性を高める」改革であるといえます。
3. 具体的な流れ|オンラインで公正証書遺言を作る手順(想定)
デジタル化された公正証書遺言は、どのような手順で作成されるのでしょうか?
本稿執筆時点(2025年7月)では、制度の詳細な運用マニュアルはまだ公表されていませんが、これまでの発表資料や他の電子公証制度との類似性から、おおよその流れを以下のように想定できます。
ステップ1:事前相談・原案作成(オンライン対応可)
まずは、遺言の原案について公証人や専門家(行政書士・弁護士など)と相談します。
この段階では、従来と同様に面談・メール・電話などを通じて、遺言内容や必要書類について確認しながら準備を進めます。
なお、相談や原案のやりとり自体は、これまでもオンライン対応されていたケースも多く、デジタル化後も大きな変更はありません。
ステップ2:オンラインによる本人確認(eKYC)
遺言作成当日、本人確認をオンライン上で行います。
この際には以下のような仕組みが想定されています:
- 顔写真付きの身分証(マイナンバーカードや運転免許証など)を提示
- ビデオ通話での顔認証・本人確認(eKYC)
- 公証人による口頭での意思確認
このeKYCの仕組みにより、公証人が遺言者本人の意思能力や自由意思をしっかり確認できることが前提となっています。
ステップ3:オンライン面談(Zoom等)
本人確認後、Zoomなどのビデオ会議ツールを用いて、公証人との正式な面談が行われます。
ここで、遺言内容を読み上げながら最終確認し、必要に応じて証人もオンラインで立ち会います(同席または別回線での参加が想定されます)。
ステップ4:電子署名による遺言作成
遺言内容に問題がなければ、本人が電子署名を行います。
これにより、「署名押印に代わる意思表示」がなされたと認められ、公正証書遺言として成立します。
公証人側でも、所定の手続きと電子署名を施したうえで、遺言データを正式な公正証書として確定させます。
ステップ5:正本・謄本の交付とデータの保管
完成した公正証書遺言は、従来と同様に「正本」「謄本」が交付されますが、電子データの形での交付も選択できるようになると見込まれています。
原本は公証役場のシステムで厳重に保管され、将来の相続手続きで必要になった際にも、スムーズに内容確認や証明が可能になります。
このように、手続きの要所は従来と同じながらも、「どこにいても」「紙を使わずに」作成できる点が大きな進化といえるでしょう。
4. デジタル化のメリット
公正証書遺言のデジタル化のメリットには次のようなものがあります。
● 公証役場に行かなくて済む
これまで必須だった公証役場への来訪が不要になることで、身体の不自由な方や遠方に住む方にとって大きな負担軽減となります。
特に高齢者や地方在住の方にとっては、物理的・心理的なハードルが大きく下がります。
● 時間と手間の短縮
オンラインで完結するため、証人の手配や交通手段の調整など、従来の煩雑な準備が簡素化されます。
また、行政書士などの専門家に相談→そのままオンライン作成へ進めるという流れもスムーズになりそうです。
● ペーパーレスで管理しやすい
紙の書類は紛失リスクや保管の手間がありますが、電子データで保管されることで相続時の確認・手続きもスムーズになることが期待されます。
5. 制度利用の注意点
このように公正証書遺言のデジタル化は、手続きのハードルを下げる画期的な制度改革ですが、次のような注意点もあります。
● パソコンやスマホ環境が必要
オンライン手続きを行うには、ある程度のデジタル機器とネット環境が必要です。
「カメラ付きの端末」「安定した通信環境」「電子署名の操作」など、機器操作に不安がある方にとっては障壁となる場合があります。
● ITリテラシーの差が利用可否に影響
オンラインに慣れている人には非常に便利ですが、インターネットやZoomの操作に不慣れな高齢者層には逆に負担となることもありえます。
必要に応じて、家族や専門家によるサポートが重要になります。
● 制度の詳細はまだ流動的
執筆時点(2025年7月)では、運用マニュアルや具体的な運用基準が整備中の段階です。
そのため、地域の公証人や実務担当者によって対応にばらつきが出る可能性がある点には注意が必要です。
制度は確実に前進していますが、「すべてがオンラインで簡単にできるようになる」というイメージを持ちすぎないことが大切です。
あくまで、“利用者にとっての選択肢が広がる”という視点でとらえると、現実的な理解につながります。
6. まとめ|公正証書遺言は、より使いやすく進化していく
これまで「公証役場に行くのが面倒」「証人を頼みにくい」といった理由で敬遠されがちだった公正証書遺言。
そのハードルを大きく下げるのが、今回のデジタル化による制度改革です。
オンライン面談、電子署名、電子保管といった技術の活用により、手続きの利便性は大きく向上します。
とくに高齢者や地方在住の方、日中に動きづらい方にとっては、自宅にいながら正式な遺言を作成できる可能性が開かれるという意味でも大きな前進です。
一方で、制度の詳細はまだ整備途中であり、すべての方にとって“完全に簡単・便利”というわけではありません。
どの形式の遺言が自分に合っているのか、どこまでオンラインを活用できるのかを、今後しっかりと見極めていく必要があります。
—
「人生の最期に伝えたいこと」を、確実に届けるために。
公正証書遺言は、今後ますます身近な手段となっていくはずです。
そして、その変化を上手に取り入れることが、安心できる相続の第一歩になるでしょう。
👇 専門家のサポートで、想いがきちんと伝わる遺言を
相続の準備は、「何をどう分けるか」という技術的な問題と同時に、「どうすれば家族が安心して次の一歩を踏み出せるか」という感情的な側面も含んでいます。
だからこそ、遺言書を作成する際には、形式だけに頼るのではなく、第三者である専門家のアドバイスを受けることが、家族にとって一番の安心材料になります。
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を承っています。
大切な遺志を確実に届けるために、今できる備えを一緒に考えてみませんか?