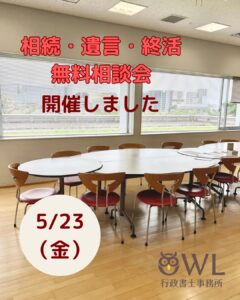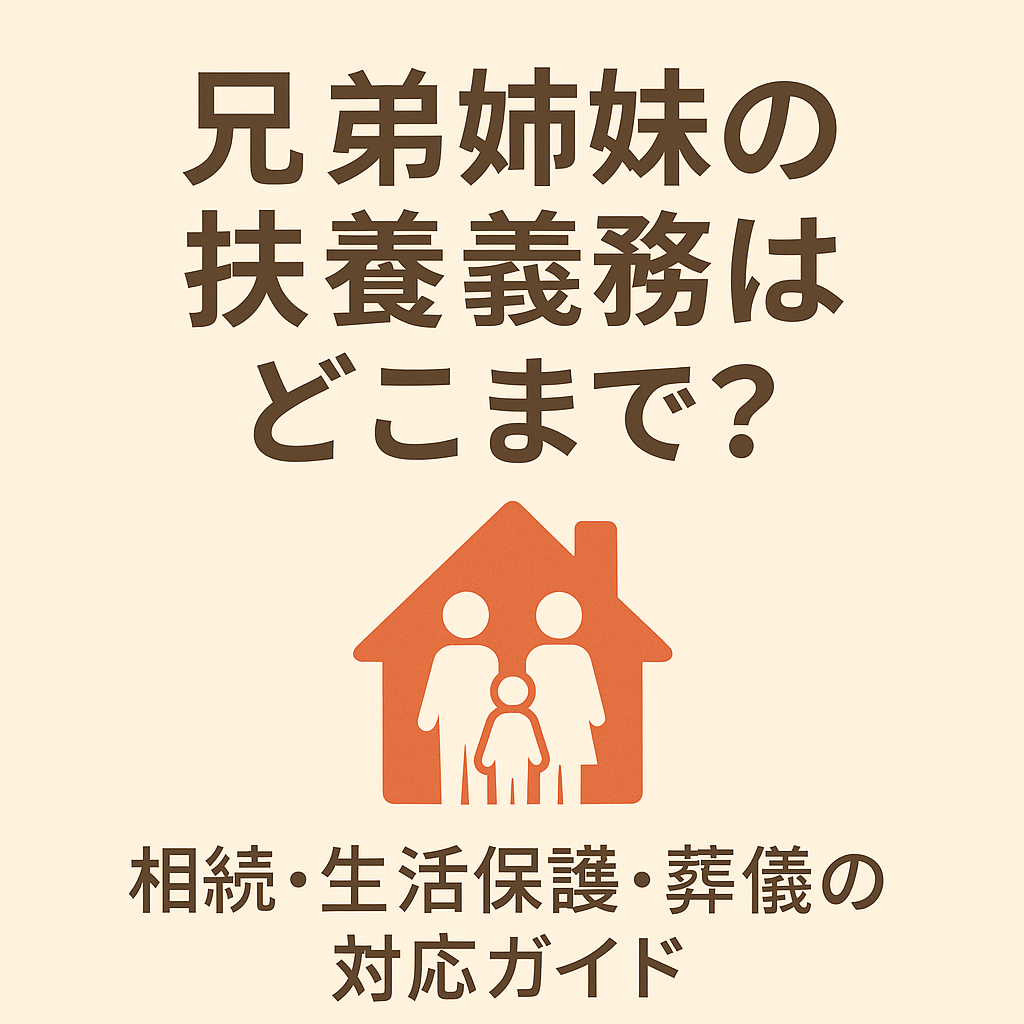
「兄弟だから仕方ない…」
そう思って長年、経済的な援助を続けてきたけれども、相手は働くこともせず、生活を改めようともしない。限界を感じながらも、「家族だから見捨てていいのか?」という葛藤に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そんなときに立ちはだかるのが、「扶養義務」という法律上の言葉。
確かに民法には、親族間で互いに扶養し合う義務があるとされています。
けれど、この扶養義務、どこまでが本当に法的に「しなければならない」ことなのでしょうか?
本記事では、兄弟姉妹における扶養義務の法的な実態と、
相続、葬儀、相続放棄といった関連するテーマまで、できる限り分かりやすく解説します。
「扶養義務」とはそもそも何なのか?
民法第877条第1項には、次のような規定があります。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
この条文だけを見ると、「兄弟姉妹は互いに助け合うべきで、援助を拒否してはいけない」と感じるかもしれません。
しかし、実際には、すべての扶養義務が同じ重さではありません。
民法上の「扶養義務」には2つの種類があります。
扶養義務には2つのレベルがある
「生活保持義務」:親子・夫婦に課される強い義務
親と未成年の子(経済的に自立していない子)との間、あるいは夫婦間には、非常に強い扶養義務が存在します。これを「生活保持義務」と呼びます。
これは、自分の生活水準と同等の生活を、相手にも保障するというレベルの義務です。
たとえ自分自身が経済的に余裕がない場合であっても、一定の生活を相手に維持させる義務があるとされます。
たとえば、自分では生活できない未成年の子に対して、その父母が一定の収入を得ていれば、その収入の中から子の生活費を確保する責任を負うことになります。
「生活扶助義務」:兄弟姉妹などに課される限定的な義務
一方で、兄弟姉妹の間の扶養義務や成人済みの子と親との間の扶養義務は、これよりもずっと緩やかです。
こちらは「生活扶助義務」と呼ばれます。
これは、
- 自分の生活に明らかな余裕があり、
- 相手に真に扶養を必要とする事情がある場合に限り、
- 生活に最低限必要な援助を行うべきとされるものです。
つまり、
- 自分自身の生活が苦しければ、援助を拒否できる
- 相手が働けるのに働いていないなど、自立可能な状況であれば、扶養を断っても違法ではない
ということになります。
働かない兄弟を支え続けなければならないのか?
それでは、働けるのに働こうとしない兄弟に対しても、扶養義務はあるのでしょうか?
まず前提として、民法上の扶養義務(生活扶助義務)は「真に生活に困っており、自分ではどうにもできない人」を対象にしています。
働く能力があるのに働かないというのは、扶養の必要性が否定されたり、大幅に縮減される可能性が高いです。
過去の裁判例でも、「就労可能であり、なおかつ努力をしていない人」については、扶養請求が認められなかった事例が複数あります。
たとえば、
- 就労支援の制度を活用していない
- 生活保護の申請すらしていない
- 働ける年齢・健康状態であるにもかかわらず、援助だけを求めている
といった場合、援助の拒否は法的にも正当化されうるのです。
また、「今まで援助してきたから、これからも当然支援し続けるべき」ということでもありません。
むしろ、支援を継続してきたことによって、精神的・経済的に疲弊してしまったのであれば、それは支援をやめる正当な理由として扱われる可能性さえあります。
相手に過度な依存心や浪費傾向が見られるようになっているのであれば、それを理由にして「これ以上の支援は行わない」と意思表示することは、法的にも、倫理的にも妥当な対応です。
扶養を法的に拒否するには?|できることと注意点
では、このような場合に具体的にどう対応していけばよいかを整理しておきましょう。
家庭裁判所で扶養の「調整」や「拒否」を申し立てる
相手がしつこく金銭援助を要求してきたり、扶養を法的に請求してくる場合は、家庭裁判所に扶養調停や審判を申し立てるという方法があります。
家庭裁判所は、
- 双方の収入や生活状況
- 扶養される側の自立努力の有無
- 扶養する側の精神的・経済的負担
などを総合的に考慮して、扶養の範囲や金額、あるいは「扶養の必要なし」という結論を導き出します。
これは「兄弟間の関係を明確に法的に整理する」という意味で、非常に有効な手段です。
拒否の意思を明確に示す(通知文・内容証明)
裁判所を使わなくても、まずは「これ以上は支援しません」という意思表示を文書で明確に伝えるだけでも事実上の効果があります。
書面やメールで通知をしたり、内容証明郵便を使うという方法があります。ただし、感情的に相手を刺激することにならないように文面等には十分に注意が必要です。
相手が生活保護を受けている場合は?
生活保護制度では、扶養義務者(兄弟など)に対して「扶養照会」が行われることがあります。
これは任意回答であり、法的義務ではありません。
生活扶助義務の範囲では、「扶養できる経済的余裕がない」「精神的負担が大きい」といった理由があれば、扶養を断ることは正当とされています。
兄弟が亡くなったら、後始末の義務はあるのか?
扶養の問題とは別に、もうひとつ多くの人が悩むのが「兄弟が亡くなったとき、自分が後片付けをしなければならないのか?」という点です。
「病院から遺体の引き取りを頼まれたが関わりたくない」
「連絡も取っていなかった兄弟の葬儀や埋葬まで自分がやらなきゃいけないの?」
結論からいえば、兄弟姉妹に対して法的に“後始末の義務”はありません。
遺体の引き取り義務は法的にない
病院や警察から「ご兄弟が亡くなりました。引き取りをお願いします」と連絡が来ることがあります。
しかし、これはあくまで協力要請であり、法的な義務ではありません。
対応できない場合には、「引き取れません」ときっぱり伝えて構いません。
対応しないからといって違法行為になることはありませんし、罰則もありません。
誰も遺体を引き取らない場合、行政(市区町村)が「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」として対応し、簡素な火葬・埋葬が行われます。
葬儀や埋葬の費用負担も強制されない
「兄弟だから葬式を出す義務がある」と思い込んでいる人もいますが、民法上も墓地埋葬法上も、兄弟姉妹に葬儀・埋葬の義務は明文化されていません。
財産がなければ、葬儀は簡易に済まされ、費用は自治体が負担します。
どうしても心情的に関わりたくない場合は、その旨を伝えて他の親族か自治体に任せることが可能だということです。
相続人となると責任が発生することも
ただし、ここで注意すべきは、「自分が相続人である場合」です。
仮に故人にわずかでも財産があり、自分が相続人として何らかの財産を受け取ると、その瞬間に“葬儀・遺品整理などを含む責任”が事実上発生します。
そうした負担を避けたい場合は、「相続放棄」をするのが現実的といえるでしょう。
相続放棄には相続開始(死亡)から3ヶ月以内という期限があるので、死亡を知ったらすぐに対応する必要があります。
生前にやっておくべきこと
兄弟との関係がすでに断絶している場合、「亡くなった後、相続にも関わりたくない」と思うのは自然なことです。では、生前のうちに「私は相続放棄するから」と宣言しておけば、それで済むのでしょうか?
実は、生前に「相続放棄します」と言っても、法的には一切効力がありません。法律上の相続放棄は、相続開始後(=死亡後)に家庭裁判所に申し立てる必要があるからです。
とはいえ、事前に備えておくことはできます。
- 相手が亡くなったときのために、家庭裁判所での相続放棄手続きの流れを確認しておく
- 死亡の連絡が来た際に速やかに放棄の申述を行うための書類(戸籍など)を調べておく
- 親族や関係機関に「私は相続には関与しないつもりです」という意思表示を事前に共有しておく
これらは法的効果はなくとも、実務的なトラブル回避に大きく貢献します。
おわりに|「扶養」と「家族のつながり」の線引きを考える
兄弟姉妹の関係は、必ずしも仲の良いものばかりではありません。
特に、経済的援助が一方的に続くような関係は、支える側にとって深刻な負担やストレスとなります。
本記事で紹介したとおり、
- 兄弟姉妹間の扶養義務は法的にも限定的であり、
- 支援を断ることも可能、
- 遺体の引き取りや葬儀も義務ではなく、
- 相続放棄によって関与を避ける選択肢もある
という点を理解しておくことで、必要以上に自分を責めることなく、自分の人生を守る決断ができるようになります。
「家族だから」と無理に背負い込まず、
法律的にどこまでが“責任”で、どこからが“善意”なのかという線引きを、一度考えてみてはいかがでしょうか。
👇 相続や家族の問題で、判断に迷っている方へ
ここまで読んでいただいた方の中には、
「法律上は問題ないと分かっても、気持ちの整理がつかない」
と感じている方も多いかもしれません。
相続や扶養、家族との距離感については、
正解がひとつではなく、状況によって考え方が変わります。
そうした判断に迷いやすいテーマなど相続・遺言・終活に役立つコラムを、
行政書士の実務目線で月1回ほどまとめています。