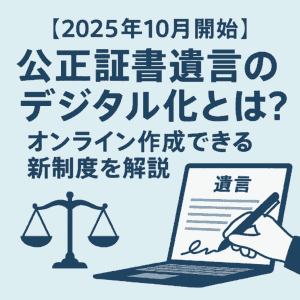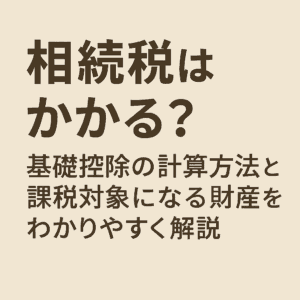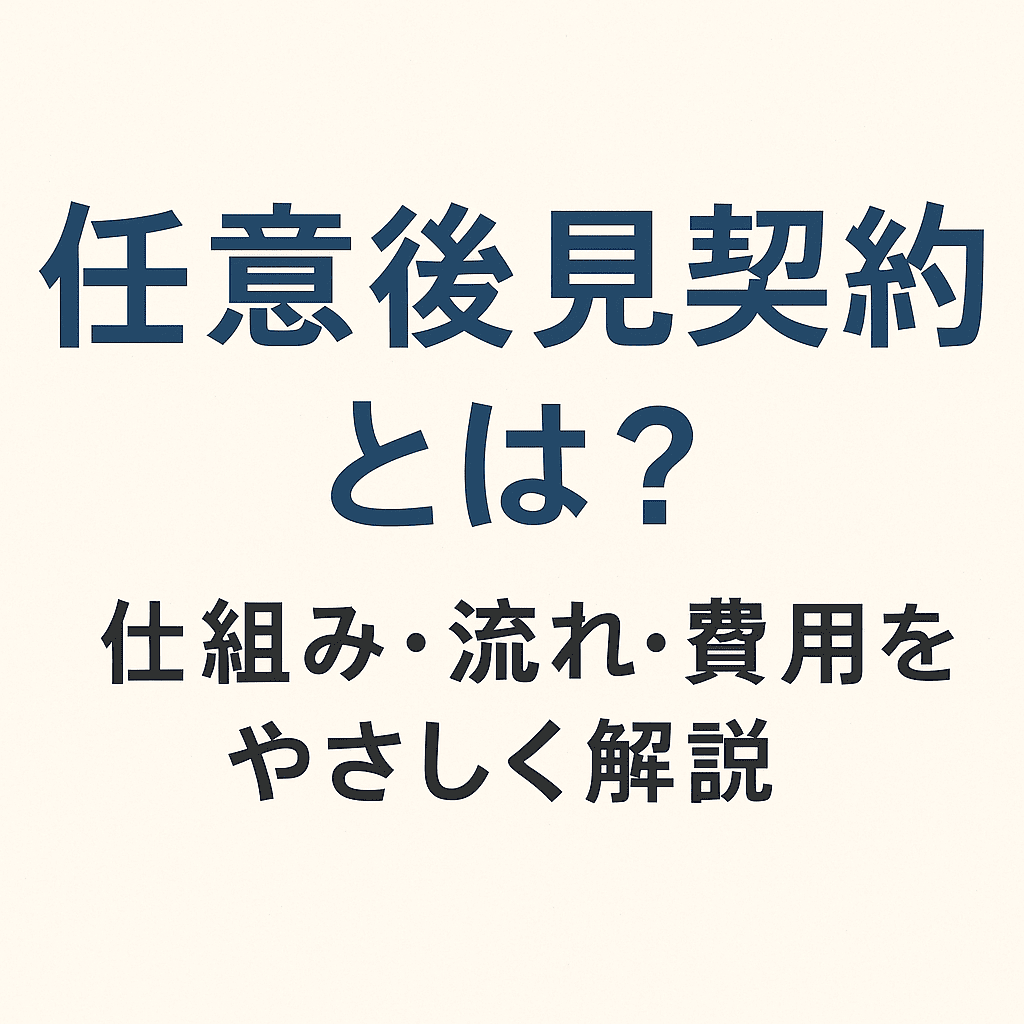
はじめに
「任意後見」という言葉を聞いたことはあるけれど、詳しくはよく分からない。そんな方も多いのではないでしょうか。
本人の意思決定を法律的に支援する後見制度には大きく分けて2種類あり、ひとつは民法に定められている法定後見(成年後見・保佐・補助)、もうひとつが今回取り上げる任意後見です。任意後見は「任意後見契約に関する法律」という特別法に根拠があり、自分で将来に備えることを前提とした制度です。
任意後見契約は、将来認知症などで判断力が落ちたときに、自分で選んだ人に財産管理や生活のサポートをお願いできる制度です。元気なうちに準備できる「もしもへの備え」の一つとして注目されています。
この記事では、任意後見契約について手続きの流れや費用をやさしく解説し、終活・認知症対策の一つとして知っておきたいポイントをまとめました。
1.任意後見契約とは?基本のイメージ
任意後見契約は、将来認知症などで判断力が落ちたときに、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に財産管理や生活のサポートをお願いできるという契約です。
契約の内容は公正証書で作成することが法律で定められており、家庭裁判所の関与もあるため、公的に守られた仕組みといえます。
2.手続きの流れ
1. 契約を結ぶ(元気なうちに)
まずは信頼できる人を任意後見人に選び、公証役場で契約書を作成します。ここでは「どんなことを任せたいか」を細かく決めることができ、生活に関わる契約や財産管理の方法などを自由に盛り込めます。
2. 判断能力が低下したとき
実際に認知症などで判断が難しくなった場合、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。この監督人が就くことで、任意後見契約が初めて効力を持ちます。
3. 契約がスタートする
家庭裁判所が任意後見監督人を選び、その監督のもとで任意後見人が活動を開始します。これにより、日常生活の支援や財産の管理がスムーズに行えるようになります。
3.法定後見との違い
「後見制度」というと、家庭裁判所が選任する法定後見と混同されやすいのですが、任意後見は仕組みが少し異なります。
- 法定後見 … 判断力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。誰が後見人になるかは裁判所が決定します。
- 任意後見 … 判断力があるうちに、自分で「誰に、どのようなことを任せるか」を契約しておける制度。
つまり、法定後見が「困ってから裁判所にお願いする仕組み」なのに対して、任意後見は「困る前から自分で決めておける仕組み」と言えます。
4.家族信託との違い
任意後見とあわせてよく比較されるのが家族信託です。
任意後見は「判断力が不十分になったときに効力が発生し、生活や介護の契約も含めて任せられる」のに対し、家族信託は「契約を結んだ時点ですぐに効力が発生し、財産を柔軟に管理できる」仕組みです。
ただし、家族信託には身上監護(介護や医療契約などの生活面の支援)は含まれないため、役割には明確な違いがあります。
5.メリットと注意点
メリット
- 信頼できる人を自分で選べる
- 任せたい範囲を柔軟に設定できる(財産管理、医療や介護契約など)
- あらかじめ準備しておくことで、将来の安心につながる
注意点
- 契約を結んでもすぐに効力が発生するわけではなく、判断能力が低下してから家庭裁判所が監督人をつけた時点でスタートする
- 監督人がついた後は、原則として終身で続くため、途中でやめることは難しい
- 後見人への報酬に加えて、監督人への報酬もかかるため、ランニングコストが発生する
6.任意後見の費用感
任意後見を利用するにあたっては、契約時と契約発効後の両方で費用がかかります。大まかなイメージを押さえておきましょう。
- 契約書作成時の費用
・公証役場の手数料は通常数万円程度。
・行政書士や司法書士など専門家にサポートを依頼する場合は、数万円〜十数万円程度の費用がかかります。 - 契約発効後の費用(判断能力が低下してスタートした後)
・任意後見人への報酬:月数万円程度が一般的。
・任意後見監督人への報酬:家庭裁判所が決定し、月1〜2万円程度が目安。 - 家庭裁判所への申立て費用
・任意後見監督人選任の申立てにも、印紙代や郵券代など数千円〜1万円程度の実費がかかります。
・申立てを専門家に依頼する場合は、別途10~15万円程度の専門家費用がかかります。
つまり「契約時にまとまった費用が必要」+「契約発効後はランニングコストが発生する」という点が、任意後見の大きな特徴です。
7.まとめ
任意後見契約は、将来に備えて自分の意思をあらかじめ形にしておく仕組みです。
- 信頼できる人を自分で選んで任せられる
- 契約は公正証書で行い、判断力が低下したら家庭裁判所の監督のもとでスタートする
- メリットがある一方、費用や「一度始まったら原則終身」という注意点もある
任意後見制度は認知症対策にとって有力な選択肢の一つです。遺言やエンディングノートと同じように、「知っておくだけでも安心できる選択肢」として覚えておくとよいでしょう。