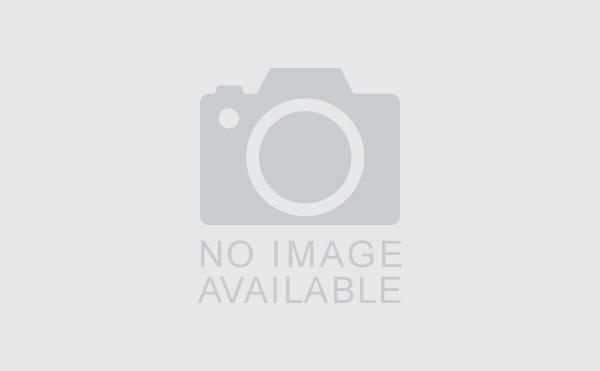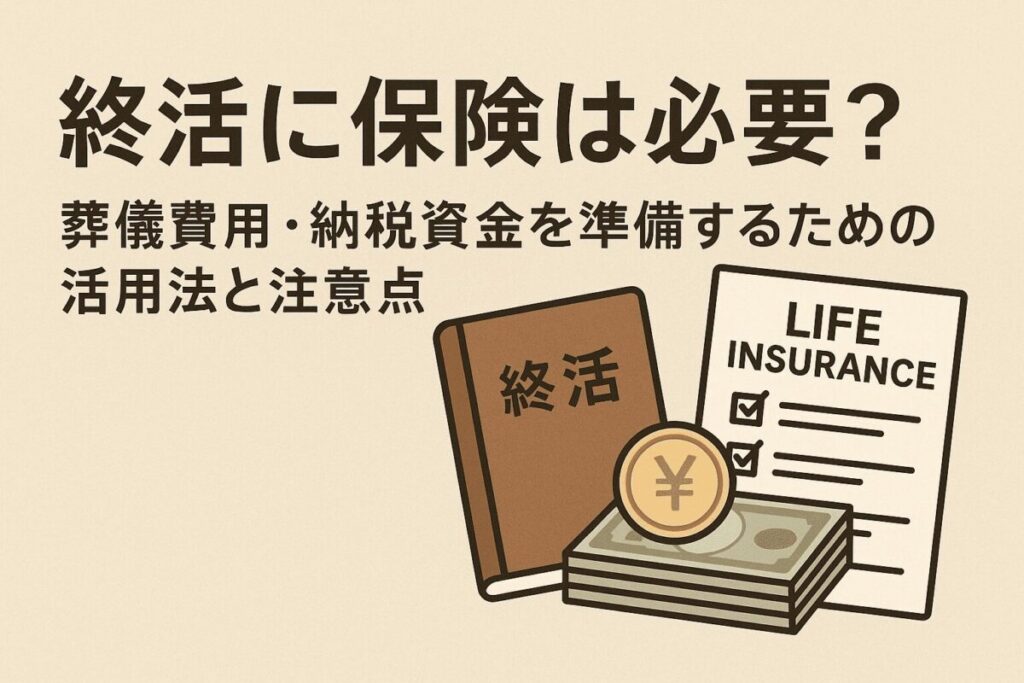
はじめに|終活と保険の関係
終活というと、遺言書やエンディングノートの準備を思い浮かべる方が多いですが、実際には「お金の準備」も大きなテーマになります。葬儀や医療・介護の費用、さらには相続税など、人生の最終段階ではまとまった資金が必要になる場面が少なくありません。
そのときに役立つのが「保険」です。保険金は受取人に直接支払われるため、銀行口座が凍結されてもすぐに現金を残せます。ただし、万能ではなく、年齢制限や相続税との関係など注意すべき点もあります。この記事では、終活における保険の活用法をメリット・デメリットの両面から整理します。
1. 終活で検討される主な保険の種類
終活で「保険を活用しよう」と考えたとき、実際に候補となる商品はいくつかあります。ここでは代表的な保険の種類を整理しておきましょう。
(1) 生命保険(終身保険・定期保険など)
最もオーソドックスなのが生命保険です。契約者が亡くなると、あらかじめ指定した受取人に保険金が支払われます。
特に終身保険は「一生涯の保障」が続くため、必ず保険金が支払われる点が特徴です。相続や終活においては、相続人にまとまった現金を残す手段としてよく利用されます。
一方、定期保険は「一定期間だけ」の保障なので、老後や終活に向けた備えとしてはあまり使われません。
(2) 医療保険・介護保険
病気やケガによる入院費、手術費をカバーするのが医療保険、要介護状態になったときに給付金が受け取れるのが介護保険です。
これらは「亡くなった後」の備えではなく、「生きている間の生活資金」を支えるためのもの。終活を広くとらえれば、自分の最期の過ごし方を安心して選ぶための支えになるといえます。
ただし、介護リスクや医療費は予測が難しいため、必要以上に保障を厚くしすぎると老後の保険料負担が重くなる点に注意が必要です。
(3) 葬儀専用保険(少額短期保険)
ここ数年で人気が高まっているのが「葬儀保険」と呼ばれる商品です。
保険金額は50万〜300万円程度と小ぶりですが、葬儀や埋葬にかかる費用をまかなうには十分。加入年齢が80歳や85歳まで認められている商品もあり、「高齢になってからでも加入できる」という点で注目されています。
ただし、少額短期保険は掛け捨てで、保障内容がシンプルである分、長期的な相続対策には不向きです。主に「葬儀費用を確保して家族に迷惑をかけない」という目的で利用されます。
2. 保険を活用するメリット
終活における保険の一番の魅力は、「万が一のときにすぐ現金を残せる」という点です。現金は相続や死後の手続きにおいて、最も汎用性の高い資産です。ここでは、終活で保険を利用するメリットを整理してみましょう。
(1) 葬儀費用などの即時資金にあてられる
人が亡くなると、葬儀や埋葬、初七日などの法要にかかる費用を、遺族はすぐに用意しなければなりません。
銀行口座は相続開始と同時に凍結されるため、自由に現金を引き出すことができません。その点、保険金は請求から比較的早く支払われるため、「葬儀費用の即時資金」として非常に役立ちます。
(2) 受取人を指定できる
保険の大きな特徴は、受取人を契約時に自由に指定できることです。
遺産分割協議を経ずに、直接その人に保険金が支払われるため、トラブル回避に有効です。特に「介護をよくしてくれた子に多く残したい」といった場合には、遺言と組み合わせて使うと意図を実現しやすくなります。
(3) 相続税の非課税枠を活用できる
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、
500万円 × 法定相続人の数 までの非課税枠が認められています。
例えば、法定相続人が3人いれば1,500万円まで非課税。適切に活用すれば、相続税の節税につながります。
(4) 不動産を相続させる場合の納税資金準備になる
「自宅や土地を特定の相続人に相続させたいが、相続税を現金で払えるか不安」というケースは少なくありません。
そのようなとき、生命保険を利用して「納税資金」を準備しておくのは有効な方法です。
保険金は現金で支払われ、しかも早期に受け取れるため、相続税の納税資金として使いやすいのです。
ただし、この場合も保険金自体に相続税がかかるため、非課税枠を超える部分は課税対象になる点に注意が必要です。
3. 保険のデメリット・注意点
保険は終活において有効な手段のひとつですが、メリットばかりではありません。実際に契約・活用する際には、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。
(1) 高齢になると保険料が高額になる
保険は加入時の年齢や健康状態によって保険料が大きく変わります。
例えば60歳と75歳では、同じ保険金額を設定しても保険料に大きな差が出ます。高齢で加入すると「保険料負担が重すぎて逆に老後資金を圧迫する」という事態になりかねません。
(2) 加入できる年齢に上限がある
一般的な生命保険は70歳前後までしか加入できない場合が多く、80歳を超えると選択肢は少額短期保険などに限られます。
「納税資金のために大きな保険を準備したい」と思っても、高齢になってからでは希望通りの契約ができないこともあります。
(3) 保険金も相続税の課税対象になる
保険金は受取人に直接支払われるため、遺産分割協議の対象には含まれません。
一方で、税務上は「みなし相続財産」とされ、相続税の計算には含める必要があります。
もちろん 500万円×法定相続人の数 までの非課税枠は活用できますが、それを超える部分は課税対象となります。
つまり「節税効果」は非課税枠の範囲内にとどまるという点には注意が必要です。
(4) 受取人の指定を放置するとトラブルに
受取人を指定できることはメリットですが、指定の更新を怠るとトラブルの原因になります。
たとえば、離婚後も元配偶者が受取人のままになっていたり、複数の子どもがいるのに一人だけが受取人になっていたりすると、遺産分割の不公平感から争いにつながることがあります。
(5) 保険に頼りすぎると全体の資産設計が歪む
保険は「安心の種」ですが、老後資金や日常生活に必要な資金を削ってまで契約するのは本末転倒です。
資産全体のバランスを見ながら、あくまで「終活の一部」として保険を位置づけることが大切です。
4. 高齢者が検討できる保険の選択肢
「終活で保険を使いたい」と思っても、すでに高齢の場合は加入条件が限られてきます。ここでは、70代・80代でも加入できることがある保険について整理し、どのように終活に役立てられるかを解説します。
(1) シニア向け終身保険
近年は「シニア世代でも入れる終身保険」が増えています。
- 加入可能年齢:70代前半〜75歳くらいまでが一般的
- 保険金額:数百万円〜1,000万円程度まで選べる場合もある
- 目的:葬儀費用の確保や、相続人に現金を残すために利用される
ただし、保険料は若年層より大幅に高くなるため、資金に余裕がある人向けです。
(2) 少額短期保険(葬儀保険)
「80歳でも加入可能」「最高85歳まで」という商品もあり、加入条件が比較的ゆるやかなのが特徴です。
- 保険金額:50万〜300万円程度
- 目的:葬儀費用や死後の事務のための即時資金を準備するのに適する
- メリット:掛け捨て型で手軽に契約できる
- デメリット:保険金額が小さいため、相続税の納税資金対策には不向き
(3) 医療・介護保険(高齢者向け商品)
70代後半でも加入できる商品は一部存在しますが、保険料は割高で保障内容も限定的です。
「相続対策」というよりは、「自分の介護費用や入院費用を子どもに負担させたくない」という目的で加入されるケースが多いです。
高齢期における保険活用の限界
- 大きな相続税対策(納税資金を1,000万単位で用意するなど)は難しい
- 実際には「葬儀費用を残す」「少しの現金を確保する」といった補助的な役割が中心になる
- 高齢期にまとまった現金を残す必要がある場合は、保険よりも 資産の組み換え(不動産の売却・生前贈与など) を検討した方が有効なこともある
5. 保険と他の終活手段の組み合わせ
保険は終活における便利なツールですが、万能ではありません。実際には「保険だけに頼る」のではなく、他の手段と組み合わせることでより安心できる備えが実現します。ここでは代表的な組み合わせ方を紹介します。
(1) 遺言書との組み合わせ
- 保険金は受取人指定によってスムーズに支払われますが、遺産全体の分け方を整理するには遺言書が不可欠です。
- 「保険金は長男に」「自宅不動産は次男に」といった形で使い分けることで、不公平感を減らし、トラブルを防ぐことができます。
(2) 家族信託との組み合わせ
- 高齢になって判断能力が衰えると、保険の見直しや資産管理が難しくなります。
- 家族信託を設定しておけば、信頼できる家族に資産管理を任せつつ、保険金の使い道(葬儀費用や納税資金)も含めた包括的な設計が可能です。
(3) 生前贈与との組み合わせ
- 子どもや孫に毎年少しずつ贈与していく方法は、保険より柔軟に現金を渡せる手段です。
- 保険で「万が一のときの即時資金」を確保しつつ、贈与で計画的に資産を移していくと、節税効果や生活支援の両立ができます。
(4) 預貯金・不動産の整理とあわせて考える
- 保険だけでなく、日常的に使う預貯金や不動産をどう扱うかが終活の核となります。
- 不動産を相続させる予定がある場合、納税資金を保険で補い、預貯金は生活費や医療費に回すなど、役割分担を意識するとスムーズです。
6. まとめ|保険は「安心のタネ」のひとつ
保険は「現金をすぐ残せる」点で終活において大きなメリットがあります。葬儀費用や納税資金を準備するのに有効ですが、年齢制限や税負担などの制約もあるため、過信は禁物です。
大切なのは、保険を「終活の一部」として位置づけ、遺言や信託、贈与など他の手段と組み合わせること。そうすることで、家族に安心を残し、自分自身も安心して最期を迎える準備が整っていきます。
👇 ご相談をご希望の方へ【初回無料】
保険は終活の選択肢のひとつにすぎません。遺言や家族信託など、他の方法とどう組み合わせるかが大切です。当事務所では、終活に関するご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。
初回60分は相談無料です。ご来所のほか、オンライン(Zoom)にも対応しています。