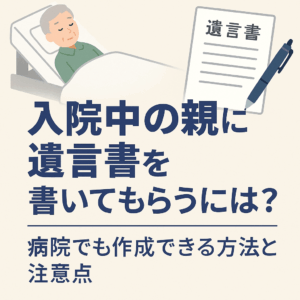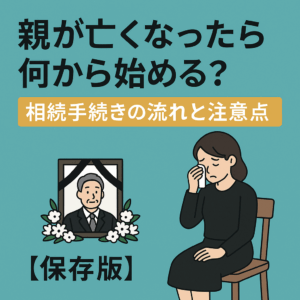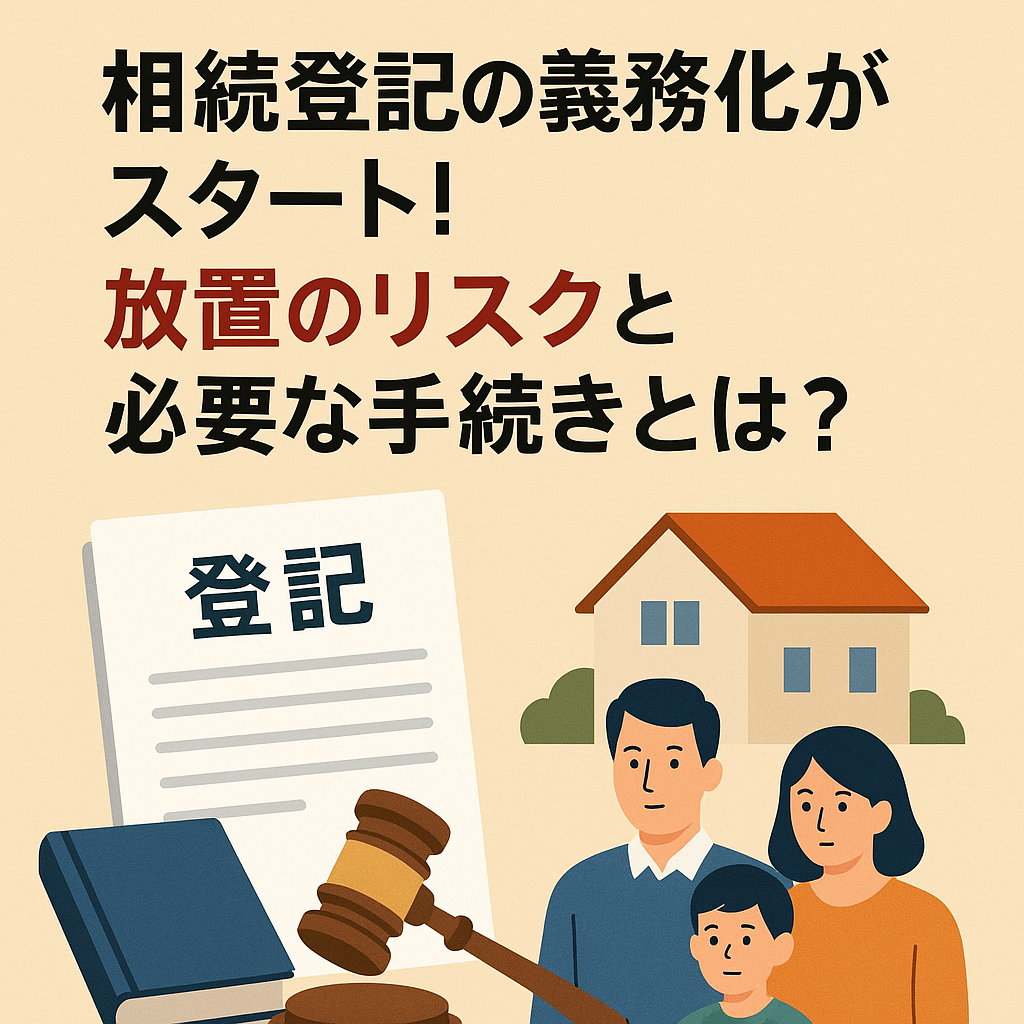
2024年の法改正で「相続登記」は義務に
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産について、登記の申請が義務化されました。これまでは相続登記をしていなくても法的な罰則はありませんでしたが、今後は放置することで過料の対象となる可能性があります。
これにより、不動産を相続した方は「期限内に登記しなければいけない」という新たな責任を負うことになります。知らずに放置してしまった場合、「いざ売却したい」「融資に使いたい」と思っても名義変更がされておらず、手続きが進められないといったトラブルにつながることも。
この記事では、相続登記の義務化について、対象となるケースや罰則の内容、必要書類、手続きの流れ、放置によるリスクまで詳しく解説します。今のうちに必要な準備を確認しておきましょう。
相続登記が義務になるのはどんなケース?
相続登記の義務化が適用されるケース
相続登記の義務化は、以下のようなケースに該当します:
- 2024年4月1日以降に相続が発生した不動産
- それ以前に相続が発生していたが、2024年4月1日以降にその事実を知った場合
つまり、「以前に親が亡くなって実家が親名義のまま」というケースでも、法改正以降にその相続を認識した時点から3年以内に登記しなければならないということになります。
違反した場合の罰則は?
相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料(罰金とは異なる行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
とはいえ、現時点では悪質なケースでない限りすぐに過料が科されるというよりは、「登記の促進を図るための仕組み」として機能する側面が強いと考えられます。それでも、長期間放置してしまえば法的リスクは無視できません。
相続登記の必要書類と手続きの流れ
相続登記に必要な書類
相続登記を行うには、以下のような書類を準備する必要があります:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(最後の住所が確認できるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 固定資産評価証明書(毎年4月以降に市区町村から取得)
- 遺言書または遺産分割協議書(法定相続で分けない場合)
- 相続関係説明図(法務局提出用)
手続きの流れ
- 相続人の調査(戸籍収集など)
- 不動産の情報確認(登記事項証明書を取得)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議または遺言書の確認
- 登記申請書の作成
- 必要書類を添えて管轄法務局へ申請
これらの手続きは一人でも可能ですが、戸籍の読み取りや申請書の作成は煩雑で、特に相続人が複数いる場合にはトラブルになりがちです。司法書士等の専門家に依頼すれば、スムーズかつ確実に進めることができます。
名義変更を放置したままだと起きるリスク
「そのうちやればいい」と相続登記を放置すると、さまざまなリスクが発生します。
売却・担保設定ができない
名義が故人のままだと、不動産を売却したり、金融機関に担保提供したりすることができません。いざ必要になったときに、手続きが間に合わないという事態になりかねません。
相続人が増えて手続きが複雑に
時間が経つほど、相続人が死亡して二次相続が発生するなど、関係者が増えます。その結果、協議が成立しにくくなり、手続きが膨大になります。
税金や管理費の負担があいまいに
名義変更をしていないと、誰が管理責任を負うかが不明確になり、固定資産税や修繕費を誰が払うのかで揉めることもあります。
法的な罰則リスク
前述のとおり、相続登記義務化により、将来的には過料が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない時代になってきています。
まとめ
相続登記の義務化は、多くの方にとって「今まで放置してきた問題」と向き合う契機となります。早めに登記を済ませることで、将来のリスクや手間を大きく減らすことができます。
当事務所では、提携司法書士と連携して相続登記を含む不動産の名義変更手続きを、必要書類の収集から法務局への申請まで一貫してサポートしています。
「まだ相続人同士で話し合いがまとまっていない」「何から始めればいいかわからない」といったご相談にも対応可能です。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。