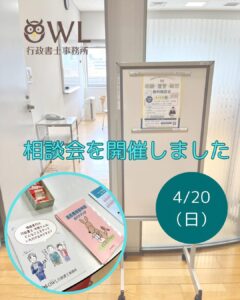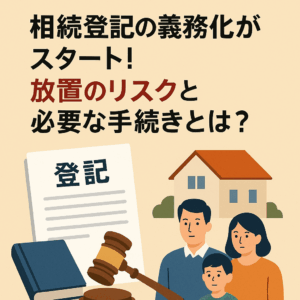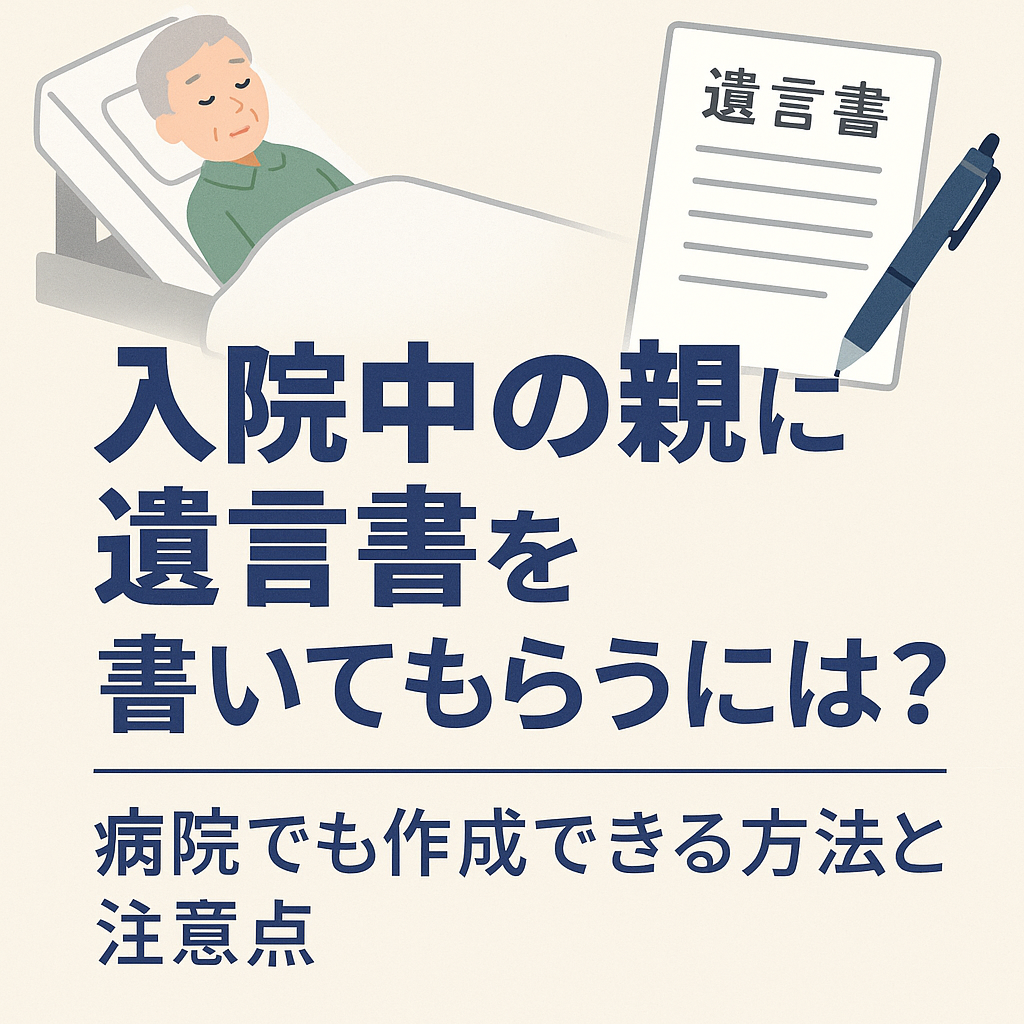
「入院中の親から『すべてお前に任せる』と言われたけれど、このまま何もせずに万が一のことがあったらどうしよう…」
そんな不安を感じている方は少なくありません。遺言書がないまま相続を迎えると、親の思い通りに財産が引き継がれない可能性があります。
本記事では、入院中でも遺言書を作成する方法と、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
まず確認すべきは「本人の意思能力」
遺言書は本人の自由意思に基づいて作成されるべきものであり、家族が書かせたいと思っていても、本人がその気でなければ無理に進めることはできません。
また、特に入院中で体調に不安がある場合には、「本当に遺言書を書ける状態なのか?」という点が非常に重要になります。つまり、ご本人が自分の考えをはっきりと伝えられる状態かどうか(法律上は「意思能力がある」といいます)を見極めたうえでの手続きとなるため、慎重な対応が求められます。
意思能力に疑いがあると、後々無効とされてしまうリスクもあります。
✅ 専門家としての実感
実際のご相談でも、「親は全部任せると言っているが、具体的にどうしたらいいかわからない」という声をよく聞きます。
まずは、ご本人に遺言の必要性を丁寧に説明することが第一歩です。
遺言書の作成方法は3つ
入院中でも作成可能な遺言書の方法は主に以下の3つです。
① 自筆証書遺言
本人が全文を自筆で書く方法。証人も公証人も不要で、手軽に始められます。
- メリット
・費用がかからない
・時間や場所に縛られない - デメリット
・書式ミスによる無効リスク
・病気や手の震えなどで書けない可能性
・亡くなった後に「検認」が必要
※2019年の法改正により、財産目録はパソコンでの作成が可能になりました。
✅ 自筆証書が向いているのは:
- 遺言の内容がシンプル(すべて配偶者に、など)
- 体調が比較的安定しており、筆記も可能な場合
② 公正証書遺言(病院出張対応可)
公証人が作成し、本人が口頭で意思を伝えてサイン・押印する方法。
病室に出張してもらうこともできます。
- メリット
・形式不備のリスクがない
・筆記できなくても作成できる
・検認不要 - デメリット
・費用がかかる(手数料+出張費など)
・証人2名が必要
・病院によっては面会制限あり
✅ 公正証書が向いているのは:
- 体調が安定していて、日程調整が可能
- 複数人に分けるなど、内容がやや複雑な場合
- 後々のトラブルを避けたい場合
③ 危急時遺言(緊急対応)
病状の悪化などにより、公証人を待つ余裕がない場合、3名以上の証人の立ち会いのもとで遺言を口頭で伝える「危急時遺言」という制度もあります。
ただし、20日以内に家庭裁判所の確認が必要です。
具体的な遺言作成の流れ(公正証書遺言を例に)
公正証書遺言を作成する際には、いくつかのステップを踏んで準備を進める必要があります。以下に代表的な流れを紹介します。
1. 専門家に相談(内容の整理と意思確認)
まずは行政書士などの専門家に相談し、ご本人の意思をしっかりと確認することから始まります。どのような財産を、誰に、どのように渡したいのかを整理しながら、遺言書の骨子を組み立てていきます。
2. 必要書類の収集(戸籍、財産目録など)
遺言書作成には、財産の内容や相続人を特定するための書類が必要です。たとえば戸籍謄本や固定資産評価証明書、預貯金の通帳コピーなどを準備します。これらは専門家が必要に応じてリストアップし、収集をサポートします。
3. 公証人と日程・内容調整
文案がまとまったら、公証人と連絡を取り、遺言内容の確認や当日の出張日程について調整を行います。病室などでの出張作成の場合には、本人の状態や病院側の対応についても事前確認が必要です。
4. 証人の手配
公正証書遺言には証人が2名必要です。ご家族や知人にお願いすることもできますが、守秘義務が求められるため、専門家側で証人を手配するケースも多くあります。
5. 病室で遺言作成(本人が口頭で確認→署名・押印)
当日は公証人と証人が病室を訪問し、本人の口から遺言内容を確認します。その後、公証人が作成した遺言書に署名・押印することで完成となります。体調や意思能力に問題がないかを見極めたうえでの手続きとなるため、慎重な対応が求められます。
費用の目安
入院中の遺言作成にかかる費用は、状況によって異なりますが、以下が一般的な目安となります。
- 公証人手数料:約2万円〜5万円(遺産総額に応じて変動)
- 出張費:数千円〜1万円程度(距離により異なる)
- 証人費用:1人あたり5,000円〜1万円程度(専門家に依頼する場合)
- 専門家への報酬:数万円〜(内容の複雑さや地域差あり。金融機関で依頼すると100万円を超えることも)
上記はあくまで目安です。「遺産の確実な承継」や「相続トラブルの予防」のための投資ととらえ検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ|大切なのは「意思能力があるうちに動く」こと
遺言書は、本人がしっかりとした意思を持っている間に作成しておくことが何よりも重要です。入院中であっても、体調が安定しており、意思確認ができる状態であれば、自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれも作成が可能です。
ただし、病状が進行して意思能力の判断が難しくなると、遺言作成そのものができなくなる可能性もあります。そのため、「もう少し元気になってから…」と先延ばしにせず、できるだけ早く準備を始めることが望ましいです。
✅ 専門家へのご相談をおすすめします
入院中の遺言作成には、病院側の対応確認や証人の手配、文案の検討、公証人との調整など、多くの専門的な判断と実務的な準備が必要です。
当事務所では、病室での出張による遺言作成サポートに対応しており、スムーズな準備をトータルでお手伝いしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。