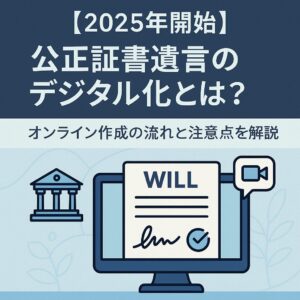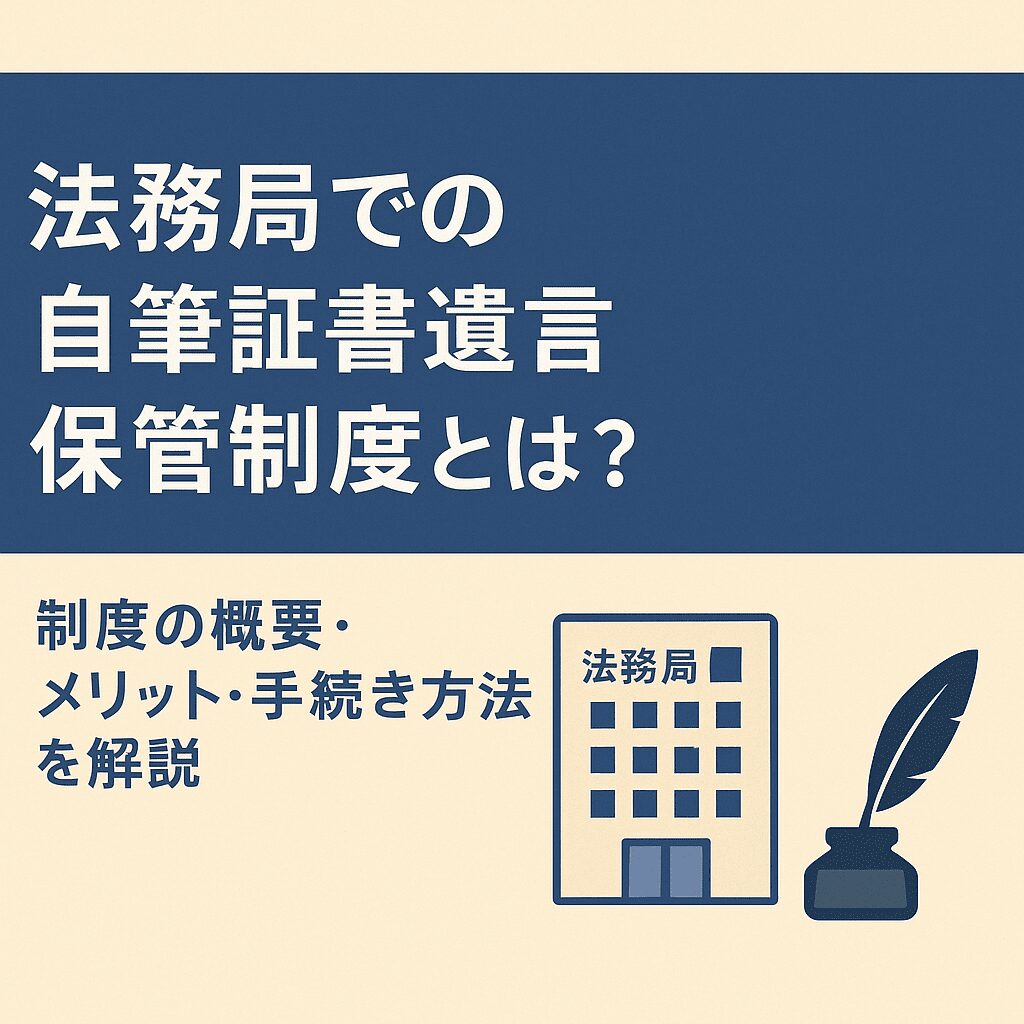
はじめに:なぜ今、「遺言書の保管」が重要なのか
「親が生前に遺言を残していたはずなのに、見つからない」「兄弟の一人が勝手に遺言書を処分したようだ」「せっかく遺言書があったのに、形式不備で無効になってしまった」――
こうしたトラブルは、相続の現場で決して珍しくありません。特に、自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は本人が紙に書いて作成するため、保管場所や管理方法に大きなリスクが伴います。どれだけ真剣に内容を考えても、それが適切に保管されず、死後に活かされなければ、遺言の意味は半減してしまうのです。
そんな問題を解決するために、2020年7月から新たに始まったのが、「自筆証書遺言の保管制度」です。この制度を使えば、作成した遺言書を法務局に安全に預け、確実に残すことができるようになりました。
この記事では、制度の概要から、具体的な手続きの流れ、他の遺言方法との比較まで、相続の現場で役立つポイントを詳しく解説していきます。
1. 法務局の遺言書保管制度とは
● 制度の概要と導入背景
自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日からスタートした新しい制度です。
これまで、自筆証書遺言は作成後に自宅で保管されることが多く、
- 発見されないままになってしまう
- 意図的に隠されたり破棄されたりする
- 改ざんや筆跡のトラブルで無効扱いになる
といった課題がありました。
また、自筆証書遺言を使う場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があるという煩雑さも、相続人にとっては負担でした。
こうした実務上の問題を軽減し、「誰もが安心して遺言を残せる社会」を目指して整備されたのが、この保管制度です。
● 保管の対象になる遺言の種類
制度の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。
公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外となるため注意が必要です。
ただし、保管できる自筆証書遺言にはいくつかの条件があります。
- 用紙サイズはA4に統一
- ホッチキス止めや封筒への封入は不可(裸で提出)
- 印鑑の押印が必要
- 財産目録を添付する場合はパソコン作成も可だが、各ページに署名・押印が必要
これらの形式要件を満たしたうえで、遺言者本人が法務局に出向いて申請することが制度利用の前提となっています。
2. 利用のメリット
では、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことで、どのような利点があるのでしょうか。以下に主な4つのメリットを紹介します。
1)検認が不要になる
通常、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。これは、遺言書の形式を確認し、偽造や改ざんを防ぐためのものですが、裁判所への申立てや戸籍の収集、相続人全員への通知など、多くの手間と時間がかかります。
しかし、法務局で保管された遺言書であれば、検認が不要です。相続人はそのまま各種の相続手続きに進むことができ、大きな時間短縮になります。
2)遺言書の改ざん・隠匿・破棄を防げる
遺言書を自宅などで保管していると、相続人のひとりがこっそり内容を書き換えたり、都合の悪い遺言書を破棄・隠匿したりするリスクがあります。
ところが法務局では、遺言書は厳重に保管され、第三者の手が届きません。また、受け取った日付や内容が記録されているため、改ざんは事実上不可能です。
遺言の真正性を担保し、トラブルの芽を摘むという点でも、保管制度の意義は大きいといえるでしょう。
3)死亡後、通知制度により遺言の存在を知らせられる
法務局の保管制度では、遺言者があらかじめ指定しておいた最大3名までの相手に対し、遺言者の死亡後に「遺言書が法務局に保管されている」旨を通知してくれる制度があります。
通知のタイミングは、遺言者の死亡情報が戸籍事務を担当する市区町村から法務局に伝わった後。文面には死亡の事実そのものは書かれませんが、通知を受けた人が、遺言の存在に気づく大きなきっかけになります。
「せっかく遺言を預けたのに、誰にも気づかれないまま…」という事態を防げるのです。
4)全国の法務局で閲覧・取得が可能
保管された遺言書の内容は、全国どこの法務局でも閲覧・証明書取得が可能です(ただし申請が必要)。
相続人が遠方に住んでいる場合でも、わざわざ遺言者の地元に出向く必要はなく、地元の法務局で手続きを行うことができるのは、大きな利便性と言えるでしょう。
3. 手続きの流れ
法務局の保管制度を利用するには、遺言者本人が出向いて手続きすることが必須です。代理人による申請や郵送での対応はできません。以下に具体的な流れを紹介します。
① 保管申請の予約をする
まずは、事前予約が必要です。予約は、インターネットまたは電話で行うことができます。
- インターネット:法務省の「遺言書保管制度」専用ページから予約
- 電話:申請先の法務局(遺言書保管所)へ直接連絡
保管を希望する法務局は、以下のいずれかの所在地に基づき選ぶことができます:
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
このうち都合のよい場所を選びましょう。
② 必要書類の準備
予約後、申請当日までに以下の書類を準備します。
- 遺言書(封をせず裸のまま)
※形式的な要件を満たしている必要があります。ホッチキス留めやノリ付けも不可です。 - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 遺言書保管申請書
法務局の窓口で取得するか、事前に法務省のサイトからダウンロード可能です。 - (希望する場合)通知対象者の氏名・住所情報(最大3名まで)
③ 法務局で保管申請手続き
予約日時に法務局へ出向き、以下の流れで手続きが進みます。
- 本人確認(写真付きの身分証による)
- 遺言書の形式確認(内容のチェックではなく、方式の要件を満たしているかの確認)
- 保管申請書とともに提出
※形式不備がある場合は、いったん受け付けられず返却されるので注意が必要です。
④ 保管証の受け取り
手続きが完了すると、「遺言書保管証」が交付されます。これは、遺言書が法務局に保管された証明として大切に保管しておきましょう。
この保管証があることで、遺言の存在を相続人に示しやすくなります。
詳しい申請方法や必要書類の様式については、法務省の公式ページでも確認できます。
👉 法務省|自筆証書遺言書保管制度のご案内
4. 費用と注意点
● 保管手数料は「3,900円」
自筆証書遺言の保管にかかる費用は、一件あたり3,900円(収入印紙)です。比較的安価で利用でき、家庭裁判所の検認手続きが不要になることを考えると、コストパフォーマンスは非常に高いといえます。
また、保管後の手続きにおいて、以下のような追加手数料が発生する場合があります:
- 閲覧請求(画像):1通につき300円
- 閲覧請求(原本):1通につき1,400円
- 遺言書情報証明書の交付:800円
※いずれも収入印紙による納付
● 制度利用時の注意点
いくつか誤解されがちな点や、注意すべきポイントを押さえておきましょう。
① 内容の法的有効性まではチェックされない
法務局で確認されるのは「方式の適合性」だけです。たとえば、以下のような点はチェック対象外です:
- 遺言の文言に矛盾がないか
- 相続人の記載が適切か
- 相続分が法律に反していないか
そのため、遺言書の内容に不安がある場合は、専門家に一度見てもらうことをおすすめします。
② 保管後の内容変更には再申請が必要
いったん法務局に保管した遺言書でも、内容を変更したい場合は、
- 既存の遺言書の撤回手続き
- 新たに作成し直した遺言書の再保管申請
という2段階の手続きが必要です。間違っても、新しい遺言書をただ書くだけでは前のものが無効になるとは限らない点に注意してください。
③ 通知対象者は最大3名まで指定可能
保管時に「誰に通知するか」を指定することで、相続開始後にその人たちへ「遺言書が保管されていた旨の通知」が自動的に送られます(※ただし、通知文に「死亡」の文言は含まれません)。
これは任意の制度であり、通知を希望しないことも可能です。
④ 自筆証書遺言以外は対象外
繰り返しになりますが、この制度の対象となるのは「自筆証書遺言」のみです。公正証書遺言や秘密証書遺言は保管できないため、あらかじめ形式を確認しておきましょう。
5. 他の遺言方法との比較
遺言には、自筆証書遺言以外にも「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」といった方式があります。ここでは、自筆証書遺言(法務局保管制度あり・なし)と公正証書遺言を比較し、それぞれの特徴を整理してみましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言(保管なし) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文を書く | 自分で全文を書く | 公証人が聞き取り作成 |
| 検認の必要性 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 保管場所の安全性 | 自宅など(リスクあり) | 法務局で厳重保管 | 公証役場で厳重保管 |
| 作成時の証人 | 不要 | 不要 | 証人2名が必要 |
| 内容の確認 | なし(自己責任) | 形式のみ法務局が確認 | 公証人が法的内容も確認 |
| 作成費用 | ほぼゼロ | 3,900円 | 数万円〜(財産額で変動) |
| 利用しやすさ | 非常に手軽 | 手軽だが出向が必要 | 専門家の関与で安心 |
| 改ざん・紛失リスク | 高い | 非常に低い | 非常に低い |
この比較からわかるとおり、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言は、「費用を抑えつつ、安全に遺言を残したい人」にとってバランスの良い選択肢です。
一方で、判断能力の低下が懸念される高齢者や、相続に関して法的な争いが想定される場合は、公証人が内容を確認してくれる公正証書遺言の方が安心といえるかもしれません。
まとめ:自筆証書遺言を“活かす”ために、保管制度の活用を
遺言書は、書いただけでは意味がありません。残された家族がそれを見つけ、読める状態で、法律的にも有効であってはじめて、遺言者の意思が実現されます。
その点で、法務局の保管制度は「遺言が確実に届く」可能性を大きく高めてくれる心強い制度です。
この制度はこんな方におすすめ
- 遺言書をできるだけ費用を抑えて自分で作りたい方
- 書いた遺言書を確実に残し、検認の手間を避けたい方
- 将来の相続人間の争いを未然に防ぎたい方
- 公正証書遺言のような煩雑さは避けたいが、安全性を確保したい方
ただし、前述のとおり内容の法的有効性までは保証されないため、少しでも不安があれば、専門家に相談したうえで作成・保管することをおすすめします。
▼ 遺言書の内容や作成に不安がある方へ
当事務所では、自筆証書遺言の作成や、法務局での保管制度の利用に関するアドバイスを承っています。
初回60分の個別相談(来所またはZoom)は無料です。お気軽にご相談ください。
✅ 相続対策として遺言を準備したい
✅ 法務局の保管制度を使いたいけれど形式が不安
✅ 公正証書遺言との違いも知りたい
という方に向けて、状況に応じたご提案をいたします。