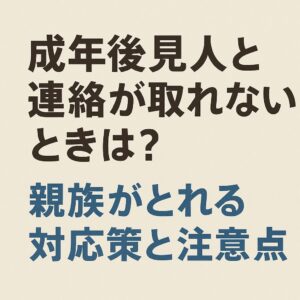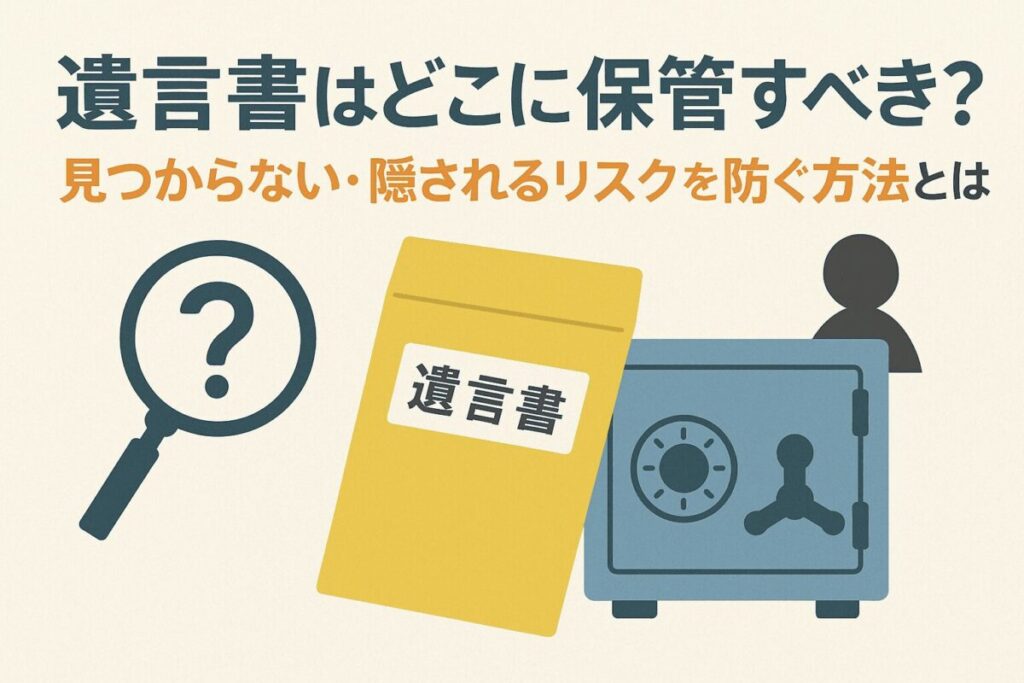
はじめに|遺言書は「書いた後」が大切
遺言書を書いたからといって、安心するのはまだ早いかもしれません。
せっかく法的に有効な遺言書を作成しても、適切に保管されていなければ、発見されないまま無効と同じ結果になってしまうことがあります。相続トラブルの多くは、実は「遺言書がない」ことよりも、「あったのに使われなかった」ケースに起因しています。
また、自筆証書遺言の場合は、保管の仕方ひとつで、破棄や改ざんといったリスクを招くこともあります。
この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの保管方法と注意点、法務局での遺言書保管制度、万が一見つからなかったときの影響、さらには破棄や隠匿を防ぐための考え方まで、**「遺言書をきちんと活かすための保管術」**をお伝えします。
自筆証書遺言の保管方法と注意点
自筆証書遺言は、自分の手で紙に書いて作成するシンプルな方式ですが、保管方法によって実効性に大きな差が出る点に注意が必要です。
自宅での保管にはリスクも
もっとも一般的なのが、自宅での保管です。封筒に入れて机の引き出しや金庫にしまっておく人も多いのですが、ここにはいくつかの落とし穴があります。
- 発見されない可能性がある
遺言書があることを家族に知らせていなかった場合、誰にも気づかれずに葬儀や相続手続きが進んでしまうことも。 - 故意に破棄・隠匿されるリスク
遺言の内容に不満を持つ親族がいた場合、見つけたとしてもその存在を隠したり、破ってしまうようなトラブルも現実に起こり得ます。 - 家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言は、たとえ封がされていても、相続開始後に**家庭裁判所での「検認」**という手続きが必要です。これに時間がかかると、相続手続き全体が遅れてしまうこともあります。
信頼できる第三者に預ける場合の注意点
行政書士や弁護士などの専門家に預ける、あるいは信頼できる家族に託すという方法もあります。これには次のような利点があります。
- 遺言の存在を確実に相続人に伝えられる
- 不正な破棄や隠匿のリスクが減る
ただし、預けた相手が亡くなったり、連絡が取れなくなる可能性もあるため、定期的な見直しや、複数人に所在を知らせておくなどの工夫が求められます。
法務局の保管制度を活用する選択肢
こうした自宅保管や第三者への預け方に不安がある方には、2020年に始まった**「自筆証書遺言書保管制度(法務局での保管制度)」**の利用がおすすめです。
この制度では、本人が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に持ち込んで預かってもらうことができます。これにより、
- 紛失や破棄、隠匿のリスクが大幅に減少
- 相続人は「検認手続きなし」で手続きに入れる
- 遺言が保管されていることを、一定の手続きにより相続人が確認できる
- 遺言者の死亡後、あらかじめ指定された最大3名までの相手に対して、「遺言書が法務局に保管されていること」を通知してもらえる制度がある(通知制度)※遺言者が希望する場合のみ実施
といったメリットがあります。
公正証書遺言の保管はやはり安心感がある
自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は公証人が作成をサポートし、原本を公証役場が保管してくれるため、保管面での安心感が大きいのが特徴です。
原本は公証役場に保管される
公正証書遺言の最大の強みは、原本が公証役場に半永久的に保管されるという点です。これにより、たとえ遺言者が持っていた謄本や正本を紛失しても、再発行が可能です。火災や盗難があっても、原本は安全に残るため、信頼性の高い方式といえます。
手元の正本・謄本も重要
ただし、遺言者自身が保管している「正本」や、相続人に渡している「謄本」は、相続手続きの際に必要になることがあります。
このため、
- どこに保管しているかを明確にしておくこと
- 信頼できる人に存在を伝えておくこと
が重要です。特に、誰にも知らせずに貸金庫などに入れてしまうと、死亡後に家族が開けられず、遺言が使えないままになってしまうことも。
「公正証書だから安心」は半分正解
たしかに、形式や保管という面では公正証書遺言は非常に優れています。しかし、遺言の存在を相続人が知らなければ、使われない可能性があるという点では、自筆証書遺言と同様の課題を抱えています。
したがって、
- 「公正証書にしておけば大丈夫」と思い込まないこと
- 遺言の存在と保管場所を、最低限1人以上には伝えておくこと
がとても大切です。
遺言書が見つからなかったらどうなる?
せっかく想いを込めて遺言書を作成しても、相続人がその存在に気づかなければ、遺言はなかったものとして扱われてしまいます。
「なかったことにされる」リスク
相続の手続きは、原則として「遺言がない前提(法定相続)」で進められます。遺言書の存在が判明しないまま遺産分割協議が終わってしまうと、後から遺言が見つかっても原状回復は難しいのが現実です。
たとえば、
- 相続人の一部にだけ遺言を知らせていた場合
- 家の中のどこかにしまい込んでいた場合
- 「遺言を書いた」と言い残したまま場所を誰にも伝えていなかった場合
などは、遺言があること自体が誰にも認識されず、そのまま終わってしまう可能性があります。
実際にあったトラブル例
- 遺品整理の途中で封筒が出てきたが、すでに遺産分割が終了していた
- 認知症の親が亡くなった後、遺言が出てきたが、自筆の体裁を整えていなかったため無効とされた
- 遺言書の存在を知っていた親族が、ほかの相続人に知らせなかった
こうしたケースは、特別な事例ではなく、実務の現場で日常的に起きていることです。
見つけてもらう工夫が大切
遺言書を有効に活用してもらうためには、「どこにあるか」を適切に伝えておくことが不可欠です。
- 家族に口頭で伝える
- エンディングノートに保管場所を記す
- 専門家に預けておき、連絡先を残しておく
など、遺言書の「所在情報」も遺言とセットで準備しておくことが、最終的な意思を確実に伝えるために必要です。
補足|故人が遺言書を残していたか分からないときは?
遺言書の存在を家族が知らず、「そもそも書いていたかどうかも分からない」という状況も少なくありません。そのような場合には、次のような方法で確認することができます。
- 自宅や貸金庫の書類を丁寧に整理して探す
特に封筒に「遺言書」や「重要書類」などと書かれているものに注意。- エンディングノートやメモ帳に手がかりがないか確認する
保管場所や作成の有無に関する記述がある場合があります。- 信頼していた専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に連絡を取る
相談履歴や保管の有無について情報が得られることも。- 法務局の「遺言書保管制度」を確認する
法務局で保管されていた場合、相続人等が「遺言書情報証明書」を請求することで存在を確認できます。このように、遺言の有無を確認する手段がいくつか存在するため、「知らないから存在しない」と即断しないようにすることが大切です。
破棄・隠匿・改ざんを防ぐには?
自筆証書遺言を作成した場合、その存在を知った誰かによって破られたり隠されたりするリスクがゼロではありません。特に、遺言の内容に不満を持つ相続人がいた場合に、トラブルの火種になりかねません。
民法にはペナルティもあるが…
民法第891条では、以下のような行為をした相続人は**「相続欠格」**として、相続権を失うと定められています。
- 故意に遺言者や他の相続人を殺害(または殺害しようと)した者
- 詐欺や脅迫によって遺言をさせた・取り消させた者
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
つまり、遺言書を勝手に破ったり、隠したりした相続人は、本来の相続分すら失う重大なリスクを負うことになります。
しかし実際には、
- 証拠が残らない場合には責任追及が難しい
- 他の家族が遺言の存在を知らなければ、隠匿されても気づけない
という現実的なハードルがあります。
トラブルを未然に防ぐ保管と伝え方
こうした事態を防ぐためには、「誰にも見つからないようにしまっておく」ことが逆効果になる場合もある、という視点が重要です。
トラブル防止のための具体的な対策としては、以下が挙げられます:
- 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
保管の事実は法務局のシステムで管理され、破棄・改ざんのリスクは大幅に減ります。 - 公正証書遺言を選択する
原本は公証役場に保管されるため、物理的な破棄・隠匿は不可能に近くなります。 - 遺言の存在を複数の人に知らせておく
一人だけでなく、複数人に存在を共有しておくことで、不正の抑止力になります。 - エンディングノートに「保管場所」と「万一の相談先」を書いておく
遺言と併せて家族が見つけやすい情報を残すことは、実務上非常に効果的です。
まとめ|安心できる保管と伝え方をセットで考える
遺言書は、**「書いたら終わり」ではなく、「見つけてもらい、正しく使ってもらってこそ意味がある」**ものです。どんなに内容が整っていても、見つからなかったり、無効にされたりしてしまえば、遺志を伝える手段とはなりません。
そのためには、以下の2つの視点をセットで考えることが大切です。
- 安心できる保管方法を選ぶこと
自宅保管・専門家への預け入れ・法務局での保管・公正証書遺言など、それぞれの特性を理解したうえで、自分に合った方法を選ぶ。 - 家族(または信頼できる第三者)に伝えておくこと
保管場所や存在そのものを、確実に伝える手段を用意する。たとえばエンディングノートやメモ、専門家の連絡先などを通じて「見つけてもらう仕組み」を整えておく。
特に法務局の保管制度や公正証書遺言を活用すれば、破棄や隠匿といったリスクを大幅に減らすことが可能です。「自筆だから心配」「誰にも見せたくないから家にしまう」ではなく、「大切な人に必ず届けるためにはどうするか?」という視点で考えてみてください。
せっかく作成した遺言書が、あなたの想いを確実に家族に届けるものとなるよう、保管方法と伝え方の工夫を今から準備しておきましょう。
おすすめの関連記事
📘自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?|失敗しない遺言書の選び方
→ コスト・手間・安全性の違いを比較。あなたに合った遺言書の選び方を解説します。
📘死後の手続きは誰がやる?知っておくべき死後事務委任契約のポイント
→ おひとりさまの不安を解消する死後事務委任の基本的な流れと注意点を紹介。
📘遺言執行者は相続人でもいい?選ぶときの注意点と専門家との違い
→ 誰を遺言執行者にすべきか迷っている方へ。実務面の注意点をまとめました。
👇 遺言書の保管に不安がある方へ|まずは無料相談をご利用ください
「せっかく遺言書を作ったのに、家族に伝わらなかったら…」「自宅保管で本当に大丈夫だろうか?」そんな不安をお持ちの方は、一度専門家にご相談ください。
当事務所では、事務所またはZoomによる初回60分無料の個別相談を承っています。遺言書の作成状況やご家族の事情に応じて、適切な保管方法や伝え方をご提案いたします。
大切な遺志を確実に届けるために、今できる備えを一緒に考えてみませんか?